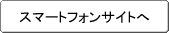| 霊的人類史は夜明けを迎える 第三部 霊性の〝夜明け前〟 第一章 スピリチュアリズムの予兆 (一) エマニュエル・スウェーデンボルグ ・致命的だったキリスト教の影響 ・〝新教会〟(ニューチャーチ)の偏向 (二) A・J・デービス ・スウェーデン・ボルグが支配霊 ・致命的欠陥 ・霊媒と人格 第二章 スピリチュアリズムの勃興 (一) ついに〝電話のベル〟は鳴った ・エプワース事件とハイズビル事件 ・フォックス夫妻の証言 ・五十年後の立証 付記 ・〝電話のベルが鳴る仕掛けは他愛もないが〟 (二) 現代の啓示──スピリチュアリズムの三大霊訓 ①─インペレーター霊団の自動書記と霊言による霊訓 ・大きかったスピーア博士夫妻の存在 ・モーゼスは人類の代弁者 ・危険をはらんだギリギリの選択 ②──ザブディエル霊団の霊感書記による霊訓 ・スピリチュアリズムのアニメーション ・二大特質 ③──シルバーバーチ霊団の霊言による霊訓 ・大きかったハンネン・スワッファーの存在 ・四つの思想上の特徴 | 第三章 既成宗教界とスピリチュアリズム (一) キリスト教会がとった態度 ・英国国教会の「スピリチュアリズム 調査委員会」による〝多数意見報告書〟 ・聖職権主義が〝真実〟をも葬る (二) 大幅な修正を迫られる仏教の来世観 ・天保十年丁亥八月廿四日夕陰霊出現発端の事 ・「無念のことありて割腹せし者の霊なり」 ・「死後の世界は生前に考えおるものとはいたく異なるものぞ」 ・「百里千里も一瞬の間にて行くべし」 ・「儒仏の説くところを信ずるは、みなその道におもねる者のすることにて」 ・霊の誓約書 ・いったん霊界へ戻る ・火事騒ぎ ・「今は包み難ければ物語らん」 ・災厄の原因と厄払い ・「いまだ墨痕の乾かざる四、五百年前の古筆を拝覧するとは・・・」 ・御霊遷しの神事 ・月いっぱいなるぞ 付記 (三) 普遍的宗教としての神道に求められているもの ・脚下照顧 ・いくら自国の遺産を誇ってみても ・もっとインターナショナルなものに ・スピリチュアリズムの原理に照らして総点検を もうすぐ人類史の二日目が始まる──あとがきに代えて |
第三部 霊性の〝夜明け前〟
第一章 スピリチュアリズムの予兆
本書のメーンテーマは、人類史における〝霊性〟の消長の過程を、主としてイエスとローマ帝国とキリスト教の絡み合いの中に見ることである。
霊性を失った時の人間は、獣性と変わらぬ恐ろしい残忍性をむき出しにすることがある。その最たるものを前節の最後で〝魔女狩り〟の中に見たのであるが、その実態は私が紹介したものよりはるかに残虐で陰惨なものだった。
が、いたずらにその残虐性をさらしものにすることは無意味であるし、本書のテーマからそれることにもなるので、そのありのままの実体を知りたい方は、私が紹介した書物をお読みいただきたい。
さて、さしもの狂気も十七世紀後半には下火となり、十八世紀末で完全に見られなくなるのであるが、その頃から、あたかもパブテスマのヨハネが新しい真理の伝道者の出現を予告したように、スピリチュアリズムの勃興の間近いことを予告する〝しるしと不思議〟が見られるようになってきた。
(一) エマニュエル・スウェーデンボルグ
霊に身をまかせてしまうタイプの霊能者、たとえば自動書記とか霊言を専門とする霊媒の場合にせよ、通常意識のまま霊視力や霊聴力を働かせたりインスピレーションを受けたりするタイプの霊能者にせよ、その仕事が生まれついた生活環境から受ける影響───なかんずく宗教的信仰───や常識的通念というものによって大なり小なり左右されることは、人間の宿命といってよい。
その中でもわれわれが意外に気づいていないものの一つに、ことばの影響がある。生まれついた国の言葉は、生涯にわたってその人間の精神的生活に影響を及ぼすと言ってよいほどの拘束力をもっている。
たとえば英語の water を〝水〟と訳すのは、厳密にいうと間違いである。同じく水でも、欧米人と日本人とでは頭に浮かべる概念が違うからである。これが〝カミ〟の観念になると世界の民族によってことごとく違うし、もしかしたら人間一人ひとりでも違っているかも知れない。
しかも、ここでいちばん大切なのは、地上の言語はあくまでも時間と空間にしばられた物的時限での伝達手段に過ぎず、したがって物質を超越し時空も超えた存在をことばで表現することは不可能である以上、地上のいかなる民族のカミの観念も完全では有り得ないということである。
さて、以上のような前置きをしたのは、十七世紀後半から十八世紀にかけて活躍した霊能者のスウェーデンボルグが、霊的能力も含めてあらゆる面で天才的な才能に恵まれ、数々の大きな業績を残しながら、残念なことに、その霊的産物にはキリスト教的偏向が見られると同時に、彼の信奉者がそれをさらに増幅する方向へもっていってしまった事実を指摘するためである。
・致命的だったキリスト教の影響
スウェーデンボルグは冶金学・採鉱学・工兵学・天文学・物理学・動物学・解剖学・財政学・経済学という数々の分野で〝権威〟とうたわれるほど造詣が深かったが、同時に司教だった父親の影響で〝母乳とともに神学を吸い込み〟(コナン・ドイル)、長じては熱心な聖書研究家でもあった。
彼は、バイブルは〝神の作品〟であると信じていた。ただしバイブルの言葉には表面とは違った意味があると主張し、さらに、その本当の意味を自分は天使から教わっている───それができるのはこの自分一人だけである、と信じていた。
コナン・ドイルは、スウェーデンボルグが〝自分は絶対だ〟と思いこんだことによる影響に比べれば、ローマ教皇の〝不謬説〟などは取るに足らないと言い、その理由は教皇の場合は特殊な議題で枢機卿を前にして評決を下すときだけ〝間違いを犯さない〟のに対して、スウェーデン・ボルグの場合は、自分が霊界へ行って見聞きしてきたものは何一つ間違っていないというのであるから、それを読む者への影響が大きいというのである。
スウェーデンボルグを高く評価している W・H・エバンズでさえ、A New Heaven (拙訳 『これが死後の世界だ』 潮文社) の中で、彼の思想には、〝暴君的〟といえるほどのキリスト教の影響があると言い、特に黙示録の影響が顕著であると述べている。
しかし一方スウェーデンボルグは、〝三位一体説〟や〝贖罪説〟といった神学上のドグマは否定している。性の問題でもパウロのような禁欲説は説いていない。悪の根源は利己主義にあると説き、この世は魂の精錬所であり、物的なものによって霊的なものが磨かれるのだという。
そういった点だけをピックアップしてみたかぎりではスピリチュアリズムと相通じるものがあるが、彼の膨大な量のラテン語の著作を読んだ者は、十人が十通りの、百人が百通りの新しい宗教をその中に見いだすのではないかと思われるほど、内容が混沌としているとコナン・ドイルは言う。
・〝新教会〟(ニューチャーチ)の偏向
それに加えてスウェーデンボルグにとって不幸だったのは───ここが有目的的スピリチュアリズムと違うところであるが───彼の信奉者によって結成された新教会 The New Church という集団が一種の新興宗教のように、スウェーデンボルグを絶対的な師にまつり上げ、折角の新しい潮流を逆流させてしまったことである。
このあとで紹介する A・J・デービスもスピリチュアリズム勃興前の霊能者であるが、デービスの場合、スピリチュアリズムが勃興するや、いちはやく賛同して陰に陽に支援したのとは対照的に、ニューチャーチはなぜかスピリチュアリズムと異なる側面ばかりを強調し、相通じる側面はことごとく無視する態度に出た。ためにスピリチュアリズムとの間に無用の敵対関係が生じてしまった。
この点についてコナン・ドイルは、霊的原理に照らせばスウェーデンボルグの著作の中には素晴らしい教説が沢山あり、近代の第一級の霊能者として、どこのスピリチュアリスト・チャーチにもその肖像画を飾ってもよいほどの人物なのに、ニューチャーチは、小異を捨てて大同につき共通の大義のために手をつなぎ合う洞察力に欠けていた、と断じている。
私見を述べれば、スウェーデンボルグ個人としては学者としても霊能者としても才能あふれる第一級の人物だったのかも知れないが、スピリチュアリズムという地球規模の霊的事業の計画の中には組み込まれていなかったことを物語っていると思う。
マイヤースの〝類魂説〟の中で述べられていることであるが、類魂の系譜の中で、ある特殊な一面、例えば音楽的才能ばかりが繰り返し顕現し続けると、モーツアルトやシューベルトのような天才が出現するという。
それと同じことが霊能者にも言える。長い歴史の中には霊的才能の天才が数多く輩出している。しかし当人にとっては必ずしも霊的仕事が使命ではないこともあり得るわけである。
何度も言うように、地上生活は不自由な物的環境の中で苦しみつつ努力するところに意義があるのであって、霊的な仕事にたずさわることばかりが偉いわけではないし、高尚というわけでもない。そういう人生を使命として生まれてくる高級霊もいるが、むしろ無名の平凡な人生の中で、霊界での飛躍的な進化にそなえて研鑽を積んでいる高級霊もいる───数からすればその方がはるかに多いのである。
ところが、人間は〝しるしと不思議〟の本来の意義を理解せずに、目を奪うような能力や現象に心まで奪われて、その霊能者自身を崇めるようになり、その人の教え以外にも目もくれないようになっていく。スウェーデンボルグが不幸だと言ったのは、そういう取り巻き連中によって心ならずも垣根をこしらえられてしまったからである。
ドイルによると、スウェーデンボルグは生涯かなり重度の吃音障害者だったために、思うことを存分に言って聞かせることができなかったのだという。それもたしかに不孝な条件の一つだったことは間違いないが、最大の不幸は、側近に優れた人物がいなかったことにあると私は見ている。
(二) A・J・デービス
〝育ち〟の点でスウェーデンボルグときわめて対照的なのが米国の霊能者アンドリュー・ジャクソン・デービスである。
スウェーデンボルグが司教の家に生まれ、当時としては第一級の高等教育を受け、しかも学問的才能に恵まれていたために、十指で数えられるぼどの分野で〝権威〟とうたわれるほどの業績を残し、そのうえさらに霊的能力を発揮して膨大な著作を残したのに対し、デービスは、その日の食事にも事欠くほどの貧しい家庭に生まれ、学校へも通えず、十六才になるまでに読んだ本はたった一冊だけだったというほど、学問とは縁遠い環境の中で育っている。
・スウェーデンボルグが支配霊
ところが面白いことに、そのデービスの中心的指導霊が、ほかならぬスウェーデンボルグだった。自叙伝の The Magic Staff(魔法の杖) によると、一八四四年三月六日、十七才のある日、半入神状態で外へ連れだされて、そのまま四十マイルも離れた山の方角へわけもわからず急がされた。
山中で我に帰ってみると、目の前に二人の品のいい男性がいて、一人から医学について、もう一人からは道徳について懇切な講義を受けた。それが一晩中続いた。のちにデービスは、前者は紀元二世紀のギリシャの医学者ガレンで、後者はスウェーデンボルグだったことを知ったという。(ちなみに、ガレンはその後、前出の治療家 M・H・テスターの中心的指導霊となってる。)
確かに彼は、当時彼は人体を透視して、病状を的確に述べていた。それも目の前にいる患者だけでなく、遠隔地にいる人でも同じことだったという。
スウェーデンボルグの影響は入神講演に良く表れている。デービスは入神講演が得意で、のちに The Great Harmonia (大いなる調和) と題する全四巻の大著となって出版されているが、その講演に立ち会ったことのある 二ユーヨーク大学のヘブライ語教授ジョージ・ブッシュ氏は次のように述べている。
《私はデービス氏がその入神講演の中でヘブライ語を正確に引用し、また、地理学上の知識も、たとえ何年間も勉強したとしても、あの年齢であれだけ知っているのは驚異と言えるほどのものを披露するのを聞いている。
歴史ならびに聖書関係の考古学、神話、言語の起原と共通性、地球上の各民族における文明の発達、等々に関する難解な質問に対して美事に答えている。その美事さは、キリスト教世界の図書館のすべてに通える特典を有する当代髄一の学者であっても名誉なことと言えるほどのものだった。
仮にあれだけの知識を、彼が靴みがきを止めてからの二年間でなく、生涯をかけて必死に勉強した末に獲得したものだったとしても、地上のかつてのどの天才も敵わないほどのものであるが、彼はそれまで、ただの一ページも読んだことがないというのである。以上の事実を私は厳粛なる気持ちで証言する。》
・スピリチュアリズムの勃興を予言
彼の思想は〝調和哲学〟の名称で広まり、詩人のロングフェロー、哲学者のエマソン、天文学者のローエル、その他、多くの知識人に大きな影響を及ぼし、同時にスピリチュアリズムにも貴重な貢献をしている。その頃はすでにハイズビル事件を皮切りに心霊現象への関心が沸騰していて、デービスもそれを新しい時代の幕開けとして歓迎していた。
一八四七年、すなわちハイズビル事件の前年に出版された Principles of Neture (大自然の原理) の中に次のような一節がある。
《肉体に宿っている霊 (人間) が高級界の霊と交信している───この場合も人間の方は無意識であって、そのことに気づいていない───ということは事実である。そしてこの事実が、間もなく、生きた証拠の形で地上に演出されるようになるであろう。地上世界はその時代の到来を、歓呼の声をもって迎えることであろう。内部の霊性が開発され、今すでに火星や木星や土星では当たり前とされている霊的交流が、地上に確立されるであろう。》
これは、言い変えれば、〝しるしと不思議〟が演出され、それが学問的に立証されるようになることを意味するもので、人間の霊性と霊の世界の実在、そして霊の威力を認識させるための手段だった。
つまり二千年前にイエスがユダヤの民族に身をもって範を示したものを、今度は世界的規模で、しかも科学的実証つきで示そうというものだった。
しかし、五感中心の生活を営んでいる人間はとかく現象的なものに興味が偏り、実験会を催しては面白がるばかりで、肝心の教訓的側面をおろそかにしがちである。
心霊現象の話題が英国へ飛び火して第一級の学者や文化人の理解を得て、一段と高度な発達を遂げはじめた頃、米国では相も変わらず現象面ばかりが関心の中心で、おまけにトリックによる詐欺事件まで横行し始めた。そうした傾向に対してまっ先に、そして最も厳しい批判を浴びせたのがデービスだった。
・致命的欠陥
デービスは一八二六年に生まれ、一九一〇年に八十四才で他界している。その間の著作は厖大なものにのぼるが、最近その復刻版が出はじめている。良さが再認識されていることの証拠であろう。私もそのほとんどを入手している。
それ以前にも、前出のエバンズの A New Heaven や J・C・レナードの The Higher Spiritualism に引用されてデービスの文章を訳しているので、その良さは十分に認識している。また、デービスの著書を全訳してほしいという要望も私のもとに寄せられている。が、なぜかその気になれないまま今日に至っている。
それが、このたびコナン・ドイルの History of Spiritualism を読んでみて、その原因として納得のいくものを発見した。ドイルはデービスを高く評価しながらも、次のようなことを述べている。
《・・・・・・しかし、彼の著作のかなりの部分に意味不明の箇所があり、非常に読みづらいことは認めねばなるまい。それは、彼がやたらに長たらしい単語を用いるからで、時には自分で単語をこしらえているところもある。それが品位を損ねているのである。》
言語に過敏なタイプの私には、その辺が鼻もちならなかったのである。なぜそうなったのか───これは実は、意外に大切なことを示唆してくれていると思われるので、私見を述べてみたい。
霊媒現象というのは基本的には霊媒が自己を滅却することによって発生するのであり、したがって霊媒は受動的な立場にあり、使用される道具にすぎない。その点の認識は普遍的なものであるが、そこから先、つまりだから霊媒は無学文盲の方がよいのかという点に関して、意見が大きく二つに分かれる。
その通り、霊媒は何も知らない方がよいという意見と、いや、なるべく教養を積み、幅広い知識を蓄えておく方がよいという意見である。
・霊媒と人格
これは霊能の種類によって答えが違ってくる問題で、たとえば、ただの物理現象の霊媒であれば、体質的にエクトプラズムを多量に持っていることが第一条件であって、教養も人格もさして関係はない。
日本におけるスピリチュアリズムの草分け的存在である浅野和三郎氏の未亡人・多慶子夫人には、亡くなられる直前まで、何度か横浜のお宅へお邪魔して思い出を伺ったことがあるが、その中で、浅野氏が何人かの物理霊媒を使って実験していた頃の話として、帰宅して晩酌をなさりながら、霊媒たちの品性が悪くて不快な思いをさせられることをグチっておられた話をされた。「嫌なヤツらだ!」 と憤慨されたこともあるという。
その程度の人間でも物理霊媒は務まるということである。だからこそ浅野氏は我慢して養成にあたったのであろう。
しかし一方、主観的霊能、なかんずく霊言と自動書記となると、霊媒の人格と教養が圧倒的な影響を及ぼす。その人格と教養の程度が霊的波動を決し、その波動の程度が、伝達される霊的メッセージの内容の程度を決するのである。つまり霊媒の霊的理解力が、その霊媒を通して伝えられる霊示の高さを決定づけるということである。
したがって当然、教養とか知識といっても、ただの〝生き字引き〟ではなく、その人の精神的な血となり肉となっていなければならない。
さきほど、ヘブライ語の教授がデービスの講演の中のヘブライ語やキリスト教関係の知識に驚いた話を紹介したが、単なる知識の披露だけで感心するのは禁物である。
その程度のことは低級霊でも出来る。むしろそれが、低級霊が歴史上の人物の名を騙って出る際に、それらしく見せるために使う手でもあるのである。つまり知識をひけらかすことによって感心させ信用させるのである。
が、それが高級霊による崇高な内容の通信となると、たとえてみれば名演奏家と楽器との関係と同じで、楽器が名器であるほど魂をゆさぶる名演奏ができるし、普段の手入れと調律が必要だし、演奏会場の雰囲気も大切になってくる。高等な霊界通信を受ける霊媒は、教養と同時に人格も問われることになるゆえんである。
こうしてスウェーデンボルグとデービスを比較対照した時、潜在意識というものがプラス方向にもマイナス方向にも大きく作用するものであることを改めて思い知らされる。
スウェーデンボルグの場合は、幼児期のキリスト教信仰と長じてからの聖書研究が霊的啓示を色濃く着色しているところが窺われるし、一方デービスの方は、あまりに無教養であったことが崇高な内容の通信の伝達に際して障害となり、その不足を補おうとする潜在意識の働きが気取った文章となって表れた、と私は見ている。
高等なことを言っているようで、どこか気負いのようなものがあって、ことばが空回りしている感じがするのである。
しかし、そうした点を割り引いても、全体としてみて二人とも稀にみる天才的霊能者であったことは間違いない事実で、本格的なスピリチュアリズムの活動が開始される直前の予兆だったとみるのが妥当であろう。
第二章 スピリチュアリズムの勃興
(一) ついに〝電話のベル〟は鳴った
その二人を敢えて紹介したのは、確かにその後のスピリチュアリズムの産物に比べて大したことはないとはいうものの、それまでの暗黒時代の硬直した神学的教説に比べるとき、そこに時代的背景の大きな変化を読み取ることができることを指摘したかったからである。
もっとも、それに加えてもう一つ、二人は天才であっただけに、凡人が努力してもかなえられないものを、いとも簡単にやってのけた。が、天才であるがゆえの欠陥もさらけ出していることを、日本における二人のファンへの警告も込めて指摘しておきたかったからでもある。
・エプワース事件とハイズビル事件
それからほどなくしてハイズビル事件が話題を呼び、欧米の第一級の学者や文化人が霊媒現象の真理解明に乗り出し、ついにその原因を死者の霊とする〝霊魂説〟が打ち出されるに至った。そのいきさつは 『コナン・ドイルの心霊学』 (新潮社)でセンセーショナルな写真とともに紹介した。
が、実は、それ以前にも、現象そのものはハイズビル現象よりも激しく、かつ長期間にわたったものがいくつかあった。たとえば〝エプワース事件〟というのがその一つである。これはメソジスト教会の創始者ジョン・ウェスレーの父親で同じく牧師だったサミュエル・ウェスレ―の家族が住んでいたエプワースの牧師館で起きた怪奇現象で、一七一六年十二月に始まって翌年の夏ごろまで断続的に発生している。
主として叩音現象だったが、子供がベッドもろとも浮揚したことも何度かあった。ウェスレー氏が話しかけても、小鳥のさえずりかネズミの鳴き声のようなものが返ってくるだけだったという。当時としては大変な話題をさらいながら、科学者の関心を呼ぶこともなく、ただの怪奇現象として記録にとどめられているだけである。
ということは、それが偶発的なものにすぎなかった───目的も計画性もなかったということを意味している。その点、ハイズビル事件はその後の経過を見て明らかなように、さきに紹介したデービスの予言と、もう一つ、現象が発生したのと同じ日のデービスのメモにも、それが計画的だったことを物語るものが見られる。一八四八年三月三十一日付けのメモに次のように記されている。
《けさ日の出ごろ、寝ている私の顔の上を暖かい息が吹き抜けた。そして優しく、しかし力強い声で 「友よ、いよいよ仕事が開始された。見よ、生きた証拠が生まれようとしている」 と言った。いったい何のことだろうと、一人考えていた。》
この〝声〟は多分スウェーデンボルグであろう。この簡単な文章を読んだだけで、霊界において用意万端が整い、ちょうど宇宙ロケットの発射の点火のように、最前線の指導者のゴーサインが出された様子がほうふつとしてくる。
私はあっさりと〝仕事〟という訳語にとどめたが、原文では the good work となっている。good はここでは〝意義ぶかい〟といった意味で用いてあると思われるが、それよりも、定冠詞の the が用いられていることの方が重要であろう。すでに定まっていることを意味するもので、霊界ではいつそれが開始されるのか、大変な話題になっていた筈である。
といって、現象そのものは他愛もないものだった。すでに何度か紹介したが、改めて簡略に説明しておくと、現象の主なものはエプワース事件と同じく〝叩音〟でそれも幾種類かあり、稀には家中に響きわたるほどの轟音もあったらしい。それが妙なことに、二人の娘(当時十四才と十一才)のいるところにかぎって発生した。
怖がった二人が両親の寝室に逃げ込むと、その部屋で轟音がして、その響きでベッドが揺れるほどだったという。
そんな現象が前年の暮れから発生し始めたのであるが、明くる年の一八四八年三月三十一日が記念すべき日とされているのは、その日に妹のケートが勇気を出してその音のする方向へ向かって 「私のする通りにしてごらん」 と言って指先を鳴らしたところ、それに呼応して、鳴らした回数だけ音がした。
自分の年齢を尋ねると、きちんと十一回音がした。それがきっかけで霊との〝交信〟が始まったからである。
これをコナン・ドイルは、大西洋の海底ケーブルが敷設されて最初に交信したテストエンジニアどうしの対話にたとえて、そのとき交わされた言葉は月並みなものだったが、その後、同じケーブルを使って本格的に重大な対話がなされるようになったと言い、ハイズビルの名もない一軒家で起きた一人の少女と目に見えない一人の死者の霊との交信が、その後、数多くの高級霊が崇高なメッセージを送ってくる端緒を開いたのだと結んでいる。 (『スピリチュアリズムの歴史』)
もっとも、この霊界からの計画的な働きかけの最初の舞台となったフォックス家にとって、それは大変迷惑な話だったことであろう。〝証人〟として近所の人々を呼び交信の様子をいっしょに確認してもらい、それがさらに話題を呼んで、翌日には二百名を超す野次馬が押しかけ、その中には心ない人も大勢いて、好き勝手な憶測をし合った。
当然のことながら〝悪魔〟の仕わざだと息まく暴徒まで現れる始末で、フォックス夫人はその心労で、わずか一週間で髪が真っ白になったという。
・フォックス夫妻の証言
しかし一方では、その現象を本格的に調査しようという動きも出てきて、二人の姉妹を使って実験が行われるようになった。これが心霊実験会の始まりである。調査委員会が結成されてフォックス夫妻への聴聞会まで開かれている。夫人の証言は長文のもので、事件当日の様子を克明に述べているが、その最初の一節に夫人の正直な戸惑いの心境が窺われるので訳出しておく。
《・・・・・・私は幽霊屋敷とか超自然現象とかを信じているわけでありません。この度のことで大騒ぎを起こしてしまったことを申しわけなく思っております。それは私たち一家にとっても大変迷惑なことでございます。この家に移り住んだことが私どもの不運だったのでございます。
しかし、真実は知っていただかねばなりません。そのための証言はよろこんでいたしますし、ぜひさせていただきたいのです。ラップの原因は私には説明できません。が、私が確信して言えることは、そのラップが今申し上げた通りに、繰り返し聞こえたということです。今朝(四月四日)もまた聞いております。子供たちも聞いております。
私は以上の陳述が改めて朗読されるのを聞いて、その内容に間違いないことを保証し、必要とあらば、喜んで宣誓することを確約します。》
当日はフォックス氏も主席していて、夫人の証言が読み上げられるのを聞いたあと、次のような声明文を書いている。
《私は妻マーガレット・フォックスによる右の証言を聞き、さらに目を通してみて、その内容の詳細な点に至るまで真実であることを証言します。妻が語ったラップは私も聞いております。われわれからの質問に対して、妻が述べている通りの返事が返ってまいりました。
妻が述べた質問以外にも実にさまざまな質問をしておりますが、やはり的確な返事がラップで返ってきました。同じ質問を繰り返してみたこともありますが、同じ返事が返って参りました。そこには何一つ矛盾は見出させませんでした。
そのラップの原因については、少なくとも自然な手段は思い当たりません。何かが、あるいは何者かがどこかに潜んでいて出しているのではないかと思い、家中のあらゆる場所を何度も捜査してみました。が、そのナゾの解明につながるものは、何ひとつ発見できませんでした。
それがどれほど混乱と不安を生み出したか知れません。これまでに何百人という方が私の家を訪れています。そのために日常の仕事が手につきません。一日も早く、自然現象であれ超自然現象であれ、とにかくその原因が解明されることを期待しております。
地下室の発掘も、水が引き次第、再開されることでしょう。それによって、そこに埋められたとされる人体の痕跡があるかどうかの確認が得られることでしょう。もし発見されれば、その原因は超自然的なもの以外には有り得ないとの確信が得られるものと信じます。》
・五十年後の立証
右の声明文の中の〝地下室の発掘〟というのは、その家の地下室に通信霊の死体が埋められているという事実の証拠固めのために行われたものであるが、発掘を開始して間もなく大量の水が出て、一時中断されていた。
それが再会されたのは夏のことで、深さ五フィートのところで厚板が出てきた。さらに掘り進むと、今度は木炭と石炭が出土し、その下から人間の髪と骨の一部が出てきた。そして医学の専門家による検査でもそれが人間のものであることが確かめられた。が、それ以上のものが発見されず、ついに作業は打ち切られた。
問題の骸骨がそっくり発見されたのは、実にそれから五十年後の一九〇四年のことで、心霊とは何の関係もない Boston Journal という新聞にそのニュースが掲載された。
《ロチェスター発、一九〇四年十一月二十二日。一八四八年にフォックス姉妹が聞いたというラップの発信者とされる人物の骸骨が同家の地下室の壁と壁の間から発見された。これで、二人の少女は霊との交信に関する誠実さにつきまとっていた疑惑を完全に打ち消すことができた。
フォックス姉妹はある男性の死者の霊と交信したと言い、その男性は殺害されて地下に埋められたと主張したことになっていた。そこでその地下室が何度か掘り返されたのであるが、その遺体が見つからず、二人の話の裏づけ証拠が得られずにいた。
その遺体を発見したのは、今では〝お化け屋敷〟と呼ばれている、その二人の少女が住んでいたハイズビルの家の地下室で遊んでいた小学生たちだった。その家の現在の所有者でハイズビルの名士でもあるウィリアム・クライド氏は、子供たちの通報で調査したところ、地下室の崩れた壁の下からほぼ完全な白骨死体が発見された。
(中略) これによって一八四八年の四月十一日に署名された母親マーガレット・フォックス夫人の宣誓書が、事実上、裏づけられたわけである。》
それが問題の行商人のものであることを証明するものとして、遺体のそばから、当時の行商人が金銭を入れて持ち歩いていたというブリキ缶が発見されている。その現物は今も、米国のスピリチュアリズムの本拠地となっているリリー・デール(ニューヨーク) に、フォックス家の屋敷とともに保存されているという。
では、最初に出土していた頭髪と骨の一部との関連はどうなるのか───こうした問題になるとシャーロック・ホームズの親であるコナン・ドイルの独壇場で、最初死体を厚板に乗せて運び、石炭と木炭をかけて埋めたが、不安になってもう一度掘り起こし、人目につかない壁の下に埋め直したのだと推理している。薄暗い中での作業だったために、骨と髪の一部が残ったことに気づかなかったというわけである。
もっとも、私がそこを訪れた最大の目的は、霊的行事に参加することよりも、フォックス家の家族が住んでいた例の家屋がそっくりリリー・デールに運ばれて、他のいくつかの資料とともに展示してあるとの話だったので、それをこの目で確かめることにあったのであるが、その家屋は数年前に火事で焼失したとのことで、その跡地にはご覧の通りの銅板の記念碑が残っているだけだった。それらはこう綴られていた。
フォックス家はマーガレットが十一才、ケートが九才の時にこの家に住んでいて、一八四八年三月三十一日、人類史上はじめて人間個性の死後存続の証拠を霊界から受け取った。そしてそれがスピリチュアリズムの発端となった。
この家屋は一九一六年五月にベンジャミン・F・バートレットによって買い取られ、ハイズビルからここに運ばれてきたものである。》
なお〝ハイズビル〟という地名であるが、これを最初に日本語に置き換えた人がそう呼び、いつしかその呼び方が定着しているので私もそれに倣ってきたのであるが、今回の旅行で近隣の人々や図書館の人に尋ねても一様に〝ハイデスビル〟と呼び、ウィン・カウンティという小さな〝郡〟の中のごく一部の地域をさす〝字〟(アザ)のようなものだとの話で、確かにどの地図にも載っていなかった。
そこから西へ二十五キロのところにロチェスター市がある。私が印象深く思ったのはそのロチェスターが想像以上にあか抜けのした英国風の落ち着いた中都市だったことで、フォックス家事件が世界の話題をさらった時、そこを訪れた学者や知識人たちは多分このロチェスターに宿をとったであろうと、一軒のコーヒーショップで一服しながら想像したことだった。
・〝電話のベルが鳴る仕掛けは他愛もないが・・・・・・〟
以上、私はフォックス家に起きた心霊現象、俗にいうハイズビル事件について、これまでに公表されていなかった資料を紹介した。事件が〝一件落着〟するまでに半世紀もかかっているわけであるが、実はスピリチュアリズムの観点から見るかぎり、ハイズビル事件の目的はとっくに果たされていた。
というのは、すでの嫁いでいた長女も含めたフォックス三姉妹のような霊媒的素質を持った人材がその後ぞくぞくと輩出して、学者や文人、法曹界などの第一線の人々によって真剣に調査されるようになり、〝霊魂説〟がほぼ固まりつつあったのである。
やがてその潮流は英国へ移り、ウィリアム・クルックスやオリバー・ロッジなど世界的にも著名な学者による調査の洗礼を受け、ここでも〝霊魂説〟は動かし難いものとなった。
しかし同時に、心ある人々には、心霊現象が死者の霊によって起こされているのはよいとして、ではその死者たちの霊はその後どういう生活を営んでいるのか、その世界と地上世界とはどういう具合につながっているのか、神は存在するのか、生命は本当に永遠なのか、といった宗教的問題の核心へ関心を向けるようになった。
それに呼応するかのように、十九世紀末にはモーゼスの 『霊訓』 が出版され、二十世紀初頭にはオーエンの 『ベールの彼方の生活』 が出版され、同じ頃からモーリス・バーバネルの口を借りてシルバーバーチが語りはじめている。
三千有余年にわたって受け継がれてきた霊的潮流が、途中いくつかの暗黒の危機を乗り越えて、この世紀末に至ってようやく〝霊的真理〟という、今の人類に最も必要なものを〝事実〟という土台に乗せて、地上へ届けてくれたのである。
これからその〝三大霊訓〟の梗概をまとめてみたいと思うのであるが、その前にコナン・ドイルの 『新しき啓示』 から次の一節を紹介して参考に供したい。
《・・・・・・しかし幸か不幸か、大戦が勃発した。戦争は〝生〟を真剣に見つめさせ、一体何のために生きているのかを改めて考えさせることになった。
苦悩する世界の中にあって、毎日のように夢多き青春が満たされないうちに次々と散っていく若者の戦死の報に接し、またその魂が一体いずこへ赴くかについて明確な概念もないまま嘆き悲しむ妻や母親たちの姿を見て、
突如、私はそれまで自分がだらしなく引きずってきた問題は実は、物質科学が知らずにいるエネルギーが存在するかしないかといった吞ん気なものではなく、
この世とあの世との壁を突き崩し、この未曽有の苦難の時代に人類に用意された霊界からの希望と導きの呼びかけなのだという考えが閃いた。これは大変なことなのだと気づいたのである。
そう思った時、客観的現象そのものへの興味が薄れ、それが事実であることさえ確信すれば、そこで現象の用事は済んだのだと確信した。それよりも、それが示唆している宗教的側面の方がはるかに大切なのだと思うようになった。
電話のベルが鳴る仕掛けは他愛もないが、それが途方もない重大な知らせの到来を告げてくれることがある。
心霊現象は、目を見張るようなものであっても些細なものであっても、電話のベルにすぎなかったのだ。それ自体は他愛もない現象であるが、それが人類にこう呼びかけていたのだ───〝目を覚ましなさい! 出番にそなえなさい! よく見よ。
これが〝しるし〟なのです。それが霊からのメッセージへと導いてくれるのです〟と。
本当に大切なのはその〝しるし〟ではなく、そのあとに来るメッセージだったのである。新しい啓示が人類にもたらされようとしていたのである。それが果たしていつのことか、どの程度のものがどの程度の鮮明度をもってもたらさせるのかは、誰にも分からなかった。
が、大切なのは、現象そのものの真実性はまじめに取り組んだ者には一点の疑念の余地もないまでに証明されているが、実はそれ自体は重要ではなく、その現象が示唆するものがそれまでの人生観を根底から覆し、生命の死後存続という宗教上の課題をもはや〝信仰〟の分野のものではなくて、確固たる〝客観的事実〟としてしまうに違いないということである。》
(二) 現代の啓示──スピリチュアリズムの三大霊訓
①───インペレーター霊団の自動書記と霊言による霊訓
霊媒のウィリアム・ステイントン・モーゼスは、オックスフォード大学でキリスト教神学を学んだあと、牧師としてマン島に赴任した。
若いながらも知性と人間性を兼備した有能な青年牧師として、大変な期待と尊敬を受けていたが、一八六九年、三十才の時に重病を患い、翌年回復して英国本土に赴任してもすぐまた病気が再発したために、牧師職を断念して療養に専念することになった。
その療養のために世話になった医師のスタンホープ・スピーア博士の奥さんがスピリチュアリズムに大変熱心で、交霊会へ連れて行ったり霊媒を読んで自宅で交霊会を催したりした。
モーゼス自身は、牧師はやめても相変わらずキリスト教信者だったために、そのことをあまり快く思わなかったらしい。ところが、間もなくモーゼス自身のまわりにさまざまな物理現象が発生し始める。
テーブルの浮揚、人体(モーゼス自身)の浮揚、物品引寄、香気の発生、楽器を置いていない部屋での楽器演奏、手先などの物質化現象などであるが、やがて自動書記が出はじめる。
最初の頃は取りとめのない内容のものばかりだったが、一八七三年から出はじめたインペレーターと名のる霊からの通信内容が、それまでモーゼスが絶対的に信仰していたキリスト教の教義内容と表面衝突するようになり、戸惑いと不満をぶちまけたモーゼスの質問に対してインペレーターが忍耐強く、克明に、そして丁寧に、しかし時には叱りつけるような語気をもって教えさとすという形での霊信が、一八八〇年までつづいた。
『霊訓』 に収められたのは、そのほぼ十年間に書かれた厖大な量の通信のホンの一部である。それ以外にモーゼスの死後スピーア夫人がまとめた続篇 『インペレーターの霊訓』 があり、これには霊言も収められている。
いずれも主としてインペレーターと名のる最高指導霊が、モーゼスの霊的革新の目的にそって啓示した通信を採録してあるが、通信の本来の目的は言うまでもなくキリスト教神学の間違いを指摘し、それに代わる新しい霊的真理を届けるということにあり、
私の推測では多分、右の二冊の書物となって世界十数か国で読まれることになることまで計算に入れていたのではないかと思われるフシがある。
続篇の中でインペレーターが次のようなことを言っている。 「イエスが神であるとの概念が生まれたのは死後かなりたってからのことでした。そしてそのことはイエスご自身にとって大変迷惑なことでした」
これはニケア会議でのキリスト教のでっち上げを示唆しているのであるが、私は、他のいくつかの霊界通信を参考にしたうえでの結論として、どうやら地球圏の上層界においては、ニケア会議後ほどなく到来する〝暗黒時代〟を予測し、その反動として生じるかずかずの不幸な出来事に対処する手段を講じた。
それが近代スピリチュアリズムであるとみている。そのスピリチュアリズムの数ある部門の一つである〝新しい啓示〟の一つがこのモーゼスの自動書記と霊言による通信だったのである。
その〝不幸な出来事〟は第二部の第三章で紹介した。まさに血も凍るような時代だった。インペレーター霊も、このあと➂で紹介するシルバーバーチ霊も、キリスト教を〝呪うべき宗教〟とか 〝人類の呪い〟とまで表現してその悪業を厳しく批判しているが、それは、そうした悪行が因果律によって生み出す必然の結果としての悪影響が由々しきものだったからでもある。
歴史では暗黒時代は西暦一〇〇〇年ころまでとされているが、実質的には十六世紀のルネサンス末期まで続き、その余波は更に現代にまで及んでいると私は見ている。〝序論〟でそれを端的に紹介した。
霊性を何よりも重んずべき宗教が、その霊性を封殺することによって権力組織を構築し維持せんとしたことは狂気の沙汰としか言いようがないが、インペレーターが繰り返し警告している邪霊集団の存在を考慮すれば、それも納得がいく。
彼らの暗躍を許すスキを与えてしまったということであるが、その要因の最大のものは、霊性が封殺されて、知性とのバランスが崩れたことにある。
・モーゼスは人類の代弁者
さきに私は、地球圏の上層部においてこうした事態に対処するための方策が検討されたと述べたのは、そうした知性と霊性のアンバランスを是正するための方策が検討されたと言い変えてもよいもので、まず幽界の上層部から浄化活動が開始された。
というのは、人間の発する悪想念は、ちょうど排気ガスが大気を汚染しフロンガスがオゾン層を破壊するように、地球の霊的大気圏を汚染しているのである。
それを浄化することから始めて、一八四八年に至ってようやく地上界に直接働きかけるところまで来た。それがハイズビル事件だったのである。
このように、スピリチュアリズムという名称での地球浄化活動は、イエスの死後まもなくして開始され、それが物質界に及んだのが十九世紀半ばだった。その頃はすでに〝科学時代〟に入っており、欧米の第一級の科学者が心霊現象の研究に熱中した。
これを英国の博物学者アルフレッド・ウォーレスが〝近代スピリチュアリズム〟と呼んだ。言うなれば科学的基盤をもったスピリチュアリズムということである。
インペレーター霊団はそうした時期に出現した。私の推察では、霊媒とされたモーゼスは、地上へ降誕する前の〝先在〟の時期にインペレーターを始めその配下の主なメンバーと打ち合わせが出来ていたはずである。しかし、いよいよ肉体に宿ってしまうと、少なくとも脳を中枢とする意識にはそのことが蘇ってこない。
それが結果的にはモーゼスを徹頭徹尾キリスト教の擁護者としての立場を固持させることになった。が、そこにこそ大きな意義があったと私は見るのである。
つまりモーゼスをキリスト教の代弁者としての立場に立たせ、呪うべき暗黒時代の産物であるキリスト教神学の誤りと過ちを説き聞かせた。それに対してモーゼスは、当然のことながら激しく抗弁し、スピリチュアリズムを批判し、かつ嫌悪感をあらわにした。それを受けて立ったインペレーターが懇切丁寧に真実の霊的教義を説いて聞かせた。
その内容は理路整然として知性と良識にあふれており、霊界側で用意周到な準備がなされていたことを窺わせる。が、それでもなおモーゼスは、それをあくまでもキリスト教的観点からしか見ようとしなかった。
あまりのしつこさに一時はそう引き上げの警告まで出すにいたるが、折よく(?)そのさなかに他界した友人のとりなしによって事無きを得る、といったドラマチックな展開を見せる。
・危険をはらんだギリギリの選択
そうした魂と魂の真剣勝負───霊界通信によく有りがちな、唯々諾々(イイダクダク)として霊の言うことなら何でも聞きいれてしまう態度とは違う熾烈なぶつかり合いが、モーゼスの霊界通信の最大の特徴であり、読む者をして、ひとりキリスト教にかぎらず、宗教的教義の功罪についての認識を改めさせずにはおかない。
しかしそれは、一つ間違えば取り返しのつかない悲劇に終わる危険と背中合わせの、ギリギリの選択だったのである。その大冒険の地上の主役として選ばれたモーゼスは、よほど霊格の高い霊の降誕だったはずである。
現今の既成宗教の堕落と逸脱ぶりは、常識をモノサシとして見ても度が過ぎていることは、誰の目にも明らかである。宗教は組織化するときまって堕落する。
組織化がすなわち堕落というわけではない。宗教の本来の使命は霊的真理の普及にあるのに、肝心のその霊的真理をおろそかにして、営利追求と権力の座の奪い合いに明け暮れているところに堕落の要因があると私は見ている。
人類は、この地上に誕生してからまだ日が浅い。青二歳といってもよい程度の成長度であろう。UFOでやってくる宇宙人とは数千年の差があるといわれている。その若さゆえに犯してきた数々の過ちや愚行のツケが、今、地球環境の破壊という形で回ってきている。
メルキセデクに始まった高級神霊の降誕という形での霊力の流入はイエスをもって終了し、今、スピリチュアリズムという名のもとに、霊界からの働きかけとなって展開している。
そうした中にあって、皮肉にもイエス・キリストの名のもとにこの地上に呪うべき害毒を残したキリスト教を俎上にのせて、地上という物質界に身を置く人間としての正しい生き方を説いたインペレーター霊団による啓示は、キリスト教関係者にとどまらず、広く宗教界ならびに一般庶民にとって、計り知れない意義を持つものと信じる。
②──ザブディエル霊団の霊感書記による霊訓
オーエンの 『ベールの彼方の生活』 は一九一三年から始まった本格的な霊界通信を、四つの時期に分けてまとめたものである。 「推薦の言葉」 を寄せたノースクリッフ卿が社主をつとめる 〈ウィークリー・ディスパッチ〉 紙上に連載され、終了と同時に四冊の単行本となって発行されたのであるが、これとは別に、オーエンの死後残された霊界通信の中から断片的に編集されたものが二編あり、それが一冊にまとめられて第五巻として発行されている。
誰が編纂したのか、その氏名は記されていない。それはよいとしても、内容的に前四冊のような一貫した流れがなく、ただの寄せ集めにすぎないので、私はこの一冊だけは訳していない。
通信全体の内容をたどってみると、第一巻は、オーエンの実の母親からの通信が大半を占め、その母親らしさと女性らしさとが内容と文体によく表れていて、言ってみれば情緒的な感じが強い。が、その合間をぬってアストリエルと名のる男性の霊からの通信が綴られ、それが一つの章にまとめられている。
地上で学校長をしていたというだけあって、内容がきわめて学問的で高度なものとなっている。が、それも第二巻以後の深遠な内容の通信を送るための肩ならし程度のものであったらしい。
第二巻を担当したザブディエルと名乗る霊は、オーエンの守護霊であると同時に、その通信のために結成された霊団の最高指導者でもある。しかし、地上時代の身元については何の手掛かりもない。
高級霊になると滅多に身元を明かさないものであるが、それは一つには、こうした地上人類の啓発のための霊団の最高指導者の任を命ぜられるほどの霊になると、歴史的にも古代に属する場合が多く、たとえ歴史にその名をとどめていても、伝説や神話がまとわりついて信頼できない、ということが考えられる。
さらには、これほどの霊にとっては、地上の人間による〝評判〟など、どうでもよいことであろう。このザブディエル霊の通信の内容はいかにも高級霊らしい厳粛な教訓となっている。
第三巻と第四巻では、アーネルと名のる、ザブディエルと同じ霊格をそなえた霊が深遠な霊界の秘密を披露する。とくにイエス・キリストの神性に関する教説は他のいかなる霊界通信にも見られなかった深遠なもので、キリストを説いてしかもキリストを超越した、人類にとって普遍的な意義をもつ内容となっている。まさに本通信の圧巻である。
・スピリチュアリズムのアニメーション
スピリチュアリズムとの出会いによってキリスト教の牧師職を潔く辞した山本貞彰氏は、第三巻の書評 (〈心霊研究〉 九月号、一九八六年) で、〝モーゼスの 『霊訓』 がスピリチュアリズムのバイブルとするなら、オーエンの 『ベールの彼方の生活』 はスピリチュアリズムのアニメーションである〟と、実にうまい表現をしておられる。
そして第四巻の書評 (同一九八七年五月号) でこう述べておられる。
《一九〇九年、六十三才で帰幽した母親が、愛情から、英国国教会の牧師をしていた大事な息子を正しい心霊の道に導こうとして熱心に語りかけたことが契機となって、多くの高級霊が惜しみない協力の手をさしのべ、ついに第十界の高みにまで揚げられたアーネル霊から霊的宇宙に関する壮大なパノラマが送られてきた。古今稀なる重厚な霊界通信である。
アーネル霊は、ルネッサンス期に、イタリヤのフローレンスで音楽と絵画を教えていた人で、かなり迫害されていたようである。霊自身の自己紹介を引用してみよう。
「しかし正直なところ、私は神の愛について当時の人たちには許しがたい広い視野から説いていました。それが私に災いをもたらすということになりました。殺されこそしませんでしたが、悪しざまに言われ、大いに孤独を味わわされました。当時はまさに冬の時代でした」
詩聖ダンテが有名な 『神曲』 を、まさに冬の時代を救おうとして、一三〇〇年ごろから地獄篇の 「ひとの世の旅路の半ば、ふと気がつくと、私はまっすぐな道を見失い、暗い森に迷い込んでいた」 という冒頭の句を書き始めたという古事を思わせる時代である。
ローマ法王と国王が権力の座を掌中に握ろうとして醜い争いに明け暮れていた時代である。アーネル霊が 「冬の時代」 と表現したのは、まことに適切な言葉であると感心している。
さて、この第四巻の柱は、なんといっても、「地球浄化」 という神の大事業の企画、立案、実施という壮大な通信内容であろう。
尊い大神の大事業は、当初神界において審議会が開かれる。それは何億年も前にさかのぼり、創造界の神格の高い天使たちによって行動計画がたてられる。その主宰霊がキリストであるという。キリストは無数の廷臣を引き連れて遥か高い天界から下がってこられ、再び地上へ向かわれる。
このときこの大事業に勇躍志願したアーネル霊が最初に手がけた仕事は、下層界の浄化作業であった。何しろ地球全域はスピリットにびっしり取り囲まれ、さらに彼らの背後には天界の上層界にまで幾重にも大軍がおびただしく控えているという。
その数は無数であり、その一人一人が地上のいかなる威力ある者よりもはるかに強い力を持っているというから、なんとすさまじい光景ではないか。
キリストの軍勢が勢揃いし、地球浄化のために最高位にあられるキリスト自らが大軍の中を切り込んでいかれる。汚れなき至純のキリストにとって地上の悪は見下ろすだに戦りつを覚えずにはおれないものであったが、自ら担われた使命に尻込みされることはなかった。その姿はまさにリーダーであったという。(中略)
この書評を書いている私も、かつて住みなれた家を放棄した。さまよえる子羊の一頭であった。英国国教会という小さくない家の中に安住している方がはるかに楽である筈なのに、決して心に平安と霊的慰めは与えられなかった。
今にして思えばアーネル霊が示してくれた、ごく当たり前の指針こそが、私にとってどんなに大きな救いとなったか測り知れないものがあった。すべてを捨てて家なき子になってみて、初めて心にしみいる喜びの福音とは、自然の法則に即した単純な指針に徹することにあったのだ。
この辺の消息を、ぜひまじめなクリスチャンに知らせたいと念願している。この部分は、キリスト教だけに止まらず、世界に存在するすべての既成宗教に対する霊界からの警鐘であり、浄化の大事業が、強く激しくおし進められていることを実感するものである。》
・二大特質
そして本通信全体の特質として、山本氏は次の二つを指摘しておられる。
《その第一は、「キリスト論」 Christology に大修正が加えられる拠点になることである。神学上のすべての組み立ては、その者がどんなキリスト論を持っているかにかかっている。つまりキリストをどう観ているかである。
既成宗教の枠内で組み立てられたキリスト論は、アーネル霊もふれているように、一冊のバイブルにのみ縛られているので、非常に陳腐なものになっている。少なくとも、真面目に求道する者の心には訴えるものを持っていない。むしろ素朴な信仰すら奪ってしまうことが少なくない。
聖書では真意をつかむことが出来ない多くの部分を本通信が補い、明確な肉付けをしてくれているだけでも、実に革命的な信仰上の転換、言い換えれば生き生きとした信仰へと導かれるであろう。
第二には、我が国におけるスピリチュアリズムの進むべき道について、本書は良き羅針盤のひとつとなることは必定である。キリストという文字がやたらに多く使われていても、その通信内容は結局、自然法則に適った生き方、およびその宇宙観を与えてくれる、いわば 「虎の巻」 のようなものであると思う。
しかも、あちこちに豊富な例え話や寓話が挿入されていて楽しく読める。我が国固有の文化的環境や伝統も、つきつめれば自然の法則によって培われてきたものであるから、ことさら超常現象に大騒ぎをしなくても、日常性の中にスピリットの働きを感じとれるものである。楽しい胸騒ぎや、小さく呼吸が合った時の幸福感などを・・・・・・。
その時に本通信は個々の日常性に深い意味を与え、励みを添えてくれるのである。ささたる日常の出来事について本通信の 「虎の巻」 から意味を探り、喜びと希望を見いだし、力強い一日が送れれば、それこそ本来のスピリチュアリズムの正道に沿った人生となることであろう。》
③──シルバーバーチ霊団の霊言による霊訓
シルバーバーチというのは、今からほぼ三千年前、イエス・キリストよりも一千年も前にこの地球上で生活したことのある霊、ということ以外は、地上時代の姓名も地位も民族も国家もわかっていない。本人が最後まで明かさなかったのである。せめて姓名だけでもとお願いしても、
「それを知ってどうしようというのです? もしも歴史上の有名人だったら有り難がり、どこの馬の骨だかわからない人物だったらサヨナラをなさるおつもりですか?」
といった皮肉っぽい返事が返ってくるだけだった。毎週一回の割で五十年余りも続いた交霊会で同じ質問が何度出されたか知れないが、
「いずれ明かす日も来るでしょうが、わたし個人のことよりも、わたしが語る内容の方が大切です」
というのがせめてものまともな返事で、人間が地上時代の名声や地位や階級などにこだわるのを〝悪趣味〟として、警告をこめた返事をするのが常だった。
そのシルバーバーチが初めてバーバネルの口を借りてしゃべったのは一九二〇年、バーバネルが十八歳の時だった。当時バーバネルは、文人や芸術家による社交クラブの幹事をしていた。ある日そのクラブの例会で講演をした人の口からスピリチュアリズムという言葉を聞いて関心をもった。
すると間もなくその人がブロースタインという霊媒によるホームサークルに招待してくれた。
行ってみると、その霊媒の口をついて、いろいろな国籍の言葉が出た。それが死者の霊だと聞かされた時、バーバネルはバカバカしくなり失笑した。何の証拠もないし、言っていることも下らないことばかりだったからである。
ところが、二度目に出席したとき、会の途中でうっかりうたた寝をしてしまった。目が覚めて、あわてて失礼を詫びたところ、実は寝ていたのではなく、自分の口を使ってあるインディアンがしゃべったと聞かされた。それがシルバーバーチだった。
いきなり入神現象を体験させられたバーバネルは、しかし、霊媒になる考えは毛頭なく、実業家として身をたてようとしていた。交霊会も不定期に催され、聞く人も二、三の友人や知人に限られ、しかもシルバーバーチはバーバネルの支配の仕方が思うようにいかず、英語も、その後のあの流暢なものに比べると、同じ霊とは信じられないくらいひどいものだったという。
・大きかったハンネン・スワッファーの存在
しかし、それも回を追って急速に改善され、どうにかシルバーバーチという一個の霊の個性が明確になった頃に、演劇評論家で〝フリート街の法王〟(フリート街は英国の新聞界の代名詞)の異名をもつハンネン・スワッファ―がその会に出席した。
スワッファーはバーバネルの親友だったが二十歳も年上で、英国ジャーナリズム界きっての大物の地位を築いていた。
その彼もバーバネルに劣らず頑固でヘソ曲がりの毒舌家だったが、一九二四年、四十五才の時に出席したデニス・ブラッドレーが司会役をする交霊会で、英国新聞界の大物で大先輩のノースクリッフ卿が出現して語りかけ、その内容が自分と卿の二人しか知らないことだったのでいっぺんに参ってしまい、スピリチュアリズムへの関心を深めていった。
そうした体験をへてバーバネルの交霊会に出席したスワッファーは、シルバーバーチの霊言にただならぬ質の高さを直観し、自宅で毎週金曜の夜に開催することにし、名称も〝ハンネン・スワッファー・ホームサークル〟とした。
そしてそこからさらにスワッファーの存在意義を物語る働きをする。「こんなに素晴らしいものを、こんな一握りの者が聞くだけでは勿体ないではないか」 と言い出し。ぜひとも心霊新聞〈サイキック・ニューズ〉 に連載するようにバーバネルに進言した。
しかし、自分がその心霊紙の主筆であり社長でもあることから、バーバネルは 「そんなことをしたら私の魂胆が疑われる」 といって断った。が、会を重ねるごとにますますシルバーバーチの魅力に取りつかれていくスワッファーは、重ねてバーバネルに公表を迫った。
二人は親友でもあったせいで、それを断るバーバネルとの間で口ゲンカにも似た烈しいやり取りでがあったようであるが、バーバネルもついに折れて、〝自分がシルバーバーチの霊媒であることを内密にするなら〟という条件のもとで、いよいよ連載が始まったのだった。一九二〇年に語りはじめてから実に十数年後のことだった。
正確な日付は分からないが、〝シルバーバーチはほぼ半世紀にわたって語り続けた〟という時、それは、ハンネン・スワッファー・ホームサークルが結成されて、その霊言が 〈サイキック・ニューズ〉 に連載されだしてからのことで、一九二〇年の最初の入神体験から数えれば、実に六十年となる。
その期間の長さからいっても、霊言の質の高さからいっても、まさに〝人類史上空前絶後〟といっても過言ではない。
その霊言をまとめた最初の霊言集が出版されたのは一九三八年であるが、その時もまだ、霊媒がバーバネルであることが内密にされていた。知っていたのはレギラーメンバーと招待客(ゲスト)だけで、そのゲストにも〝箝口令〟(カンコウレイ)が出されるほど厳重に秘されていた。しかし、そんな状態がいつまでも続けられるはずはない。
「シルバーバーチの霊媒はいったい誰なのだ?」 という読者からの問い合わせが日ましに寄せられるようになりバーバーネルも事の重大さを悟って、ついに一九五九年に〝シルバーバーチの霊媒は誰なのか───実はこの私である〟という劇的な一文を掲載したのだった。
・四つの思想上の特徴
こうした二つのいきさつ、つまり〝公表〟に関して二人が口論までしながら十数年も経過したことと、霊媒がバーバネルであることを四十年ちかくも〝内密〟にしたという事実を見て、誰しも疑問に思うのは、なぜシルバーバーチはそうした問題に口を挟まなかったのかということではなかろうか。
実を言うと、そこにこそシルバーバーチの思想上の特徴の一つが如実に出ているのである。すなわちシルバーバーチによると、人間界の問題はあくまでも人間どうしで知恵を出し合って解決すべきであって、そこに霊界からの強制があってはならないというのである。
常識的に考えれば、シルバーバーチが一言〝早く公表しなさい〟といってもよかったはずである。しかしそこには、一人間としてのバーバネルの自由意思があり、本人がこうしたいというのであれば、余ほどの間違ったことでないかぎり、忠告や警告はしないというのが、高級霊に共通した態度なのである。
シルバーバーチはよく 「あなたの理性が承服しないものは、どうぞ遠慮なく拒否なさってください」 と述べている。それも同じ考えからで、それは例えば守護霊と人間との関係についても言える。
守護霊(英語ではガーディアン) という用語には、日本語でも英語でも〝守る〟という意味があるところから、この文字だけを見た人は〝何でもかでも守ってくれる霊〟と受け止めて、その考えで現実を振り返って、〝おかしいではないか、少しも守ってくれないではないか〟という。が、
守るといっても、母親がヨチヨチ歩きの子供を〝ケガをしないように〟と、付いてまわるのとは次元が違う。母子の関係は同じ平面上のことであるが、守護霊と人間とは〝波動の原理〟で結ばれており、波長が合い、守護霊の監視下にある限りは心配ないが、つい邪な考えを抱いたリ、憎しみや自己顕示欲が強くなってくると、それを機に、邪霊・悪霊といった低級霊に操られることになる。
次にあげられるシルバーバーチの教えの特徴は〝苦労に感謝しなさい〟ということである。苦労こそ魂の肥やしであるという考えのもとに、人間生活ならではのさまざまな悩みごとや難問と正面から取り組み、自分の力で解決していきなさい、というのである。そこには〝ご利益〟的な要素はみじんもない。
「わたしの説く真理を信じても、それで人生の苦労が無くなるわけではありません」 とまで言っている。
大ていの宗教が〝ウチの神さまを信じたら病気も悩みも苦労もすべて無くなります〟と宣伝する中で、シルバーバーチはその逆を言うのである。なぜか、それは、地上という世界が魂のトレーニングセンターのようなところだからである。
せっかく鍛えにきたのに、何の苦労もなく、のんびりと過ごしたのでは意味がない。シルバーバーチの霊訓が〝大人の訓え〟と言われるゆえんはそこにある。甘ったれは許されないということである。
次に挙げられるのは、〝サービスこそ宗教〟という教えである。日本語でサービスというと、オマケとか待遇のよさといった安っぽい意味合いが感じられるが、英語の service の本来の意味は〝人のために自分を役立てること〟ということである。
どんなに小さな行為でもよい。人を喜ばせる行為、人のためになる行為こそ、一宗一派の教義を信じて宗教的行事に参加することより、はるかに霊的な宗教的行為であるというのである。
最後に挙げる特徴は〝因果律〟を宇宙・人生の根本原理としていることである。〝自分で蒔いたタネは自分で刈り取る〟というのはずいぶん言い古された諺であるが、〝やはり真実です〟とシルバーバーチは言う。善因善果、悪因悪果、因果応報などとも言うが、これに関して注目すべきことは、シルバーバーチはその因果律をただ歯車のように巡るのではなくて、〝魂の向上進化〟を目的としている点である。
これはスピリチュアリズムの特徴といってよい、きわめて大切な原理である。右に挙げた三つの特徴も実はみな、この〝向上進化〟という目的があればこそ生きてくるのであり、人生問題のすべてがそこに帰着する。
たとえば善悪の問題でも、伝統的宗教の教えや古くからの生活慣習を基準にして判断するのではなく、当人の魂の向上にとってプラスになるかマイナスになるかで判断すべきであるというのである。
われわれ地上の人間は、どう長生きしたところで七、八十年か、せいぜい百年程度であるが、シルバーバーチは死後三千年にわたる生活の末に、今この地球という故郷に戻ってきて、その間に学んだ宇宙の摂理と、地上生活を有意義に送るための英知をわれわれ後輩に語ってくれた。
それが、こうした何でないようで実は深い英知に裏うちされた教えばかりなのである。それを事実上六十年間もくり返し説いてきた。しかもその間に矛盾撞着も見られなかったという事実は、まさに人類史上空前絶後というべきであろう。
第三章 既成宗教界とスピリチュアリズム
(一) キリスト教会がとった態度
さて、前章で紹介したスピリチュアリズムの勃興を宗教界はどう受けとめたであろうか。それを英国国教会を例として見てみたい。
六十年間にわたってシルバーバーチの霊媒をつとめたモーリス・バーバネルは、ふだんは(サイキック・ニューズ) という、欧米で十万の発行部数を誇る心霊新聞 (週間) の主筆だった。私は大学を出て間もない昭和三十五年ころから、翻訳、転載の許可をもらう手紙を出したのをきっかけに、バーバネル氏と、一九八一年七月に氏が他界する直前間まで親しく文通をかわし、その亡くなる年の一月にはロンドンで念願の面会を果たした。
体格的には英国人男性としては小柄な方であるが、怖じけることを知らないその不屈の精神力は、自己顕示を極度に嫌う性格と、不思議なコントラストを見せていた。
そのバーバーネルの代表的著作に This is spiritualism(『これが心霊の世界だ』 潮文社) がある。 その中に「キリスト教会による弾圧」 と題する章があり、スピリチュアリズムをめぐっての国教会内部の意見の衝突と、極秘文書の入手にいきさつ、およびその内容が述べられている。概略を紹介すると───
・英国国教会の 「スピリチュアリズム調査委員会」 による〝多数意見報告書〟
一九三七年のことであるが、みずからも心霊的体験を持つエリオット牧師と神学博士のアンダーヒルが、当時のヨーク大主教のテンプルに会い、これほどまでスピリチュアリズムが話題にのぼるようになった以上、国教会も本格的に調査研究して、態度を明らかにすべきではないかと進言した。
テンプルはカンタベリ大主教のラングと協議し、その進言を聞きいれて、さっそく十名から成る〝スピリチュアリズム調査委員会〟を発足させた。そして二年後にその結果を報告することを約束した。内心では二人とも、どうせ否定的結論が出るとタカをくくっていたかも知れないが、ともかくそこまでは見上げた態度だった。
ところが約束の二年が過ぎてから、調査結果の〝報告書〟(レポート)をめぐって宗教的偏見がむき出しになりはじめる。ラングの命令でそのレポートが発禁処分にされたのである。
この時点からバーバネルを中心とするサイキック・ニューズ社のスタッフが活動を開始する。スタッフはレポートの公開を拒むのは、明らかにその内容が心霊現象の真実を肯定するものになっているからだという推察のもとに、それに参加した委員会のメンバーと接触を求める。そしてついに、全部ではないがレポートの大部分───肯定派七人による〝多数意見報告書〟───を入手し、それをバーバネルの責任のもとにサイキック・ニューズ紙に掲載した。
案の定、それは英国内外に大変な反響を呼んだ。蜂の巣をつついたような騒ぎとなり、堪りかねたラング大主教は、張本人であるバーバネルを激しく非難する一方、国教会とスピリチュアリズムとの同盟を求める会の会長であるストバート女史に、何とか騒ぎを鎮めてほしいと頼むほどだった。
・聖職権主義が〝真実〟をも葬る
が、レポートは絶対公表すべきであるという意見が、足もとの国教会内部からも次々と出はじめ、「この調査委員会による結論の公表を禁止させた〝主教連中〟による心ない非難や禁止令、それに何かというとすぐに〝極秘〟を決めこむ態度こそ、国教会という公的機関の生命をむしばむ害毒の温床となってきた了見の狭い、聖職権主義をよく反映している」 といった厳しいものまであった。
が、国教会首脳は頑として公表を拒否し続けた。バーバネルは右の著書の中でこう述べている。(抄訳)
《宗教についてまったく偏見のない人間はいないし、自分の宗教を弁護しない人間もまずいない。大方の人間にとっての宗教は、成人後、つまり後年になって余ほどの精神的ないし霊的体験でもないかぎり、子供時代植えつけられたものが基盤になっているものである。
そうした固定観念は年をとるほど棄てにくくなるものである。それは、とくに聖職者において著しい。エジンバラの神学者ジョン・ラモンド師は晩年になってようやくスピリチュアリズムの真実性を認めた人であるが、師にとっては内省を迫られる大問題だったようで、突き刺すような厳しい眼差しで私を見つめながら、こう語った。
「スピリチュアリズムに心をゆだねるということは、〝信仰深きお歴々〟から白い目で見られる。本当に辛い思いの中での決断でした」
宗教家がスピリチュアリズムに接した時の態度は、ちょうど医師が心霊治療に接した時の態度によく似ている。大学で学んだことの全てと矛盾するのである。交霊会で起きる現象はどうしても神学とは相容れない。正統派的観点に固執しているので、それ以外のものに接すると、忠誠心を試されているように感じるのかも知れない。
従って実験会で起きることが実は自分が帰依しているバイブルの奇跡と全く同質のものなのに、それを〝新たなる啓示〟として認めることが出来なくても、あながち驚くには当たらない。
その仕事柄、聖職者は当然、霊的なことについて専門家であってしかるべきなのに、死後の生命についての無知は、あきれ返るほどである。彼らは毎日のように死への心構えを信者に説き、愛する者を失った人々に慰めの言葉をかけているはずなのである。
なのに何故この有様なのか。やはり最初に植えつけられた正統派的教義に基づく神学的概念が、死後の生命についての新たな理解を妨げているのである。
実は、英国国教会は二年間にわたって正式にスピリチュアリズムを調査・研究しているのである。が、その報告書が上層部から発表を禁じられたのである。それを私がすっぱ抜き、心霊紙上に公表したのだが、もしそうしなかったら、そのまま永遠に埋もれていたことであろう。
そもそも国教会が〝スピリチュアリズム調査委員会〟を設置したのは一九三七年のことで、それから二年間にわたって霊媒を使った組織的な研究を行ったのちに、その結論を出した。
十名のうち最も影響力もつ七名が〝多数意見報告書〟に署名し、残りの三名───うち一人は主教夫人、もう一人は主教秘書───は〝中立〟の少数意見に署名した。多数意見は全体としてスピリチュアリズムを肯定するものだった。
報告書の内容を新聞に公表したことで私はカンタベリ大司教から非難された。たしかに、その話題を英国の新聞が大々的に取り上げたために、大主教はある有力なスピリチュアリストに騒ぎを鎮めてくれるように協力を求めたほどである。
その後テンプルがカンタベリ大主教に任命されたとき、私は書簡でぜひ委員会報告を公表するように何度もお願いした。そのやり取りは長期間に及んだが、最後まで平行線をたどり続けた。社会正義の改革運動では同じ聖職者の中でも一頭地を抜いている人物が、宗教問題では頑として旧態を守ろうとする。
現実的問題では恐れることを知らない勇気ある意見を出す人物から届けられる書簡が、ことごとく〝極秘〟か〝禁〟の印を押さねばならないとは、一体どういうことだろうか。
私の持論は、宗教問題にかぎらず、人間生活の全てにおいて、伝統的な物の考え方が新しい考え方の妨げになるということである。古い観念が新しい観念の入る余地を与えないのである。いかなる宗派の信者にとっても、スピリチュアリズム思想を受け入れる上で、その宗教そのものが邪魔をするのである。》
(二) 大幅な修正を迫られる仏教の来世観
・天保の霊言実録 『幽顕問答』 が教えるもの
今からほぼ百五十年前の天保十年といえば西暦では一八四〇年にあたり、スウェーデンボルグやデービスなどの天才的霊能者が輩出してスピリチュアリズムの地ならしをしていた頃であるが、日本でも、筑前(福岡県) の酒造家で庄屋の若主人に、
数百年前に割腹自殺した加賀の武士が憑依して石碑の建立を嘆願すると同時に、その数百年間に見聞きした死後の世界の真相を語って仏教の迷妄を諭すという現象が突発している。
第一部の第一章で説いたように、霊が人間界に働きかけるということは、善きにつけ悪しきにつけ、太古からよくあることで、それが学者の手によって科学的に、そして総合的に調査・研究がなされて普遍的な霊的原理・法則が導き出されたのが、十九世紀半ばから始まった。一連のスピリチュアリズムの活動だった。
が、〝記録する〟ということがあまり行われなかった太古はもとよりであるが、日本人は物事を分析的に捉えることを好まない民族的性向からか、文学の発達した中世から近代に至っても、霊的現象に関して今日いうところの報道形式(レポート)の客観的な記録は皆無に近いようである。
それとは対照的に西洋では五〇〇件にものぼる霊的現象の記録があって、いちばん古いものは西暦五三〇年にさかのぼるという。 (Poltergeists, by A.Gauld & A.D.Corne 11, 1979)
その点この憑霊現象は、図らずもさにわの役をするようになった神官の宮崎大門が〝これはただならぬことと〟と直観して、出現した加賀の武士の語ったことを逐一メモし、それを毛筆で清書して残してくれた。 『幽顕問答』 と題し、今でも福岡県立図書館に保管されている。
私は一九八八年にそれをコピーさせていただいたもの(A3版の和紙四十一枚)をもとに現代風にアレンジして、スピリチュアリズムの観点から解説を施し 『古武士霊は語る』 (潮文社) と題して上梓した。
執筆する前に私が調査したところ、その酒造家は、生業(ナリワイ)は変わっても今なお子孫の方が存在することが分かったので、直接お訪ねして事実を公表することについての了解を求めた。
〝序論〟で紹介したキャロル・コンプトンが世間の無知ゆえに冷たい目で見られたのと同じで、始め当家の方たちは 「むかし何やら薄気味わるいことが起きたらしい」 という気持ちから、それを世間に知られたくないという態度だったが、私が霊的な話をして少しも気味の悪いものではないことを証明すると、わりに素直に理解してくれて、性だけは秘すという条件のもとで、公表を許して下さった。
こうした経緯を見ても、正しい霊的知識がいかに大切であるかを痛感せずにはいられない。
さて本題に入るとして、この酒造家は代々不吉な話のつきまとう家で、なぜか七月四日に急死する者や急病にかかる者が多く、また屋敷内で化け物が出没するとのうわさが絶えなかった。そこで主人の伝四郎は、屋敷そのもの(家相・方角・位置など) が凶なのだろうとの考えから、別の土地に家を新築し、元の屋敷を取り壊して、その跡地に観音堂を建立し、それを〝普門庵〟(フモンアン)と名づけて、御魂鎮めの場とした。
今もそのまま残っていて、私も参らせていただいたが、三、四十体はあろうかと思われる大小さまざまな観音像がきれいに祀られていた。
しかし、原因は屋敷ではなく〝霊〟だったことが間もなく判明する。若主人の市次郎 (妻帯していて多分二十代後半と推定される)が七月四日にこの普門庵に参った時に全身に寒気を催し震えが止まらなくなった。
やっとのことで家に帰って床に伏し、いろいろと薬石を試みてもらったが、一向に良くならず、むしろ病勢は強まる一方で、一カ月も経ったころは身体は餓鬼のようにやせ衰え、さらには、うわごとまで言うようになった。八月二十二日には 「三部経をあげてくれ!」 と言うので、ともかくも言う通りにしてやっている。
とろころが二十四日になると、今度は妙な身振りや手まねを始めた。それを見て家族の者は、これはいよいよ発狂したかキツネでも憑いたのではないかと考えて、近郷の神道の修法家で老松(オイマツ)天神の宮司・宮崎大門に払ってもらうことにした。
・〝天保十年丁亥八月廿四日夕陰霊出現発端の事〟
これが 『幽顕問答』 の冒頭の見出しである。依頼を受けて訪れた大門がまず祝詞の奏上から始めると、驚いたことに、奏上が始まるとすぐに、臥していた重病人の市次郎がむっくと起き上り、床の上に正座し、両手を両膝の上に礼儀正しく置いて、いかにも神妙な態度でそれに聞き入っている。
やがて大門が〝十種(トグサ)の神宝(カンダカラ)〟の古語を誦(ショウ)じながら白羽の矢で病人の肉身を刺す修法をしたが、市次郎は身じろぎもしない。
続いて 「八握(ヤッカ)の剣!」 と唱えつつその矢を胸元近くまで刺す仕草をしたときは一瞬のけぞったが、すぐまた姿勢を正して端座しなおした。
大門はこんどは長剣を抜き払って真っ向から切りつける仕草をしたが、これを恐れるどころか、反対にしっかりと座り直して、傍らのキセルと火入れを左右の手で握りしめ、その長剣の切っ先を鋭い眼差しで睨みつけて、大門が右に振れば右へ、左へ振れば左へと顔を振ってその切っ先から目を離さず、瞬き一つしない。その時の様子を大門は
《一騎当千ノ物部(もののふ) 百万の剛敵ヲモ挫ク軍師大将ノ器モ如此(かくのごとく)ハアルマシト思フ斗(ばかり)也
此状(このさま)ヲ見レハ鬼神ヲ欺ク勇士モ争力慟セサラン。》 (ふりがな近藤)と述べ、さらに傍注として、
《此時ノ趣ハ中々短筆ニテハ書取リカタシ 其ノ座に居合セタル三、四十人ノ人々見テ能(よ)ク知ル処ナリ 面色皆青サメ身ノ毛モヨタチシト後二言へリ。》
とある。
しかし、最後に大門が刀を高く振りかざして、声高(コワダカ)に呪文を唱えてから、
「エイヤ、オー!!」
の掛け声とともに振り下ろす仕草をした時は、握っていたキセルと火入れを放りだして飛びじさり、謹んで平伏した。その時、二か月近くも伸び放題だった乱髪がバラバラと垂れ下がって顔を隠したので、その凄さは筆舌に尽くし難いものだったという。
さて、大門はいったん刀をサヤに収めてから、それを市次郎の弟の信太郎に持たせて奥の間に退がり、そこから市次郎の様子を窺っていた。すると平伏していた市次郎がやおら頭を上げると、なぜか信太郎が持っている刀の方へ目をやり、何やら意味ありげな目付きで見上げ、そして見下してから、〝それをおぬしの膝の上に置け〟と言わんばかりの目くばせをした。
先ほどから兄のものすごい形相に恐れおののいていた信太郎は、その目くばせをくらって縮み上がってしまい。席を立って逃げようとする。すると側にいた父親の伝四郎が大声でこう一喝した。(漢字・仮名づかいなどは修正。以下同じ)。
「そこを動くな! 恐れるでない! ワシをはじめ大勢の者が控えおるぞ!」
さらにその余勢を駆って伝四郎は、こんどは市次郎の方を向き、鋭い目つきでこう言い放った。
「お前なんかは怖くもなんともないぞ! この上は有難き神法〝蟇目(ひきめ)の矢〟にかけて打ち払ってもらう故に、そう覚悟いたせ!」
そう言い放ってから大門のところへ行き、こうまで加持をしていただいてもなお正体を現さぬ以上は、ぜひとも蟇目の矢、鳴弦の御法にて打ち払っていただきたいとお願いする。
それを受けて大門は、同席していた吉富養貞という漢方医のところへ行って蟇目・鳴弦の法の威力を説いて聞かせてやってほしいと頼んで、自分はまた奥に引っ込んだ。なぜ大門が自分から伝えずに吉富氏に言わせたかについては、傍注で大門自身こう釈明している。
《このあとの数か条はみな医師吉富氏を間において言い継がせたものである。先方が述べているのを聞きながら次の問うべき内容を考えるためである。この種の問題では直接談判ではとかく誤ることがあることは、こうした場面に何度も出合って心得たことである。ただし、記録そのものは、煩わしさを省くために直談のように書いておく。》
・「無念のことありて割腹せし者の霊なり」
大門の作戦は的中した。吉富氏の説明が終わるや否や、市次郎は被っていた布団を押しのけて正座し、両手を膝に置いて一礼し、ついに口を開いてこう述べた。
「これほどまでに懇(ネンゴ)ろに正しき筋道をたてて申される上は、もはや何をか包み隠さん。そこもとのご疑念はもっともなれど、余は怪物でも野狐の類でもござらぬ。元は加賀の国の武士にて、故あって父とともにこの地に至り、無念のことありて割腹せし者の霊なり。これまで当家に祟りしが、今だ時を得ずにまいった次第。一筋の願望あってのことでござる」
大門 「何の目的あってこの地に来り、いかなる無念のことありしか。また、いずこへ行くために来るか。この家にはいかなる縁ありしか。父も同じくこの地にて死にたるや」
「余は父を慕いてはるばるこの地に来りし者なるが、父はこの地にて船を雇い、単身、肥前国(佐賀県) 唐津へ赴きたり、別れに際し父は余に向かい〝汝は是非ともこのまま本国(加賀)へ帰れ。一歩たりとも余についてくることはならぬ〟と言い放てり。この事には深き分けありて今あからさまには告げ難し。
さらに余が乗船を乞うても、父はさらに許さず、〝どうしても帰国せぬとならば、もはや吾が子にあらず〟と申せり。かくまで厳しく言われては子たる身の腸(ハラワタ)に徹して、
その言に従うことなれり、さりとて本国へは帰り難き仔細あり、父が出船せしのち、取り残されたるわが身は一人思い巡らせど、義に詰まりて理に逼(セマ)りて、ついに切腹して相果て、以来数百年の間ただ無念の月日を送りたり、吾が死骸は切腹したるまま土中に埋められ、人知れず朽ち果てたり・・・・・・」
そう述べた時には目に涙を浮かべ、世にも悲しげな表情だったという。〝国元へ帰り難き仔細〟については後で改めて詳しく物語る場面が出るが、ここでかいつまんで説明しておくと、この武士の家は加賀でも相当な誉れ高い家柄だったらしく、殿から三振りの刀を下賜されたほどだった。
ところがお家騒動があって父親が濡れ衣を着せられ、殿からお咎めを受けて国外追放処分となった。
その出国に際して当時十七歳だったその武士もぜひお伴をさせてほしいと願ったが、おまえはたった一人の男児なのだから居残って家を再興してくれと頼み、母親にもその旨をしっかりと言い含めて、一人出立した。が、武士はその後も父を慕う思いを抑え切れず、母親の再三にわたる制止を振り切って、伝家の宝刀を携えて出国し、諸国を訪ね歩いて、実に六年ぶりに父と再会したのだった。
大門 「その無念はさることながら、何故にまた、かくもながいあいだ当家にのみ祟りをなすや。他家に祟られしことおありか」
「当家には故あって祟るなり、他家にも祟りしことはあるものの、ただ病気に罹らせるまでのことにて、かくのごとく言語を発したることは一度もござらぬ。これまで当家に尋常ならざることの頻発したるは、余が遺骸の埋もれたる場所より通い来て為せる業にして、同じ災厄が代々起こりしものも、みな余の所為でござった。
早くそれと気づいて祀ってくれなば有難かりしものを、気づいてくれる者のなかりしが無念でなりませぬ。
四年前に当家の祖父も余の遺骸の上にて大病に罹り、 この度この市次郎も余の遺骸の上を踏みし故に、余は瘧(ギャク)(熱病) となりてその身に憑けり、二十三日の早朝に余の鎮まる場所に気づいて砂を掘り、浜に棄てしはもってのほかなり。ために余は行き場所を失いたり」
大門 「何の為にそれほどまで人を悩ましむるや」
「一つの願望あり。その事を果たさんとてなり」
大門 「一つの願望とは何のことぞや。切腹したる時は何歳なりしや。姓名は何と名のられしぞ」
「余の願望は一基の石碑を建てていただく事それのみにして、その一事さえ叶えてくださらば今夕にも当家を立ち退く所存なり。その一念を抱きつつ時と人とを得ぬまま、ついに数百年の歳月を経て、今ようやくその機に臨むことを得たり。割腹したるは二十二歳の七月四日。次の姓名の一儀に至りては、何分にも今さらあからさまに明かし難し」
大門 「姓名を名のらずして石碑の一儀をたやすく受け合うわけには参らぬ。性も名もなしに敢えてそのことをなすは道にあらず。よってそこもとの望みは承諾できぬ」
吉富 「宮崎氏の申せしごとく、その方の姓名を名のらずば人の疑いは晴れまい。しからばその願いも成り難し」
「武士たる者、故ありて密かに国を退きては、姓名を明かさぬが道なり、さりながら、名のらずしてはその一儀受け合い難しとの御意、一応もっともなり、受け合わずばこれまで悩ませし事、みなその甲斐なし。されど、石碑建立の一儀を叶えてくださらば、さきに申せしごとく即刻引き上げ、市次郎も平癒に及び、以後は人を悩まさず。
また当家への祟りも止むべし。祟りを止め人平癒さえすれば、明かし難き姓名を明かさでもよろしきにあらずや。かくまでも懇ろに取り計らっていただくからには、申してよき事ならば何故に包み隠しましょうぞ。武士道に外ればこそ包むなり」
大門 「そこもとの申す筋合いは一応もっともなれど、姓名を刻まぬ石碑を建立するは神道の方式に適わず。よってそれに背きてまで石碑を建つわけには参らぬ」
「是非にも姓名を明かさざれば受け合えぬとのことか・・・・・・ 今となりては如何にせん。姓名を偽るはいと易けれど、わが本意にあらず。実名を明かさではまた道にあらず。君に仕えし姓名を私事の願いのために明さではならざる身となり果てたるは、さても吾が身ながらも口惜しき次第なり。
打ち明けざれば願望ならず。願望ならざれば、ここまで人を悩ましたることみな徒労となるなり・・・・・・」
そう言って大きく嘆息する。ここで吉富氏が畳み掛けるように是非とも名のってほしいと述べると、武士はいかにも大名が平民に向かって述べる風情(フゼイ)でこう述べた。
「その方に一つ頼みがある。先刻の長剣、身にしみじみ忘れ難し。今一度あれなる人(大門)のご加持にあずかりたし。その方、ご苦労であるが、頼んでみてはくれぬか」
吉富 「いかなる剣なればこそそれほどまで慕われるや」
「別段のわけありて申すにはあらず。ただただ尊く思うままにお頼み申すなり ・・・・・・」
と言ったあと、一人ごとのように
「さてさて、あの三振りの中の一振りが廻りめぐりて、いかにして・・・・・・」
となにやら感動を禁じ得ない態度を示しながら俯いた。
大門 「今一度かの長剣にてご加持にあずかりたいとの件、かつまた、石塔を建立して祀りくれよとの件、さきにも申せし如く、その方の姓名を明らかに名のることなくしては軽々しく受け合うわけには参らぬ。包みなく明かされよ。右の二件の頼みと姓名の惜しさとは、替え難しの心底か」
吉富 「これほど懇ろに申してもなお隠されるとは、いかなる理由ありてのことぞ。かくまで包むとあらば、もはやそこもとの願望は叶えられぬものと心得られよ。姓名無き者の願望は受け合い難しとの大門君の言葉は、もっともの義にあらずや」
「さきにも言を尽くせしごとく、故ありて国を逃れし武士は国内のことは深く包むが法なりと言えるはご承知のはず。姓名・氏(ウジ)素性もまた同じことなり。
吾れ割腹を遂げ、無念に果てしのみか、その遺骸は砂をかぶりたるまま数百年間そのままにして人並みならざれば、その間一日として苦痛を忘るる間なし。幾度かこの家の者ならびに他家のものに知らしめんとしたれど、誰一人として悟る者なし。されば、身体頑健と思いて憑けば、弱体にして死せし者もあり。己の苦悩を逃れんとして人を悩ますとは、さてさて拙き定めの身の上なり・・・」
そう述べて目に涙を浮かべ、しばし俯いていたが、内心ついに観念したとみえ、やがて、
「紙と硯とを貸せよ」
と言い、それを受け取ると静かに墨をすり、紙面に 〈泉 熊太郎〉 と書いた。それを手に持って、
「石碑は高さ、一尺二寸にして、表面には〝七月四日〟と書けばよろし。この姓名は決して世に漏らすまじきぞ」
と言い、改めて筆を執って石碑の形まで記し、さらに 〈七月四日〉 と書き添えた。
〈泉 熊太郎〉 の書は本人の意向を組んで大門は公開していない。どこかへ仕舞い込んだか、いっそ破棄してしまったか、その辺は定かでないが、〝七月四日〟と、最初に所望されて書き残した〝楽〟の字などは大門が透写して残してくれていた。ここに紹介したのはそれを再生したもので、実物は郷土史家に貸し出しているうちに行方不明になったと、生松天神の現宮司の母堂から聞いている。
・「死後の世界は生前に考えおるものとはいたく異なるものぞ」
大門は熊太郎の達筆の書を見て、これを身元の割り出しの糸口にしようと考える。
大門 「そこもとはこれほど見事なる書をものする武士ならば、定めし文字を多く知りおることであろう。この用紙に貴家が仕えていた当時の国主の禄高、家老、中老の姓名、および領内の郡村名を記されよ」
「前にも申せし如く、密かに国を出でたる武士は国内のことは包むが武士道なりとの意を聞き分けなきや。吾れ、武士道を破りてまで私願を遂げて悦ぶがごとき性質(タチ)にあらず。
姓名を名のるのさえ祖先に対しまた君主に対して申し訳なき次第なれど、さりとて願い叶わざれば再び人を悩まし、余の苦悩の止む時なきが辛かればこそ、まげて姓名のみは記したり、然るに、なお斯くも追求の手をゆるめぬところを見るに、貴殿らは余の申すことに疑念をはさんでおるものと察せられる。
よく聞かれよ。およそ天地の間にはこの種のことは必ずあるものにて、人間のみならず、時として山川に住むもの、また大樹・大石の非情物だに人に影響を及ぼすものなり。されど、人これを疑う。今この疑いを解かざるかぎりは、余の願望を遂げるは困難と見ゆる。さらば、いざ何なりと聞かれよ。国主に関らぬかぎりは何なりとお答えいたすであろう」
大門 「さらば、そこもとの主君に関わりなき、郡があるであろう。一郡でも五郡でもよい、告げられよ」
「我が本国のグンとな? グンとは何ごとにや」
ここで吉富氏が指先で畳の上に 〈郡〉 の字を書きはじめると、未だ書き終わらぬうちに、
「コオリのことか・・・・・・日ごろ聞き慣れませナンダ」
と述べ、さらに言葉を継いで、
「吾が本国には四郡あるのみにて五郡なきことは知りおるはず。たとえ知らぬが故に問わるとて、うかつに明かしてなるものぞ。みな君父(クンプ)の領内なるものを・・・・・・。されど、それほど地名を知りたくば五つ六つ書くべし」
そう言って 〈榎木村〉 〈榎木原〉 〈篠原〉 〈原江〉 などの地名を書いた。
地名を書いたあと熊太郎はさらに言葉を継いで
「かかることども、たとえ百千書いたとて、疑念の解けざる時は吾が願いは成就してもらわざれば、徒事(アダゴト)となるなり。また村名・山名・江名(川の名)など書き並べたりとも、遠国のことなれば吾れ一人知りしのみにて、疑念を晴らす証とはなり難し」
大門 「そこもとの申すこと、もっともなり。さらば別のこと問うことと致す。先に石碑の図を書き、正面には〝七月四日〟とのみ記せよとの望みなれど、同月同日に死したる者はあまたあれば、その年号も書き添えられよ。何と言いしぞ」
「年号を記さば直ちに君父(クンプ)のことは知れるものなり、記してよきことならば何故に包み隠そうぞ。道に違い義を失うことは、いかに問わるるとて告げるわけには参らぬ」
大門 「七月四日とのみ記して建立すれば、もし当家が転居することあらば、粗末にされることは必定。仮にさようなことにはならずとも、何人(なんぴと)の墓であるか不明なれば、おのずから粗略になるのが道理。その折には魂はいずこへ行き、いずこに鎮まるぞ」
「吾れ、天地とともに、記念してもらいし所に鎮まる心底なり」
大門 「単に月日のみ記しておかば、いずれ粗末に扱われるは必定なれど、それが望みとあらば致し方もなし」
そう冷ややかに言い放たれて、武士はしばし俯いて考え込み、やがて、
と独り言のようにつぶやいた。
大門 「国主の名、切腹当時の年号、本国内のことどもを、そこもとが言を左右にあくまでも秘密にせんとすることこそ不審なり。ぜひとも書かれよ。悪しくは計らわぬ」
この言葉に憤まんを抑え切れなくなった武士は、開き直った態度で、いかにも武士らしい啖呵を切った。
「かくまで道理を述べてもなお聞き分けなきや! 義を失い武士道に背きてまで願望を遂げたりとて、何をかせん。武士たる身の、書きまじきことを書きて私願を遂げんよりは、義を完うして弓矢の神法にかかりて煙とならんこそ本望なり。イザ、御弓矢の行事をなされよ!
さてさて無念を抱きて果てし身は、どこまで口惜しきものなるかな。正しき道理を説けども、人の疑いを晴らすよしもなし!」
激しい口調でそう述べてしばし黙然としていたが、今度は語気を転じて、平静にこう述べた。
「およそ幽界より顕界に言語を通ずるは、尋常なる霊の為しうるところにあらず。吾れ、数百年の苦痛に耐え難ければこそ、かくは人に憑(ヨ)りて頼むなり。いよいよ吾が望みの遂げ難しとならば、市次郎の死することは必定なり。もし吾が望み叶いし時は、四、五日のうちに病は平癒せしむべし。
病気の平癒を証拠に石碑の建立を頼むことは叶わぬものか。もしそれをご承諾あらば、吾れは幽界に帰りて石碑の建立される日を待つべし。顕世にて一代を閲(ケミ)する間も幽界にては一瞬の間と思われるものなれど、その苦しみは人に祟りもすべきほどのものなるぞ」
大門 「武士たるものの大義を失いて私願を遂げんよりは弓矢の神法にかかりてんとは、武士たる道を守るの言葉にも思わるる故に、かかる忠言・義心をいたずらに捨てるも、また吾が本意にあらず。全くもって武士の霊たることの証なり、さらば、これより幽界の摂理につきて数か条を聞くべし。吾が問いに一つ一つ答えよ」
「その前に一言申し置くべきことあり。
顕界の事情をみだりに幽界へ漏らすわけには参らぬごとく、幽界にも顕界に漏らすわけには参らぬ秘密があるものなり。死後の世界は生前に考えておるものとはいたく異なるものぞ。そのことは、おのおの方も死すればたちまちのうちに悟るべし。
余は幽界の者なれど、かくの如く人体に憑りおり間は、幽界のこと、いと微(カス)かなり、それと同じく、人体を離れて帰幽せば、人間界のことはすこぶる微(カス)かにして、心を込めしこと以外は明らかには知り難きものなり。人間界に漏らし難き幽界の秘密、及び人間が知りて却って害あることは申すまじきゆえ、そのつもりで問われよ」
そう述べて威儀を正して問いを持っている姿を大門は〝豪傑の武士一人座敷ニ居タル心地セリ 大病人トハ少シモ見ヘス〟と傍注で述べている。当家の者が茶を差し出すときも思わず平伏してしまい、父親の伝四郎も、ふだん息子に使っていたぞんざいな言葉が出なかったという。
・「百里千里も一瞬の間にて行くべし」
大門「切腹してのち、そこもとは常に墓所にのみ鎮まりたるか」
「多くの場合、墓所のみに居たり。切腹のみぎりは一応本国(加賀)へ帰りたれど、頼りとすべき地もなく、ただただ帰りたく思う心切なるが故に、すぐに墓所に帰りたり」
大門 「本国へ帰らるるには如何にして行かれしぞ」
「行く時の形を問わるるならば、そは、いかに説くとて生者には理解し難し、いずれ死せばたちまちその理法を悟るべし。生者に理解せざることは言うも益なし。百里千里も一瞬の間にて行くべし」
大門「しからば、そこもとは数百年の間この地に住めるなり。これより当時のことを詳しく聞かん」
「死して霊となりたる者は顕世のことは知らぬものなり。霊は人間界のことにはかかわらぬが掟なり。ただし、生存中に心を残し思いを込めたる事は、死してのちもよく知ることができ、またよく知れるが故に苦痛が絶えざるなり。およそ霊は人間界の成り行きは知らぬが常なり。されば余も詳しきことは知らず。ただ人体に憑きてその耳目を借りおる間は、すべてを知り得るものぞ。
さて余のごとく人の体を借りるに当たりて、それを病ましむるは何故というに、人の魂は太く盛んなるが故に、これを病ましめざれば余の宿るべき場所のなければなり。気の毒なれど余は、市次郎を苦しめてその魂を脇へ押しやり、その空所に余の魂を満たしぬ」
大門 「さらば人間界において弔祭(供養・祭礼)など催すも、幽界には通ぜぬことにならずや」
「なかなか然らず。考えてもみられよ。神を祀り魂を供養するは、たとえ人間界の催しとは申せ、そはみな幽界に関わることにあらずや。故に、祭祀は神にも通じ霊にも通ずるものなり。金銭のやり取り、婚姻等の俗事は穢わしければ、神霊はこれを見聞きするを避くるなり。霊となりては衣食ともに不要なるが故に欲しきものもなく、ただ苦を厭い楽しみを思うのみなり。
さて祭事を行うに当たり、人々俗事を忘れて親しく楽しむ心は幽界に通じ、祀られし神霊もこれに感応して喜ぶ。喜べは自然に魂も大きくなり、徳も高くなり、祭りを行いたる者も幸福を受くるものにて、人間界より誠を尽くせば、その誠よく神霊に通ずるものなり」
・「儒仏の説くところを信ずるは、みなその道におもねる者のすることにて・・・・・・」
大門 「帰幽せる霊はみな、各自の墓所にのみ居るものか」
「常に墓に鎮まりたるは余の如く無念を抱きて相果てし輩(ヤカラ)か、あるいは最初よりその墓に永く鎮まらんと思いを定めたる類にして、その数、いと少なし。多くの霊の赴く先は、霊の世界のことゆえ言葉にては告げ難し」
大門 「墓所に居らざる霊はいずこにて供養を受くるや。彼らもその供養の場を訪ねるものか」
「地上にて幾百年も引き続きて行い来れる祭りごとは、幽界にても大体そのごとく定まれるものなり。されば勝手に月日を改め、そのことを霊に告げずして執行すれば、それがために却って凶事を招くことあり。なぜと言うに、霊がいつもの期日を思い出し、祭りを受けに来るに、すでに済みたるを知り不快に思うが故なり。
地上にて同時に数カ所にて祭祀を行う時には、霊は数個に別れてそれぞれの祭場に到り、祭りを受くるものなり。たとえ百カ所にて祭るとも、霊は百個に別れて百カ所に到るべし。
もっとも、余の如き者の霊(地縛霊)は一つに凝り固まりて、その自由は得難し」
大門 「墓所に居らざる霊はいずこに居るものか、おおよそにしても承りたし」
「霊の赴く先はそこここに多くあれど、そは現界に生を営む者の知らで済むことなり。ただ、死後、各自の落着くところはあるものと心得おればよし。死したる後は生ける人間の考えおることとは大いに異なるものにて、生ける者の理解の及ぼぬものなり、理解の及ばぬことを言うは徒労なり、死すればたちまちに知れるものぞ」
大門 「その儀。一応もっともなれど、仏教にては死後行くべき場所を人に知らしめて安心せしむるを主眼とし、儒教もまたこれを説く。さらば今この機会にその真実を世に知らしむるの必要、無きにしもあらず。儒仏の唱うるところ、いずれが実説なりや」
「儒仏の説くところを信ずるは、みなその道におもねる者のすることにて、要するにその門に入りたる者を治むるための説にすぎず。死後、人間の赴く先は地上にありて空中にあらず。もっとも空中にもあれど、そこは死後ただちに赴くべきところにあらず。他界直後の霊の赴く場所が大地のいずこならんは、いまあからさまには告げ難し」
大門 「極楽浄土につきて仏説の当否は如何」
「(微笑しつつ頭を左右に振り、しばらくしてから) 極楽説は人の心を安ぜんがための手段方便にすぎず。生前いかなる説を信じて死すとも、死後の実相とは甚だしく違うものにて、死後のことは死後に知らばよし。人の世にあるうちは世の掟を守り、死後のことは世話を焼くには及ばぬことなり」
大門 「貴殿の返答は、極楽は存在せぬとの意と思われる。ならば、何故にそこもとは、去る二十二日に〝三部経を上げてくれ〟と言いしぞ。三部経は極楽を説けるものにあらずや」
「敢えて経が望ましと言うにはあらず。吾が父のために読ましめたるにて、心ばかりの父への供養なり。供養は経にかぎらず、ただ父のためを思いて誠を尽くせば、おのずから通ず理(コトワリ)なり。石を集め火を焚きても、霊はその気を受けて喜ぶものなり。元来、経は空を説けるものにて、毒にも薬にもならず、ただ僧侶に読ましめて誠を尽くすなり。そは誠を尽くすための手段なり」
大門 「およそ墓所に鎮まる霊はいと穢わしきものなり。しかるに、当家の神棚には尊き神々を奉祭してあるものを、そこもとの如き墓所に鎮まる霊が憚ることなくここへ来るとは、如何なる故にぞ」
「新しき墓にて腐肉の臭気ある所に鎮まる霊は穢れあれど、余のごとく数百年を閲する者は、その骨肉すでに大元の気となりて穢れなく、霊も清浄なり。吾が輩はただ人並みならぬ苦痛あるのみにて、清浄なる点は普通の霊と異なるところなし。故に、かくのごとく神棚の下にも居らるるなり。
ただし、悪行のために果てたる無念の霊は神棚の前には到り難し。余も、みだりに他家へ行くことはならねども、当家には因縁ありて、かくは来るなり」
大門 「それがしは知らぬことなれど、今夕当家に来りて聞けば二十二日の夕べにそこもとが、その夕べに限りて墓所に居り難き旨を述べられたとのことであるが、そはいかなる理由(ワケ)ありてのことか」
「二十二日は郷祭なるが故に古き神霊ご来臨遊ばされ、家々にて豊かなる清浄の気を受け入れるなり。されば余の如き無念に凝り固まりたる新しき霊は遠慮するが掟なり。このことには深き理(コトワリ)あれど、人間に聞かせても益なし」
大門 「ゴウサイとは何のことぞ」
「一郷(ヒトサト)の祭りなり」
大門 「霊が幽界の居所より墓地に来ることは易きものか」
「(同じ内容の質問にいささかムッとして声高に) 来(キタ)らんと思えばいつでも来らる!」
大門 「彼岸盆会(ボンエ)には世俗みな霊を祀る慣わしなるが、かかる折には霊は実際に来臨するものか」
「彼岸盆会は世俗おしなべて霊を祭る時と定めてあれば、霊界にても祀りを受くべき時と直感し、また死せる人も盆会には必ず来るものと思い込みて死せるが故に、必ず現れてくるなり。
されど、余の如く無念にして相果て、死して祀られざる者は、盆会などには臨み難し。
ああ、生前武士たる身にてありながら、人体に憑きて怪しまれつつ石碑の建立を相願い、忌日の祭りを頼むとは、さてさて口惜しき限りなり。この胸中、推量し給われよ」
大門 「菅原道実、藤原広嗣、橘逸勢、早良親王等、いずれも高貴な方であるが、現世に祟り給いし故に神を祀られしと史実にあり。儒者はこれを信ぜず、世の禍はみな自然の為すところとす。いずれが真実なりや」
「いかに高貴な人と言えども、無念骨髄に徹して死せむには、世に祟りを為すこと必定なり。世に知らせて無念を晴らさんがためなり。余がかくのごとく市次郎の体を苦しめるのも、その口を借りて積年の願いを漏らさんと思うが故なり。顕界にて受けたる無念は顕界より解きて貰わねば晴るることなし」
右に挙げられた〝高貴な方〟が祟りをなしたというのは、たまたまその死の直後から疫病や天災が相次いだことからそう信じられるようになったまでのことで、個人の霊の怨念がそんな大規模な災厄をもたらすとは信じられないが、その人物との縁の深い人たちには何らかの影響を及ぼすであろうことは十分考えられることである。
私が翻訳してきた西洋の高等な霊界通信が異口同音に戒めているのは死刑制度で、刑死した霊の復讐心が次の犯罪を誘発していると説いている。こうしたところにも正しい霊的知識の普及の必要性がある。地上からは抹殺できても、宇宙からその存在を消してしまうことはできないし、またその権利は人間にも国家にもないのである。
・霊の誓約書
さて以上私は、紙面の都合もあるので、大して意味のない問答、あるいは時代的思想(階級制度・男尊女卑等) に偏った箇所は省きながら紹介してきた。
が、ここまで来れば、読者も、まさかこれが市次郎の潜在意識ではないかといった疑念は差しはさまないであろう。
大門も初めのうちは、もしかしたらキツネか何かの動物霊の仕業かも知れない、用心の上にも用心をしながら返答の様子に注目していた。が、前段のあたりで〝これはまさしく武士の霊なり〟との確信を固めた、と傍注で述べている。
ところが、市次郎の看病をずっと続けてきた長吉という相撲取りだけは、当初から〝四足の類の仕業〟と決めつけて、問答の合間を見ては大門にそう耳打ちしていたらしいのである。そのことをずっと不快に思っていた武士が、前段の問答の切れ目を見て、長吉を睨みつけて、憤まんやる方ない口調でこう言い放った。
「長吉! 汝はよくもこの吾れを〝四足の類と〟と申したな! 今も言う通り、高貴の人の霊とても無念に死しては時には人を悩ますこともあるものぞ。よく覚えておいて以後つつしめ!」
大門「そこもとの腹立ちもさることながら、たとい神にもあれ何にもあれ、目の前で人を苦しめる様を見て悪魔なりキツネなりと言いたりとて、何の無法があるべきぞ。大切な御国人を悩ますとは、吾が見るところも長吉と同じじゃ!」
「今、吾れ、ふと誤れり。何とぞ吾が願いだけは聞き届けてくだされ」
大門「過ちを悔い、善を慕う心はすなわち神なれば、吾れ、そこもとの望みのままに御剣(ギョケン)加持を行いて信ぜよう。これを限りに当家を退散し、以後、人を悩ますこと勿れ。石碑も建てて進ずべく、忌日には祭礼を行い、また諡号(シゴウ)(おくり名)を授くべし」
これを聞いて武士は嬉しさを隠しきれない風情で───
「吾が年来の願望ようやく叶い、諡号(シゴウ)をも授からば、今後人を悩ますことをせぬばかりか、当家を守護し、また諸人をも救うべし」
大門 「かく誓いしのちに、もしそこもとが重ねて人を悩ますことあらば、その時には容赦せぬぞ! 骨を掘り糞壺に入れて恥をかかせん!」
「武士に二言はござらぬ!」
大門「しからば念のために右の旨を記せる一通の証文を書かれよ」
「証文とな? それには及ぶまじ」
大門「いや、すでに姓名を書きたる上は、定めし文字を知りおることであろう。ぜひとも書かれよ」
「さほどまで申される上は致し方なし。ともかく案文を示されよ」
大門「案文もそこもと自ら認(シタタ)められよ」
「これに武士はうなずいて無言のまま筆をとり、古風な書体ですらすらと認めた。原文はタテニ十センチ、ヨコ十六センチで、大門が敷き写しにしたものが残されている。
これを平たく現代風に書き直せば
《この度、宮崎大門氏は御剣(ギョケン)をもって私が立ち退くように苦心してくださいました。天保十年八月二十四日の夜に御剣加持をしていただき、幸せこの上なく、同夕にこの家を立ち退き、以後この家に限らず、人を悩ますようなことは、きっと慎みます。》
というところであろう。
書き終ると 「これにてよろしきや」 と言いながら大門に差し出した。読み終えた大門が 「よろしかろう」 と言って返すと、武士はこれを燭台の火で焼き捨て、改めて清書したという。
・いったん霊界へ戻る
さて、これで武士の宿願だった石碑の建立の条件が整い、続いて、ではどこに建立すべきかの問題が持ち上がった。本人は清浄な地であればどこでもよいとはいうものの、いずこにも地主のあることなので、その土地一帯の産土神社の宮司・山本参河(ミカワ)を呼んで相談しようということになった。そう話がまとまったところで、吉富養貞が武士に向かって、
「これほど問答が長引いては退屈でもござろう。 しばし休息されては如何?」
と医者らしい気遣いを述べると、武士も、
「吾が輩は宿願の叶う祈りにて、嬉しく、憩うには及ばねど、市次郎の体は長らく苦しめたれば長座はよろしからず。神職の来るまでしばらく同人に一睡させたし。神職の来る時、もし引き合わせあらば起こさるべし、又、御剣加持の時は必ず起こさるべし。これを限りに立ち退くべし。さらば、ご免!」
そう述べて、一礼して夜具の中に入った。入ると同時に市次郎の体から離れたのであろう。夜具の中の市次郎はまさに大病人で、武士の面影はどこにもなく、ただただ眠り込むのだった。
依頼を受けて来着した山本氏は白衣に縞の袴を着用し、病人の上座に席をとった。むろん、これまでの経緯については何一つ知らない。そこで大門と伝四郎の二人でそれまでの経緯を話して聞かせ、その石碑をどこに設置すべきかでご意見を賜りたいのだといわれて山本氏は、すぐには合点がいかず茫然として無言だった。そこで大門が
「貴殿のご不審はもっともなれど、拙者の調べによれば、これがまさしく一人の武士の霊なることはもはや一点の疑いもござらぬ。それゆえ石碑建立の議も承諾いたしたり。ただし、貴殿を始め一座の方にいささかなりとも疑いあれば、腑に落ちるまで直接その霊に問われて結構でござる」
と言うと、三、四十人の一座の者たちも口々に、
「誠に恐れ入った霊魂にござる。一点の疑念もなし」
と言うのだった。
ところが、さきの長吉だけは相変わらず不審の念が消えない。そこで三点ばかり不審な点を並べると、大門も言われてみればもっともな話だということで、いっときして再び市次郎に憑ってきた武士にその点を質すと、
「察するところ余の一睡の間に傍(カタワ)らより入れ知恵せし者あるべし。さらば今そこもとに答うるの要はあるまじ。入れ知恵したる当人を出されよ。直接語り聞かすべし」
と図星をさされて大門も二言なく、長吉を差し招いて、ここに来て委細を承れ、とすすめた。
傍注によると、そう述べた時の態度は威ありて猛(タケ)からず、まことに敬意を払うべき人物に見えたということである。長吉もその堂々たる雰囲気に押されて、しばらくモジモジしていたが、早くせんかと促させて、ようやく市次郎の枕元までにじり寄り、神妙に 「ここにてお話を承ります」 と言った。すると武士がこう諭した。
「されば長吉、汝の疑いは一応もっともなれど、ちと肚(ハラ)を大きく、耳を澄ましてよく聞けよ。前にも言えるごとく、およそ山川に年ふりたる禽獣虫魚、また大樹巨石の霊など、みな人を悩ます力あり。また生霊と言う生者の一念、恨みのある者の体に憑き、その者を悩ますこともあり。また死せし時の一念、現世に残りて人を悩ますこともあり。
余は死ぬる時の無念やる方なく、その上死骸を打ち棄てられ、標(シルシ)の石さえ建てられざる事の悔しさに、かくして市次郎の体を病ましめるなり。体を病ましめざればこの身体を借り難く、市次郎のあるべきところに吾が魂を宿し、その耳、その目、その口など借りるがゆえに、かくのごとく吾が思いを人にも告げ得るなり。
されど、余が邪気と疑われ、野ギツネと思われるも無理なき次第にて、さきの大門君の詰問の間に汝に怒りしは余の誤りなりと認めたるは、汝も知りおるであろう。
汝は人を悩ますは野ギツネばかりと思いおるがゆえに疑念が解けざるぞ。考えてもみよ。野ギツネが石碑の建立を望むものか。また野ギツネならば、神法をもて加持を受けて退かずということがあるべきか。
今もし汝の疑いにて余が野ギツネなりと断定されるに及べば、数百年の願望成就せざるのみか、これ以降も当家をはじめ諸人を悩まし、今のごとく悪鬼となりて取り憑くであろう。世の為、人の為、当家の為、そして余の為と思い、これまでの経緯をよくよく慮(オモンバカ)りで、余の正体を見届けてくれよ」
山本宮司は事の経緯を知らなかったにもかかわらず、この武士の話だけですっかり感動してしまい、上座に居づらかったと、後で述べたそうである。
このあと武士と長吉との間で珍問答が交わされ、長吉の他愛ない質問に武士は思わずプッと吹き出したりする場面もあるが、内容的には大した意味もないので省く。
それよりも一座の者にとって気掛かりなのは市次郎の身体の方で、「長吉が余計なことを聞くからこんなことになるのだ」 と口々に罵るので、長吉も恐縮して畳に頭を擦りつけて詫びた。すると武士がいかにも下々(しもじも)の者に向かって述べる風情で
「この男、愚痴(愚か者)にてあれど、長々と市次郎を親切に看病せしは奇特なれば、病気平癒の後は、この度のこと、とくと市次郎に聞かせられたい。当人も定めし歓ぶでござろう」
などと述べている。
そのあと山本氏が上座から下がり、武士の方へ向きを変えて、一礼して質問した。
「拙者は当地の産土神社の神職、山本参河(ミカワ)と申す者でござるが、承れば貴下は、加賀の住人、泉氏の御霊とのことにて、ゆくゆくは社地に鎮まりたきご希望の由、いかにも理あるお頼みでござる。市次郎の体よりお離れなさるのでれば、及ばずながらも拙者、ともかくも計らい申すでござろう」
「ご来駕の段、ご苦労にござる。拙者の身の上をお耳に達し、まことに面目次第もござらぬ。市次郎の身体より立ち退くことは今さら申すまでもござらねど、ただ社地に鎮まる事はひとえに頼み奉る。もっとも公に持ち出すことは憚りあれば、人知れず内密にして計られたし」
このあと山本氏と大門との間でいろいろと案が出され、それについて一つ一つ武士に 「いかがであろうか」 と訊ねるといった調子で話が進められた。が、結局は、事を急いでお上からお咎められては元も子もないので、あとは二人に任せてほしいということになった。すると武士は、
「三年にても四年にても待つべし、かくて吾を神と斎(イツ)き、七月四日を祭日と定めくださらば、以後は当家を守護すべし。その儀重ねがさねお頼み申す。それはさておき、先刻お頼みした御剣加持をしてくだされよ」
大門 「折角のお頼み、承知いたした。さきほどは怪しき物と思いしゆえ切りつけたれど、もはやその儀は無用なり。さらばご免」
と述べて支度に取り掛かると、武士も、
「辱(カタジケノ)うござる」
と述べて両手を膝の上に置き、鎮(シズ)んで待っていた。そして御剣加持が終わると一礼してこう述べた。
「さてさて、おのおの方にはいたくご苦労を掛けたり。先刻約せし通り、七月四日を祭りくださらば、余いかでか悪しう酬(ムク)いましょうぞ。市次郎も今日限りに日を追って平癒し、かくて七年の後には当家には吉事あるべし。それを見て余が霊界より悦びて守護しおる証とし、また神となりし徴(シルシ)なりと知られよ。
イザ出立せむ。おのおの方、門口までお送りくだされよ」
そう述べて席を立ち、ヌサヌサと歩いていく様子は血気さかりの若侍が颯爽と出で立つようで、とても大病人の市次郎には見えなかったという。居合わせた者たちもゾロゾロと門まで付いて出た。武士は門前で立ち止まり、墓地の方を向いてこう述べた。
「余この身体を離るる時、市次郎が倒れるやも知れぬゆえ、おのおの方にて彼を助けてもらいたし」
そこで何人かの者が側に寄り添い、山本、大門の両神職が神送りの秘文を唱え、祓いの言葉を奏上しているうちに、果たして市次郎は左へ倒れかかった。それを抱きかかえて家へ運び入れて寝かせると、こんどは打って変わって重病人で、吉富氏が羽毛で唇に薬を塗ってやるとスヤスヤと寝入ったという。
・火事騒ぎ
さて、市次郎の騒ぎはこれでともかくも一段落して、家族の者はもとより関係者一同はほっと胸をなで下した。
あくる日の二十五日は宮崎大門は近くの漁村での大漁祭の施行を頼まれて出張した。それを終えて帰宅したのが二十九日で、さっそく市次郎を見舞ってみると、市次郎は布団の上に起き上がってはいたものの、元気そうになく、大門が
「どうじゃ、七月四日以降のことを憶えておるか」
と尋ねると、市次郎は弱々しい声で
「七月四日、祖父の墓に詣でた時に全身に悪寒を感じ、頭痛がして気分が悪く、甚だ苦しかったことまでは記憶しておりますが、帰宅後のことは一切知りません。ただ夢の中で、大きな楼閣があって、その広い庭の中の美しいところに公卿と覚しき人々があちらこちら逍遥(ショウヨウ)している姿を見ました。その夢が覚めると同時にわれに帰りました」
と答えた。月も変わり、日を追って快方に向かっていたものの、相変わらず節々が痛み手足の自由が利かないのが口惜しくてならず、自分の無意識の間の出来事をつぶさに聞かされて
「かくまでわれを悩ますとは一体如何なる武士の霊か」 とか
「人も多いというに、われに何の過失があるというのか」 とか
「全快の上は墓を掘り返して恥をかかしてくれる!」
と言った憤まんの言葉を漏らしたという。
そんな折、その家に火事が発生した。半鐘が鳴り響き、村中から大勢の人が駆けつけた。その中に燐家の兵吉と言う者がいて、役宅 (庄屋事務所) の方を案じて走ってみると、病床に伏しているはずの市次郎が、神棚の下に正座して物凄い形相で火焔の方を睨みつけている。変だとは思いながらも、火事のまっ最中なので、そのまま戻って火消しを手伝った。
そのうち火事は不思議と大したことにならず鎮火した。が、その頃から市次郎の頭痛が激しく、鎮火後からずっと横になったままなので、またしても大門に加持を頼むことにした。
伝四郎から依頼を受けた大門はさっそく前回と同じ加持を行ったが、市次郎はただこんこんと眠り続けるのみで、その日は別段変わったこともなく終わった。
翌月も大門と山本氏と医者の吉富養貞が来た。吉富氏は診察のあと、
「脈拍は甚だ悪しきが、霊が再び憑くはずもなければ、この度は何が原因かさっぱり分からぬ」
と不審げに言った。ではもう一度祈禱してみましょうということで大門と山本氏が市次郎の側に寄り、父親の伝四郎も部屋に入ってきた。その時である。市次郎がまたもや威勢よく起き上ってこう言い放った。
「伝四郎、養貞、杜氏(酒造りの職人)の三人、ここへ来よ!」
これはまた何かあるぞと、家中が色めき立った。すると、見た目には市次郎であるが、いかにも武士らしい口調で次のように諭した。
「この度の当家の火難は七、八日前よりその兆し現われ、幽界の方にはよく知れわたり、故に、たびたびその兆しを示して知らしめんとしたれど、一人としてこれを悟らず。そのうち火焔の兆候ますます盛んになるをもって急ぎ守護せんとすれど、吾が魂を寄する所なきをもって、またまた市次郎の身体に憑き、今日、火災の起こる少し前より念力を凝らして、ようやくにして消し止めたり。
先日、余が市次郎の身体を借りていろいろ幽冥の秘事を説き明かしたれば、少しはその道理を悟りたるかと思えるに、毫(ゴウ)もさるところなく、却って幽規を犯して変を招けり。
夏の頃より積み置きし不浄の土も忌まず、これを用いて新竈(カマド)を築き、浄めの式をも行わずして火を焚くとはあまりにも不法なり。世に水火ほど清浄なるものはなし。ことに井水と竈と火とは最も清らかなるものにて甚だ尊く、ことに酒造家は火と水とを用いること、他に数十倍す。何をもってその恩に酬ゆるぞや。
なべて神霊は清きを愛す。これに従うは人たるの務めなり。しかるに不浄の土をもって竈を築くは、これ、人みずから災いを招くものにして、神明それを下すにあらざるなり。知らざることは是非もなけれど、すでに土に不浄の入りたるを知りつつこれを用いたるは不届きなり。
さきの日、余が教えおきしにもかかわらず、今かくの如し。これ下世話にいう〝喉元過ぎて熱さ忘るる〟の類ならずや。
およそ火災・洪水の類は即座に来るものにあらず。幽の方にしかるべき理(コトワリ)ありて顕に起きるなり。このことの原理は余の如き凡霊のよく知りうるかぎりにあらねど、火災起こらんとする兆しある時は、あらかじめこれを知ることを得。いやしくも古法によりて竈を清めおけば、たとえ火難の生ずる時の至るも、時運の荒(スサ)びに誘わるることなし。
この旨よくよく弁(ワキマ)えて、今後を慎み、家運の長久を図るべし」
そう言い終わった時、吉富氏が大門のところへ行って
「先月の霊か、あるいは別の邪気か、そして何故に憑きしかをお見分け下され。先月の霊は立ち退いてのちは二度と悩まさぬとの一通 (誓約書) もあれば、それとも思えませぬが、ともかくお見分けくだされ」
と言うと、山本氏も、
「先月市次郎の身体に宿れる加賀の武士が再び憑いたのでは・・・・・・」
と言った。その時である。霊が
「ご免!」
と大きく言ってから、前に結んでいた帯を後ろへまわし、両人に一礼したので、両人も答礼した。すると霊がこう語り始めた。
「それがしは、いかにも先月二十四日の夜当家の一子の身体を立ち退きたる霊なり」
山本 「何の為に立ち帰られしぞ」
大門 「先月の一通に再び人を悩ますまじきと書きたるに・・・・・・」
山本 「武士に二言なしと承りたる大門氏への一通、いかに申し開かれるや」
「その儀は先刻主人と養貞に申したり、七、八日前より当家に大難の運にさらさるる兆しあるを見るに忍びず、家の東西を徘徊してその徴を示せど、一人としてこれを悟り得るものなし、余、見るに見かねて霊気をよせるところなく、やむを得ず再び病後の市次郎の身体を借り、守護して、かろうじて火難を救えリ。
先夜当家を守り七年の内には吉事を見せんと約せしに、かかる火難ありては却ってこれが為に辛うじて願いおきたる石碑の一事も無にならんこと必定なり。かく思いて万やむを得ず宿りたるにて、以前のごとく身体を悩まさんが為にあらず。二度と宿るまじと約したが虚言と言うのであれば、火難を消したる一事をもって、この過ちをお見逃し願いたし。
それのみにあらず。今まで数百年のあいだ墓所にのみ居りたれど、先夜尊き神法に与り、神号をこうむり、邪を転じて正に帰するを得たれば、墓がいたって穢らわしくて、エイレマセヌ」
山本 「エイレマセヌとは如何なる義か。墓地に何物かがありて入り難しということか」
この時、たまたま居合わせた燐家の兵吉が商用で加賀へ行ったことがあり、
「上方にては〝エイレマセヌ〟とは〝居られぬ〟ということです」
と説明した。すると武士が
「そうさ、むさくて居ることの〝エデキヌさ〟」
と、お国訛りまる出しで言い添えてから、さらにこう述べた。
「今一つ、おのおの方に申し入れたき儀あり。先月当家を立ち退きし時、公の許しあるまで三年にても四年にても待つべしと約せしが、いよいよ幽界へ帰りてみれば、余の霊格いつの間にか向上して、墓はもちろん、その辺りの土地すべてに穢れを感じていたたまれず、やむなく樹上などのあるも、ただただ旅心地にして安ずることなし。願わくば寸尺の浄地を与え給え。その儀、改めて乞うものなり」
大門 「その儀ならば、石碑建立のときまで浄地に鎮めるように取り計らって進ぜむ。上代には櫛ある刀を霊代(ミタマシロ)とせし例などあるが、暫時の宿としていずれがよろしきや」
「ともかくも修法どおりになし給え。その法に従いて遷(ウツリ)申さん」
山本 「白木の箱に霊璽(レイジ)を置きて、それに鎮むる法もあり」
大門 「されど、血気盛んなれば魂も太かるべし。小さき箱にては如何ならむ。八寸の箱にて鎮まる得るや」
「十分でき申すなり。修法に従えば一寸の箱にも鎮まるものなり。かかる事は顕世にあるものの耳には入り難ければ、詳しく述べても益なし。その道の法の通りに従うべし」
・「今は包み難ければ物語らん」
これで、ともかくも霊箱ができ次第それに遷ってもらうことになったわけであるが、そうなると、もう二度とこうして語り合うこともできなくなるであろうから、霊をしばらく引き留めておいて、いろいろ聞き出そうではないかと言うことになった。まず吉富氏が大門に
「貴君の御剣のことを〝三振りのうちの一振りなるが・・・・・・〟と小声で言いし訳を聞き給え」
と言うと、山本氏も
「その〝三振り〟というのは如何なる意味であろうか」
と言う。すると大門が 「良いところに気づいてくれた」 と言って、さっそく新たな問答に入った。
大門 「先月、拙者が振りかざせし剣をそこもとは〝三振りの中の一振り〟と言い、またそれを念入りに拝見されし様子は、いかにも故ありげに思われたるが、何か訳ありのことか」
「ただただ尊きあまりに拝見せしまでにて、別に仔細はござらぬ」
大門 「先夕そこもとは余がもちたる刀に心をとめ、かつ二度も〝三振り〟との言葉を用いて慕わしげに見えたり。さまで一念の残りたる刀を拙者が愛藏するわけには参らぬ。いかなる不吉の三振りなるも知らずに家に永く留め置くこと、潔しとせず。そこもとの石碑の下に埋めて進ぜむ」
山本 「その通りにてはござらぬか。さほどまで念のかかりたる刀は秘蔵するに及ばず。早く塔の下に埋めるべきなり」
そう言われてもなお黙していたが、ややあって
「水を呉れよ」
と言う。作次郎と言う男が水を汲んで差し出すと、武士はそれを飲み干してから、しばしの間、胸をさすったり横腹を押さえたりしたあと、こう言った。
「その刀はその刀と、ご承知あればそれでよし」
大門 「聞かねば聞かぬほど気がかりになるものなり。さまで申しかねるところを見れば、さぞかし不吉なる刀でござろう」
「一をいえば二を言うに至るゆえに包み隠したれど、かく重ねて問われるに及びては如何にせむ。その刀は決して不吉の刀ではござらぬ。余が本国にて上様より賜りたる三振りの中の一振りなり。今その賜りし謂われは軽々しく申すべきことにあらず。口外いたし難きところは何とぞお察しあれ」
大門 「〝廻りめぐりて〟と言われしは、加賀の国に残し置きたる刀が廻りめぐりて余の家にきたとの意味なるか」
「さにあらず。今は包み難ければ物語らむ。余十七歳のとき国内に騒動起こりしが、その折、父は無実の罪に沈み、ついに上様のお咎めを受けて国を逃れたり、出国のみぎり父が母に申し置かれしは、余はただ一人の男児なれば、必ず泉家を再興させよ。上様より下賜(カシ)のこの一振りは家宝として大切に余に伝えさせよとのことであった。
しかるに余は父のお供申したく、その旨を母に願うこと度々に及べども、母はその都度たって引き留め、親一人を思いて代々の祖先の家を滅ぼすことがあってはならぬ。真実われを思う心厚きならば、国にありて家を再興せよ。たとえ後より来るとも言葉は交わさじとの父の遺言なるぞよ。必ず出国無用なりと、それはそれはきつく引き留められましてござる」
そう述べて武士はハラハラと涙を流し、それを見ていた一座の者も思わず貰い泣きして、しばし涙にむせんだという。大門も余ほど感動したとみえて、傍注でこう述べている。
《カカル事アリノママニハ如何ニモ短筆拙文ニテハ書キトリカタシ 書ハ意ヲ尽クサストハ宣(ムベ)ナルカナ。コノ人ノ義心ノ有ヲ以テ又ソノ父ノ義心 思イヤラルル也。》
大門 「して、そこもとは十七歳のみぎりに国元を出て、いずこにて父君に面会なされしぞ」
「されば余は、母が引き止むるを聞き入れず、伝家の一刀を携えて国元を出て、諸国を廻りめぐりて六年ぶりに芸州 (広島県) にて父に行き逢いたり。
そのとき父は余を見て大いに怒り、母に言い置きしことは伝え聞きしはず。汝が母の命に背きて家出せしは、取りも直さず吾が命に背きしなる。汝はただ一人の男児なれば、汝を措いて他に家を継ぐ者なし。一刻も早く帰りて母と共に家を再興せよ。吾は濡れ衣の渇くまでは死すとも帰り難き身なり。よく聞き分けられよ、父として子を思わぬ者があろうや。されど汝が吾の跡を慕うは孝にして真の孝にあらず、と理を立てて責められては、跡については行かれませんナンダ・・・・・・」
と、またもや涙ながらに語った。
吉富 「して、そこもとは強いてお供なされしや」
「イヤ、父はその夜ひそかに船にてその浜を離れ、ついに行方(ユキカタ)知れずになりたり。聞けば九州小倉行きの船に便乗されしとのことなれば、余も船を雇いて小倉まで行き着けり。されど父はまだ小倉には来りまさず、余はそれより九十余日小倉に滞留せり。
その後ようやくにして父が着きたれば言葉を尽くして随行を願えども、父は一言も返事さえ為し給わず。程なく肥後の唐津へ向けて急がるるにより、余も後より追い慕いたり・・・・・・」
大門 「小倉よりこの地まで何というところを通られしぞ」
「小倉よりこの地まで数カ所通行したれど、覚えんと思わざれば一々は覚えず、心に留めぬところは忘れたり。今もなお覚ゆるは小夜(コヤ)という土地の川辺を通行せしことにて、そこは家居も多く、近くの田圃のここかしこに三軒五軒の民家ありたり。また、ひとしお目に止まりしは博多の津(ミナト)なり。旅船多く集まり、軒数も多く、勝れてよき所なりし」
・災厄の原因と厄払い
山本 「お話中なれど、実は先刻当家に火難の気運到れる由を聞きて、当家の主人より吾らにお頼みあれば、吾れらにて家運隆盛の祈祷を修せしが、かかる修法によりて火難の凶運消失するものでござろうか。災難はいかにせば免るべきものか、ご存じあらばお知らせくだされ」
「貴殿方の御祈禱にてその凶運は必ず免るべきにござるべし」
山本 「余などによる祈禱にて災厄を免るるとの証拠やいかに」
「証拠という義にはあらざれど、先月それがしに神法加持など致されしにより、数百年宿りし吾が墓地、にわかに穢わしくなりて甚だ住み難くなりたるを思えば、その神法には邪気を転じて正に帰する威力あるは間違いなかるべし。一家の凶運もこれにて消失すべしと申すなり。その上、今は主人をはじめ家内の者どもみな心を改め、俗事にかまけて大本の道理を忘れぬ心底に帰りおれば、丹精こめし祈祷によりて開運間違いなかるべし」
山本 「この度の火難はつまりは人間の不手際によるものか、それとも天罰か、邪神の所為か、はたまた竈(ソウ)神の怒りか、お教えあれば祈念に際しても心得るべし」
「世の災禍は人間の不手際によるものも多けれど、中にはそれが神明の怒り、邪神の荒びを伴いて起こる場合もあり。また如何なる原因とも知られずして自然に発生するものもなきにしもあらず。あるいは竈神を粗末にして怒りを買うこともあれば、粗末にしたとて何の祟りもなき時もありぬべし」
山本 「さらばこの度の事は竈の神のお怒りでござろうか」
「竈神の荒びと言えば言われざるにもあらず。邪神は好みて人を害し、神明つとめて邪神を除き給う。すなわち竈神の司り給う竈に不浄を集め無法を働くことは、これ邪神の望むところにして神明の嫌うところなれば、凶事はその辺より起こるなり。
ご両所 (宮崎・山本) より当家の者に篤とこの道理を教え給われよ。誰しも家業の忙しき時は天地の道理、大本の摂理に悖(モト)りて物事を粗略にし、穢れを招き易きものなれば、よくよく注意の肝要なること、導きありて然るべきことなり」
このあと地理と所持品についての穿さくがあってから、
「すでに吾れを神霊として祀りくださることになりたる上は、これまで余に対して無法を働きたることども、などて怨みとせむ。今さらあげつらうも甲斐あらず。太刀は貴家にて伝えくださらば幽界にありていかばかりか悦ばむ。また当家の者が余を神として怠りなく祀りくれなば、余もつとめて家運を守護すべし」
吉富 「貴殿すでに神霊となられし上は、祈願すれば何事も成就なさしめ給うこと必定でござろう」
「人民の祈願は余のごとき凡霊の力にて成就するところにあらず。朝廷(オカミ)より春秋恒例の祭祀をなし給う神社の神々の与え給うことなり。余はこれまで当家に障りをなしたる罪深き霊なるに、神と祀られしにより、その報いとして当家を守護するまでにて、広く世の人々の祈願を受くることなど思いも寄らず。
四季の順環、五穀の農穣、万民の安寧などの大事は量り難き道理あるものにて、世に吉事凶事(ヨコトマガゴト)のある摂理は、今御身達に述べたりとて耳に入らざるべし。されば今後もし余に向かいて祈願する者あらば、ご両人より是非ともお止めくだされ」
・「いまだ墨痕の乾かざる四、五百年前の古筆を拝覧するとは・・・・・・」
大門 「そこもとの在世中の年号のことは極秘になされたき意向をくみて尋ねることとを控えるが、当時の都は大和なるや山城なるや、はたまた近江なるや」
「すでに山城に定まりし後なり。延歴 (七八二~八〇六) よりははるかに隔ちたり」
吉富 「ご当代になりて後か」
「ご当代?」
吉富 「家康公ご治世の後か」
「家康公? さようなことはいまだ聞き申さず」
吉富 「頼朝公前後か」
「そのことはこれ以上お尋ねくださるな。年号と父君のことは決して語らずと、先夕申せしにあらずや」
大門 「ときに、先月出現の際の御筆を拝するに、なかなか凡筆にあらず。余が所持する例の書きもの(誓約書)一通と、石碑に刻むべき文字(七月四日)、それに加賀の地名と貴殿の御姓名等であるが、これらは他人には秘すべきものなれば、ここで他人に見せられる文字を数文字お書きくださらぬか」
そう言い終わらぬうちに伝四郎が墨を摺って揮毫の用意をした。大門が筆を取り上げて
「是非とも願いたい、是非とも」
と迫る。その時、霊の鎮まるべき白木の箱ができたので見てほしい、と連絡が届いたので、山本氏が座を立って大工の家へ向かった。
大門のたつての要求に武士は、
「亡霊が何の必要ありて顕界に筆蹟を残すべきぞ。目出たくも面白くもなきことなれば、止めに致さるべし。先月は書かざればご疑念の晴れざれば、止むなく書きたり、かの書きものはこのことを明らかにせんがために書きもしたれ、今さら望まれて書くは実に愚かしきことなり」
吉富 「そこもとの御剣が遠く隔ちたる宮崎家に伝わり、かつその御剣にて加持を受け、さらにその人より神号(高峰大神)を授けらるるとは、よくよく深き縁あることにて、その人に一字なりともお伝えになれば、一層御剣を大切に致されるはず。〝剣を大切にせよ〟とでも書き記し給え」
大門 「〝剣〟の一字なりとも書き給え。そのほか何なりとご髄意に筆を染められよ」
「いやはや、理責めの強(キツ)いことよ。さらば・・・・・・」
と言って筆をとり、その筆先を熟視して、脱け出た一本の毛を引き抜いて脇へ置き、手を拭ってから 〈楽〉 の字を書いた。
折から山本氏が帰ってきて、その書を見て感嘆し
「さても見事な出来でござる。いまだ墨痕の乾かざる四、五百年前の古筆を拝覧」するとは、世にも稀なる事でござる」
と言い、居合わせた人たちも 「まことに珍しきことでござる」 と言い合ったという。
・御霊遷(ミタマウツ)しの神事
ひとしきりして山本氏が言う。
「さて、箱もすでに出来上がり、海水にて洗い清めおきたり。追々遷り給え」
「まことにご苦労に存ずる。用意万端整いなば、即刻遷り申すべし」
吉富 「いよいよ離れられる段になりては、いささか名残惜しき心地せり。今少しお尋ねしたき儀がござるが・・・・・・」
大門 「箱もできたればこれより神事を取り行うことと致すが、その前に先夕聞き落とせることをお尋ねしたい。
帰幽すれば霊は上下ともいっしょに集まりて、そのまま万代までも同じ状態のままなるや、それとも時とともに変化するものなるや。そもそも霊には一人ひとり形体がそなわれるものか」
「先月も申せしごとく、幽界の事はあからさまに顕世に漏らし難き事情あり。聞かせて益なく、語りても耳には入るものにあらず。耳に届かざることは聞きて却って疑心を誘い、害となるべし」
大門 「余は幽冥のことどもを疑う輩のために聞くにはあらず。余自身、実相を聞き天地の真理を知る一助と思えばこそ聞くものなり。たとえ聞きて耳に届かざることありても、それはそれで止むを得ぬこと。右の件につきて一応お聞かせあれよ」
「さらば一言語りおくべし。尋常に帰幽せる霊は同気の者にかぎりて一所に集まりおれど、そはただ居所が同じというまでにて、多くの霊が一つになるにはあらず。志の同じものは幾人にても集合して一つになることあれど、そは一時のことにて、万代までも一つになるにはあらず。
霊の形は顕世と同じく折りにふれて少しは変わることもあり。また中には主宰の神のお計らいにて再び顕世に生まれてくる者もあり。それらのことは長く霊界におれば次第に明らかになるものなれど、奥深きことは拙者がごとき凡霊の遠く及ばざること甚だ多し。
顕世にありし時、忠孝その他善事を務め、誠実に心を尽しながら報われずして帰幽せる者は、霊界にて報われて魂は太くかつ徳高くなり、現世にてその報いを受けたる者は、帰幽後は人並みの扱いを受くるに過ぎず。
さらに又、帰幽後に新たに功を立てて高くなる霊もあれば、現世にては善人なりしが、帰幽後に怒り(憎悪)を抱きて卑しき霊となる者もあり」
ここまで語った時に作次郎が平木の箱を持って入り、一方杜氏頭が注連縄(シメナワ)を海水で清めて持ち帰ったりして周囲が慌ただしくなって、話がいったん途切れる。箱を机上に置き、それに注連縄を張り終わると、武士は訓戒の言葉をこう締めくくった。
「先月も申したるごとく、在世中に見たることは死後もよく覚えおれど、死して後の現世のことは、よくよく意念を集中させざれば明らかには知り難きものなり。
霊の世界も現世と同じごとくに認知せらるるものなり。これを思えば、貴殿のごとく霊のことに心を止められれば、死後の事情も知らるることもあるべし。
死して後は現界のことを知りえても一向に益なし。これを思えば、現世にある者がみだりに死後の事情を知りても為にはならざるべし。されば諸宗が説ける俗説に惑わさるるべからず」
そう言い終わったころには三方(サンポウ)に神酒(ミキ)と肴(サカナ)が供えられて、いよいよ御霊遷(ミタマウツ)しの儀式の用意が整った。山本氏からその旨を告げられると、武士は威儀を正し、三尺ばかり退がって一礼した。左右には宮崎、山本両宮司が祭服を着用して座し、三、四十人にのぼる人たちも四方に席をとった。
数百年の宿願の成就を目前にして武士はさすがに感無量で、霊箱を深々と伏し拝み、涙を流しながらその内部をしげしげと見つめ、やがて袖で涙を拭ってから、こう述べた。
「さてさて時を得て願望成就し、悦ばしきこと、これに過ぐるものはござらぬ」
大門 「心に残すことあらば何なりと申し置かれよ。ともかくも計らい申さむ」
「それがし、心に残ること更になし」
作次郎 「こののち当家に凶事の兆しあらば、申し置きくだされ」
「当家に代々不吉なること生じたれど、そは吾が怒りに触れてのことなり。今はかく悦ばしくだされば、以後さる類のことは無かるべし。もとより少々の不幸災厄を免れざるは世の常なれば、深く思い煩うには及ぶまじ。もし凶事の兆しある時は、それがし守護して鎮めん」
伝四郎 「毎年七月四日には宮崎・山本ご両人のご苦労を願い、一家近縁の者ども集まりて祭りを催すであろう」
「有り難き幸せ、何とぞ御法(みのり)どおりに致して下され。また、申すまでもなけれど、吾が霊の鎮まる場所設定の件は、何とぞ世間に包み、とくに公のご厄介にならぬようお取り計らいくだされ」
そう述べてから手を合わせ、箱に向かって拝伏した時、これが人情というものであろうか。現象が突発した当初は気味悪がっていた一座の者たちも、今やすっかり泉熊太郎なる武士に心情が移っていたのであろう。名残惜しさの余りすすり泣く声が部屋中から聞こえたという。
そこで灯火を消し、御霊遷しの儀式を行い、最後に、宮崎・山本両神職が柏手を打つと、市次郎の身体が左の方へゆっくりと転がる音がした。霊が離れたのである。
そこで点灯し、うずくまっている市次郎を家の者が介抱する一方、大門が箱の鉤を締めてから門外へ運び出し、仮の一所に安置した。」
・「月いっぱいなるぞ」
明くる十三日に大門が見舞いに訪れてみると、市次郎は再び立派な大病人となっていた。気分はどうかとの問いに市次郎は、
「先月末、私の病気は平癒に向かっておりましたのに、家族の者の話によりますと一昨日より例の武士が再び取り憑いたそうで、手も足も痛みが激しくて・・・・・・」
と顔をしかめながら語り、さらに言葉を継いで、
「いったい人も多いのに、何故にこの私を苦しめるのでしょう。聞けばあなたがたは彼を神と祀ると申されたそうですが、私はさような気持には毛頭なれませぬ。むしろ、この病気が治り次第、腹いせにそいつの墓を掘り起こして、うっぷんを晴らしてやりたいくらいです」
と歯がみをしながら悔しがるのだった。
そこで同席していた山本氏が宥(なだ)めるつもりで火難の話を持ち出し、その身代わりとなった思えばよいではないかと言うと
「火難は来る時には来るわい!」
と言って怒りをぶちまけ、ありたけの罵りの言葉を吐くのだった。
宮崎氏は七ツごろ (夕方三~五時) には帰宅し、前日の問答のメモをとり出して、徹夜で草稿を整理している。
明くる十四日になって使者が来て、市次郎の容体が甚だよろしくないので加持をお願いしたいとのことだった、生松神社と市次郎の家とは入り江をはさんで向かい合う位置にあり、さっそく伝馬船で急行して修法を行ってみたが、別に怪しい様子もなく、病勢が募る一方だった。
宮崎氏は翌十五日から十八日にかけて神事で東奔西走し、帰宅したのは夜だった。その翌日の十九日の朝、伝四郎が一巻(ヒトマ)きの書を懐に入れて訪れ、ここ四、五日の間の市次郎の様子が認められていると言って手渡した。見るとそれは吉富養貞からのもので、その最後のところに実にドラマチックな現象が述べられていた。それを大門は
《九月十七日市次郎カ病気ヲ神霊顕シテ平癒ナサシメラル事。》
と題して紹介している。以下がそれである。
《ここ両日は病人の痛み、ことに強し。よりて桜井の医師美和氏をも招きて五、六人の医師と種々心尽せど、その験(シルシ)なし。
十七日の祝には看病人も皆疲れ果て、前後不覚に眠り、病人の市次郎一人つくねんとして心細きこと限りなく、いずれこの度の病はとても治るまじと観念し、腸(ハラワタ)を絞りてありたるに、ふとそのまま眠気づきウトウトなりし時、何処(イズク)よりともなく、いと涼やかなる声にて、
〝市次郎、起きよ、起きよ〟
という声聞こゆ。
誰なるかなと思いて臥したるまま後ろを見れば、年令二十歳あまりにして色白く、髪は総髪にして眼光鋭く、身には黒羽二重(ハブタエ)の袷(アワセ)のようなもの一枚着したる。人品卑しからぬ一人の武士、佇(タタズ)みいたり。
市次郎、別に怪しとも思わず、
「そこもとは何人にや」
と問うに、首を打ち振りて返事はなし。よりて市次郎は床の上に起き上がり、右の武士に向かいて座れば、
「月いっぱいなるぞ」
との言葉なり。
やがて件(くだん)の武士、市次郎の背後にまわり、乱れたる市次郎の髪を掻き上げ、頭から肩先、そして腰まで段々に揉み上げつつ撫でてくれる心地良さ。総身おのずと汗ばみて、ついうつらうつらとする程に、またも
「起きよ」
と言う。目を開きて見れば、その人、行灯(あんどん)の火にて煙草を吸いおりしが、つと立ちて、この度は前の方へ廻りて、胸より腹、そして両腋下まで撫で和らげることやや久しく、市次郎いよいよ心地よきまま、ふとその人の背部を見るに、そこには①形の紋所つきたり。その人
「永らくの間汝を悩ましたるは甚だ気の毒なり。されど、これにて身体は本復すべし」
と述べると同時に、たちまち煙のごとく消え失せたり。
ここに市次郎、今見し姿が人間にてはなかりしことを始めて悟り、余りに恐ろしくありしかば、妻を喚び起こして、薬を暖めさせて飲みたるところ、夜はほのぼのと明け渡りぬ。
翌十八日の夜、市次郎は父伝四郎、医師吉富を呼びて、夜中に起こリしことをつぶさに語る。
その朝より心地甚だ穏やかなり。同人は頭痛が持病にて、八月以来これのみは止まざりしに、今朝は洗い上げたるように気分よろしいという。養貞脈を見るに、病ほとんど平癒しおれり。
吉富養貞
宮崎大門雅君玉机。》
その後市次郎は日を追って元気になり、九月二十九日には完全に平常に復した。そして十月一日には産土神社にお参りし、四日には僕(しもべ)一人を連れて宮崎氏のもとにお礼に参上している。その折、宮崎氏が例の 〈楽〉 の字を見せると
「すっかり元気になりましたゆえ一昨日は父の留守中に私が触れ状を写そうとしたのですが、まだ手が震えて思うように書けませんでした。これは病中の私の手を借りられたとはいえ、さてもさても見事なものでござる」
と言って感心し、しばらく宮崎氏と酒を交わしながら話が弾んだということである。
開けて天保十一年六月に石工に命じて石碑を建立し、表面に宮崎氏の書になる 〈高峰大神〉 を、その上に市次郎が見たという紋所①を、向かって右側には武士直筆の 〈七月四日〉 を、台石には吉富氏の筆になる年号と銘を刻み込み、同年七月四日に落成式をあげたという。
付記(一) ───年号が〝平成〟に変わる前年の五月に私が現地を訪れた時、今は雑貨店を営んでいるという当家への道を尋ねた人から 『この道をまっすぐ行ったところです』 と言われて歩いて行くうちに、突如として左側に写真でご覧の通りの祠(ほこら)が目に入った。
瞬間、私は 「これだ」 と思って石段を上がり、表面の 〈高峰大神〉 と右側の 〈七月四日〉 の文字を確認してから、手を合わせてこの度の奇しきご縁を報告し、この事実を公表することのお許しを請うた。
それから写真に撮らせていただくことの失礼を詫びてから、少し下がって良い位置を探していると、下を通り掛かった中年の婦人が駆け上がってきて 「折角ならきれいにしてあげましょうね」 と言って、垂れ布をきれいに揃えてくれた。その様子がいかにも人間の襟元を整えるのにも似ていて、実にほほえましく感じた。
その方はいつもササキを枯れないように取り替えてあげているとのことで、今でも七月四日には近所の人たちも加わって、ささやかなお祭りをしているとのことだった。百五十年の間欠かすことなく斎(イワ)われて、泉熊太郎の霊もさぞかしお喜びであろうと拝察した次第である。
付記(二) ───平成四年十月に英国のサイキック・ニューズ紙の新編集長ティム・ヘイ氏から、この 『幽顕問答』のあらましを記事にしてくれないかとの依頼を受け、さっそくタイプで打って送ったところ、 「これは面白い。ただの記事では勿体ないから、一冊の本にしてはどうか」 といった主旨の手紙が届いた。
私にとって英文での著書は初めてなので自信はなかったが、ともかく A Samurai Speaks (サムライは語る)のタイトルで書き送ったところ、 「すばらしい出来なので、知人が出版部長をしているリージェンシー・プレスに送った」 との手紙が届いた。その理由としてサイキック・ニューズを出すのが精一杯で、単行本を出す余裕はないから、ということだった。
それが今年(平成五年)の二月のことで、三月にはその部長ジョン・ソープ氏から 「ぜひウチから出させてほしい」と要請があり、四月に出版契約を交わし、この十一月についに出版された。ロンドンとニューヨークで売り出されているとのことである。こうした事実から考えて、このサムライの物語は人種を超えて、何か訴えるものを持っているようである。
(三) 普遍的宗教としての神道に求められているもの
・脚下照顧
本書の中心的テーマとして取り上げた暗黒時代の影響は、ローマが〝すべての道はローマに通じる〟と言われたほど強大な軍事大国だったからこそ、世界史を彩るほどのスケールの大きいものとなったのであるが、第二次大戦のように、こちらから仕掛けないかぎりはストレートに外的影響力を受けることのなかった日本の宗教界の歴史も、単一民族と言われていながらやはり複雑な要素をはらんだ消長の道をたどっている。
古代においては〝かんながら〟と呼ばれる原神道の系譜があった。が、これも所詮は権力者ないしは為政者が引き継いできたものが残ったのであって、各地に点在していた豪族や渡来人の集落には、それ独自の信仰形態があったはずであるから、渡来民族を吸収同化して単一民族になるまでの過程は大変だったはずである。
卑弥呼が女王となったころは、ローマ帝国がキリスト教を国教とした時代にほぼ相当する。 「魏志倭人伝」 によれば、当時の日本も戦乱に次ぐ戦乱の時代で、卑弥呼は中国から援軍を求めたりしながら必死に凌いだが、そのうち肝心の霊能力が衰え、予言の的中率も落ちると、殺されたという。(かつては〝死んだ〟と解読されていたのが、最近では〝殺された〟と言う説が有力になってきたという。)
その後、〝かんながら〟が仏教徒との絡み合いの中でどう受け継がれてきたかについては、戦後の自由化の波に乗って〝タブー〟が取り除かれたことも手伝って、多くの新真実が明らかにされつつあり、誌上討論も活発に行われるようになってきた。どうやらこの小さな島国の宗教界も、キリスト教ほどのスケールではないが、内乱に次ぐ内乱に明け暮れていたようである。
ただの武力衝突もあったし、権力の奪い合いによる陰湿なものもあった。宗閥間の意地の張り合いという、匹夫にも劣る下らぬものに由来するものもあったようである。少なくとも私が日本史を概観したかぎりでは、本書で浮き彫りにしたキリスト教の所業を、神道系・仏教系の別を問わず、どの宗教も嗤(ワラ)って見過ごすわけにはいくまいと思うのである。
・〝いくら自国の遺産を誇ってみても・・・・・・〟
三十年以上も英語の教育と翻訳に携わってきた私が、日本人と英語国民との違いが端的に出ていると思う表現に〝われわれ日本人は・・・・・・〟というのがある。気をつけてみると無意識のうちにそう言っている。英語国民が〝われわれイギリス人は〟とか〝われわれアメリカ人は〟という言い方をすることは、まずない。〝私は・・・・・・〟である。
その〝われわれ日本人〟はわびとさびの文化、やまとことばの神秘性(言霊=コトダマ)、そしてかんながらの思想の単純にして深遠な自然性を誇り、外国人に対して〝あなた方には理解できないでしょう〟といった態度をとるのをよく見かける。が、それらは太古の日本人の誰かを通して霊界から届けられたインスピレーションによる産物であって、それをそのまま今日のわれわれ日本人が自慢すべきものではないと私は考える。
私が高校生に使用している英文教材の中に、ある英国人が
「いくら自国の遺産を誇ってみても、現代の者がそれを引き継ぐための何らかの努力をしなければ、それは何の意味もない」
と述べている文章がある。神道は、その淵源をさかのぼれば素晴らしいものであったかもしれないが、少なくとも今日見られる組織体制の中には本来の霊性が見られず、ほとんど形骸化しているように見受けられるのである。
現代の神職の中に霊の実在を現実性をもって認識し、そして説いている人は、皆無とは言わないまでも、きわめて稀ではなかろうか。私が存じ上げている神職の中にそう言う稀な方が何人かおられるが、その方たちが口を揃えて、同じ神職仲間の堕落ぶりを嘆いておられるのである。
〝葬式仏教〟と並んで〝お祓い神道〟などと陰口をたたかれるゆえんはその辺りにあるのではなかろうか。
・もっとインターナショナルなものに
昭和八年に初版が出た J・W・T・メーソン著 『神ながらの道』 (今岡信一良訳・平成元年復刻・たま出版) は、米国人ジャーナリストで自ら神道家(シントウイスト)をもって任じるメーソン氏の快著である。外国人という第三者の立場から客観的に見られる、メリットもあるであろうが、その観点の特異性と理解の深さは、驚嘆に値するものがある。
その序文の最後でメーソン氏は、日本民族の精神的構造の欠陥を喝破して、こう述べている。
《神道を理解することなくして日本を理解することは不可能だと日本人は言う。西洋人としてはその通りである。しかしそれ以上に、日本人自身にとってもその通りである。日本人は直観的に神道を理解するけれども、さらに自覚的に理解するにいたるまでは、日本人は西洋人から理解されることを期待できない。
まさに発現しようとしている新世界情勢においては、各国民は自己を他国民に理解してもらう方法を知らなければならない。それができない国民は取り残されてしまう。
日本人は遺憾ながら自己を説明する能力が欠けている。東洋における偉大な国家の将来の福祉のために、その国民は自己の文化を〝より〟客観的に理解することを学ばねばならない。神道は日本の世界文化に対する大きな貢献の源泉になり得るかもしれないのに、日本はまだその貢献の方法を知らない。
神道は世界に対してメッセージを持っている。そしてこのメッセージを普及する使命は日本が負うべきものである。そのためには、神道を日本国民自身の間に、もっと現実的なものにしなければならない。
私は日本の人たちがその肩の上にかつがれているこの責任にめざめることを切望する。神道は人民のものである。いかにしてその感化力を増進すべきかは人民の解決すべき問題である。》
メーソン氏の期待を込めた厳しい指摘に対応するには、まず何よりも神職にある人たちが、霊の実在ということについて、もっと現実的な理解───神秘的ものとしてではなく、リアルな事実としての認識を持つことが必要であろう。
それには、コナン・ドイルも述べているように、信頼のおける西洋の霊界通信に親しむ必要があろう。あえて西洋のと断ったのは、日本で入手されている神示、霊示、お告げの類は、霊言としては純正なものかもしれないが、私には余りに神懸り的で、天上的で、現実の世界から懸け離れているきらいがあるように思えるのである。
それが神道の神道たるゆえんであるとおっしゃりたい方もいるであろう。が、これからの時代は、もう、そんな言い訳では済まされなくなって来つつあることは、他の分野の国際化の波を見ても明白である。
メーソン氏も 「もっと現実的なものに」 と述べているが、私が言いたいのは、それとは別に、現実界に直結した霊界の事情を知って、それを具体的に説くという努力も必要だということである。いずれはみんなその世界へ行くである。しかも、すぐに神になるのではないのだ。
ここに紹介したのは死後の世界のイラストレーションである。コナン・ドイルが一九三〇年に他界したあと、地上時代の霊的知識の確認のために調査し、また先輩霊から教わったものを基にしてまとめて、地上の人間に理解しやすい形で送り届けてくれたものである。
この図の通りにバームクーヘンのように層を成しているわけではない。死後、意識の開発と向上とともに、こうした幾つものレベルの意識の世界を旅しながら、地上では想像もつかない千変万化の生活形態を体験しつつ、永遠の時を経て超越界へ突入するということらしい。が、そんな超越界だの神界だののことは、泉熊太郎のせりふを借りれば 「人間が世話を焼くには及ばぬこと」 であろう。
それよりも、ごく平均的な人間が赴くサマーランド、そして少し気の利いた人間が赴くという霊界あたりまでのことは知っておく必要があるであろう。そもそも泉熊太郎が死後数百年もの間、切腹して果てた土地をうろつきまわったのも、日本の武士道という限られた一時代の地上的観念に囚われたからで、マイヤースの言う〝観念の牢獄〟から抜け出せなかったのである。
メーソン氏は第十章 「神道の世界的普遍性」 の中でこう指摘している。
《神道は、現実生活から隔離したものではない。なぜなら、それは創造的活動と自己発展と普遍的神霊観とによって、生存に対する直観的反応力を日本に与えてきたからである。しかし、人生の闘争場面にあって、慰安と助力とを求める人心に、神道が応じなかったのは本当である。
神道はいまだかつて日本人の心の自覚的表面に達せず、また自覚意識の疑問に解決を与えるように解釈されてこなかったから、あたかも森の中に孤立して存在するように見える。》
神社が森の中にあるのはよいが、その神社で手を合わせて拝むだけが神と人間との関係(ツナガリ)であってはならないと私は言いたいのである。
・スピリチュアリズムの原理に照らして総点検を
前節で私はかんながらの思想を誇るのはよいが、自分がそれを立派に理解しているかの錯覚を持つことの間違いを、わび・さび・ことだまを引き合いに出して指摘した。
つまり、家伝の宝物を床の間に飾って客に披露するような調子で外国人に自慢しても、現代の日本人みずからがその真髄を理解する努力を怠っては何の意味もない、ということが言いたかったのであるが、それに関連してもう一つ付け加えたいのは、わび・さび・ことだまといったものが外国人、特に西洋人には理解できないかに思うこと自体が大きな間違いだということを、私自身、三十年以上にわたる英語の仕事と英語国民との接触を通じて直観しているということである。
日本語ではわび・さび・ことだまという言葉で客観的に表現されているだけのことであって、感性の鋭い人なら世界のどの民族の人でも、直観的に理解しているのだということを、何度か痛感させられている。ただ言語で言い表すことができずにいるだけのことなのである。
それと同じで、本書の冒頭から指摘しているように、本質的には霊的存在である人類は、一人の例外もなく霊的感性を秘めているのであるから、森羅万象の背後に控える霊性を直観する可能性を持っているのである。古代のレッド・インディアンの生活には〝宗教〟とか〝信仰〟という用語すら不要なほど自然にそれがにじみ出ていたようである。それをシートンの著書から明確に読み取ることができる。
が、私見を述べさせていただけば、日本のかんながらの伝統は、そうした人類の先天的な宗教性の自然な発露として、地上の他のいかなる宗教にも類を見ない、理想的な形態だと考える。これはもはや形式が必要か否かの問題を超越したものであって、霊性の進化が生み出す自然な産物とみるべきであろう。
しかし、基本的にはそう言えても、現実問題としてかんながらも長い年月のうちに無用の夾雑物がこびりついてしまったように見受けられる。本来は無縁であるはずのものに利用されてきた嫌いもある。そして他方では、さきにも指摘したように、肝心の霊的感性がマヒして、その本質が次第に形骸化する過程をたどってきた。
が、三十年あまりもスピリチュアリズムを研究し、その観点から世界の宗教を客観的に観察してきて、日本のかんながらの思想ほど霊的に自然で、しかも奥深いものを秘めているものは他には見いだせないというのが、私の正直な結論である。
〝客観的に〟と断ったのは、特定の信仰の熱心な信者になってしまえば、それが世界で唯一絶対のものに思えてくるものだからである。それではいけない。昨年(平成三年)十月に放映された NHK の〝プライム10〟の 「引き裂かれる恋人たち」 で、同じキリスト教の中での宗派の違いゆえの悲劇を扱っていたが、客観的に見てこれほど愚かしい悲劇はない。が、そうした愚かしい悲劇を生み出すというところに、もともと霊性をもちあわせないキリスト教の非自然性があると私は見ている。
西欧人には、日本の家庭に神棚と仏壇があることや、正月に、頑ななクリスチャンは別として、仏教のあらゆる宗派の信者も含めた全国民が神社に参拝するのが不思議に思えるらしい。が、そこにこそ神道の自然さと寛容性があるのである。最近ではたぶんクリスチャンであるはずの外国人が神社に詣でている姿がテレビに映っているのを見かけるが、少しも違和感はない。
かんながらが果たして日本民族のオリジナルなものなのか、それとも太古において渡来人によって持ち込まれたものが根づいたものなのか、その辺のことは日本民族の起源と同じく、まだ判然としない要素が多い。が、それはどちらであっても構わない。
現実に日本に太古から存在し、そして見事な形で受け継がれて来ているのだ。その事実そのものは厳然としている。それは一つには、日本が小さな島国であったことが大きく幸いしているのであろう。
しかし、先ほどから繰り返し述べているように、それを床の間に飾って人に自慢している時代ではなくなりつつあるのだ。世界へ向けてその真髄を輸出して、宗教の本質並びに宗教的儀式の正しい有り方の模範として参考に供することが、これからの神道に求められていることの一つであると私は考える。
真髄を理解した上での儀式は、絶対に必要であろう。霊界でも儀式はある。あるどころか、地上の人間には創造の及ばないほど厳粛で大規模な儀式が行われると聞いている。さもありなんと思う。
が、そのためには何よりもまず、日本の神道関係者みずからに、霊的原理と死後の世界の実相について理解が求められるであろう。その霊的知識をもとにして、たとえば 「古事記」 などを読み直せば、かつてのようにそれを地上での英雄伝説などという幼稚な捉え方ではなく、神界における創造活動の実話として捉えることができるのであろう。
ぐずぐずしていると外国の霊能者に先を越されてしまうかも知れない。英国の霊視能力者ジェフリー・ホドソンなどは、二十世紀初頭からすでに、竜神とか太陽神 (天照大神) の存在とその働きについての、きわめて高級な霊視記録を残している。
またマイヤースが送ってきた有名な自動書記通信 『個人的存在の彼方』 では
「かつて神話で火の中に生息したと伝えられているサマランダーと似ていないでもない」
とか
「彼らはさまざまな形体を取る。時には大蛇の姿になり、時には、龍の姿になることもある」
などという表現がみられる。抄訳を出された浅野和三郎氏も 「評釈」 の中で 「西洋の心霊家もとうとうここまで突っ込んだことを述べるかと思うと、実に感慨無量ではないか!」 と述べている。
ではその浅野氏の訳によるジェフリー・ホドソンの 『天使来』 The Coming of the Angels から一節を紹介して、本書の終わりとしたい。
《天使たちは太陽と全組織の大中心、一切の生命の大本源と考える。ただし、天使たちが太陽について抱く神秘的な意義は、一般の人には十分に分かっていない。太陽は実に最高級の天使たちの大本営であり、それより以下のすべての天使、すべての自然霊にとって、実に憧憬・渇仰の中心なのである。一切の活力、一切の指導方針はみなそこから付与される。
むろん最高級の天使においては、全組織の中に偏在する霊気と合流・融合してしまっているから、外部的に具象化した神の姿を特別に崇拝することはしない。彼らは万有に宿れる神と合一し、彼らにとって神は随所に存在するのである。要するに神とは力・光・生命及び意識の没人格的大中心なのである。
しかし、それは最高の理想の境地であって、その域に到達することは、わずかに少数の天使たちにのみ可能である。ふつうの天使たちはみな、太陽を崇拝の中心とするのである。
これがため彼らは、時として地上界を遠く離れた天空に留まり、各自の神格に応じて、秩序整然たる幾重もの円を描いて、感謝と祈願の誠を捧げる。円の層は一段、また一段と次第に高く重なり、末は渺茫(ビョウボウ)として無形の世界へと消える。
天使たちの身体はいずれも光り輝いているので、かくして造られた集団は、婉然(エンゼン)、生きた光の盃である。
すべての心は愛と絶讃とに満ち、すべての眼は生命の本源たる日の大神に差し向けられ、それが渾然融合して、ここに清き尊き力の凝体ができ上がる。その中から奔流のような凄まじさをもって迸(ホトバシ)り出る光の流れは、上へ上へと上昇して太陽神の御胸に達する。
俄然として虚空にいみじき音楽が起きる。礼拝者たちの胸の高鳴りが加わるにつれて楽声もまた強さを増し、ここに歓天喜地の、光と音との、世にも妙なる世界ができあがる。それにつられて天使たちも、日頃住みなれた領域よりはるかに高き境涯に進みのぼりて、太陽神の荘厳無比の御姿を目のあたりに拝するのである。
かくて全てが髄喜渇仰の最高潮に達した瞬間に、大神の御答えが初めて下される。それは黄金の光の洪水となって、全ての天使の魂にひしひしと沁み込む。前後左右、天上天下、辺りはただ澎湃(ホウハイ)たる光の海。
そしてその真っ只中に、いちだんと清く、強く、そして美しき、日の大神の御姿が浮かぶ。むろん、その御姿は見る者の霊格によってそれぞれ異なる。いかなる者も自己の器量だけしか拝むことができないのである》 (漢字・かな一部修正)
もうすぐ人類史の二日目が始まる──あとがきに代えて
一日に昼と夜があるごとく、また潮に満ち引きがあるごとく、霊性にも強く発現する時期と勢いが衰える時期とがある。これはサイクルという大自然の根本的な営みの一つのパターンであって、意図的に操作されているのではない。
そのサイクルの中のどの時期に生をうけるかによって、各自が受ける霊的影響の度合いが違ってくるということである。それは、たとえば日光の強弱にも似ていよう。朝方と真昼と夕方とでは日光の強さが違う。夜にはゼロになる。
では真昼がいちばん良いかというと、そうばかりとも言えない。夜という休息の時期があってこそ、昼間の活動のエネルギーが蓄えられる。日光が大切といっても、度が過ぎては害となることは周知の通りである。反対に日光が不足しても健康に害を来す。
霊的影響力もそれと全く同じである。本来は霊的存在でありながら、物的身体を機関として生活しているのが現在のわれわれである。現段階では地上人類の大半が自分の霊性に気づかず、物的身体こそ自分であると思い込んで生きているが、どう思い込もうと霊的存在であることは、スピリチュアリズムによってもはや決定的事実となった。
が、そう認識して霊的自覚が強まってきたときに注意しなければならないのは、霊的なことに関心が偏って物的側面をおろそかにしてしまうことである。言わば日光浴の度が過ぎるようなもので、生活全体、ないしは一生涯を尺度としてみた時に、決して健全とは言えない。物的側面への配慮をおろそかにしては、物的生活の場である地上へ降誕してきた意味がなくなるのである。
本書で私は、過去三千年の人類史をまる一日として捉え、イエスの処刑をもって昼の時代が終わり、やがて中世の暗黒時代へと入っていった過程をたどってみた。が、これをもって、夜の時代には必ずや不幸や悲劇や残忍性が出るかに受け取ってはならない。安らかな休息の時期である場合もあるはずである。
同じく、昼の時代だからといって、すべての人々が霊性の恩恵を受けるとも限らない。昼寝をむさぼっている人間もいる。
これまでの二千年の歴史が霊性を封殺する行為の連続だったのは、一つには人類がまだ未熟で元気な青二才だからであり、もう一つには、邪霊集団の暗躍を許してしまったからでもある。知性と霊性のアンバランスから生じるスキをねらって、死後の下層界にたむろする地縛霊の集団が好き放題のことをやったということである。
といっても、あくまでも人間を媒介として働きかけたのであるから、人間の自覚さえしっかりしていれば防ぐことができたはずのものである。
高等な霊界通信が口を揃えて人類の意識改革を求める理由はそこにある。罪悪を増幅する要素は霊界にあるのであるから、それを未然に防ぐ、あるいは大事に至らせなくするためのチェック機能を、各自がそなえることである。
今、地球環境の保全が叫ばれているが、環境破壊を生む根本的要素は何かといえば、人間の無知に帰着する。
たとえば無臭・無害で理想のガスと思われたフロンガスが、まさかオゾン層を破壊し、地上の生命の維持そのものまで脅かすものであるとは、考えも及ばないことだった。もとよりこれは誰一人咎められる性質の失策ではない。
咎められるべきは、自然環境にどういう影響を及ぼすかを考えずに、目先の目的と営利にとらわれて、あとは野となれ山となれ式にやってしまう、浅ましい根性である。
医学における動物実験なども、私の目には、かつての虐殺行為を医学の名のもとにやっているのと同じに見える。動物にも霊が宿っているからである。その動物が、一九八八年度の統計によると、実に八〇〇万匹も殺されているという。(日本実験動物学会表)
そういう根性を生み出す土壌は何かといえば、本書で私が指摘した大自然の霊性を忘れた病的精神構造である。
そう言う根性を生み出すほど心の環境が病的になってしまったところにある。地球環境の破壊の前に心の環境破壊があったということである。
その心の病的状態をシルバーバーチは、悪性の癌にたとえて次のように述べている。
質問 「いま地球全体に差し迫っているといわれる天災を未然に防ぐには、われわれはどうしたらよいのでしょうか」
シルバーバーチ 「この地球という天体について悲観的になるのはお止めなさい。人間の力の及ぶところではないからです。すでに申し上げた通り、人間のすることにはおのずから限界というものがあります。地球を丸ごと爆破することは人間にはできません。
地上世界にトラブルと困難と災難が絶えないのは、相も変わらず食欲と我欲と嫉妬心によって動かされているからです。一口で言えば物質第一主義のせいです。それはまさしくガンです。人類の精神構造の中枢部に深く食い込んでおります。悪性のガンです。悪性の細胞が急速に、そして一時も休むことなく増殖を続けております。
そのガン細胞を人間みずからの努力で取り除かないといけません。あなた方(サークルのメンバー)のような霊的真理に気づいた人が意識を改め生き方を改めることによって、人がそれを見習うようになり、それがガンを治療することになります。
あなた方はこうして神の光を少しでも受ける栄誉に浴した以上は、人類の未来について楽観的でなくてはいけません。取り越し苦労はいけません。常に希望に胸をふくらませることです。それがあなた方のまわりに自信にあふれた光輝を漂わせ、辺りの人に生き方のヒントを与えることになります。
人に先んじて素晴らしい宝を手にした以上は、人の手本になるような生き方をしなくていけません」
質問 「この地球世界へひきも切らず霊が誕生して来ますが、なぜでしょうか。なぜ地上へ来たがるのでしょうか」
シルバーバーチ 「それは、地球が霊の資質を磨く上で格好のトレーニングの場だからです。もしも神の機構の中で地球が存在意義をもたないとしたら、始めから地球は存在していないはずです。小学校が子供に対して果たしているのと同じ役割を地球が果たしているのです。死後の生活にとって必須のことを身につけさせてくれるのです。
地球は霊の鍛錬の場です。はがねが叩き上げられるのです。原鉱が砕かれて、黄金が姿を見せるのです。地球は神の機構の中にあって、掛け代えのない役割を果たしております」
その地球上での人類史の一日が終わって、もうすぐ二日目が明けようとしているという。その二日目には自分はもう地球にはいないかも知れない。霊の世界にいるかもしれない。しかし、イエスを最高指導者として地球圏の大霊団が地球浄化の大事業に乗り出した動機は何であったかを考えていただきたい。
緑を基調とした環境を特質とする地球は、右のシルバーバーチの言葉にもある通り、太陽系にあって、他の天体では果たせない存在意義を与えられているのだ。
地球浄化の大事業が高級霊界からの指示によるとはいえ、直接活動するのはわれわれ人間なのである。最終的には人間の自由意思にかかっているのである。私が披歴したスピリチュアリズムの思想にふれて真実を見出した思いをされた方は、地上よりはるかに活気と生き甲斐に満ちた次の段階の生活にそなえて、今すぐから意識の改革に取りかかっていただきたい。事の性質上、自然にそうなるはずのものなのである。
その時から背後霊団の新たな働きかけが始まるであろう。それが、ささやかながら、地球の浄化に貢献するゆえんでもあると私は信じている。
近藤 千雄
シルバーバーチ記念〝サイキックフォーラム21〟発足のお知らせ |