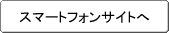霊的人類史は夜明けを迎える
スピリチュアリズム誕生の系譜
スピリチュアリズムの原点に立ち帰れ 近藤千雄著
目 次
・世界中の超常現象研究家が結束 ・近代の有名なポルターガイスト ≪スザノ事件≫ ≪ホロウェイ事件≫ ≪セロン事件≫ ≪バーミンガム事件≫ | 第三部 霊性の〝夜明け前〟 第一章 スピリチュアリズムの予兆 (一) エマニュエル・スウェーデンボルグ ・致命的だったキリスト教の影響 ・〝新教会〟(ニューチャーチ)の偏向 (二) A・J・デービス ・スウェーデン・ボルグが支配霊 ・致命的欠陥 ・霊媒と人格 第二章 スピリチュアリズムの勃興 (一) ついに〝電話のベル〟は鳴った ・エプワース事件とハイズビル事件 ・フォックス夫妻の証言 ・五十年後の立証 付記 ・〝電話のベルが鳴る仕掛けは他愛もないが〟 (二)現代の啓示 ─スピリチュアリズムの三大霊訓 ①──インペレーター霊団の自動書記と霊言による霊訓 ・大きかったスピーア博士夫妻の存在 ・モーゼスは人類の代弁者 ・危険をはらんだギリギリの選択 ②─ザブディエル霊団の霊感書記による霊訓 ・スピリチュアリズムのアニメーション ・二大特質 ③──シルバーバーチ霊団の霊言による霊訓 ・大きかったハンネン・スワッファーの存在 ・四つの思想上の特徴 第三章 既成宗教界とスピリチュアリズム (一) キリスト教会がとった態度 ・英国国教会の「スピリチュアリズム 調査委員会」による〝多数意見報告書〟 ・聖職権主義が〝真実〟をも葬る (二) 大幅な修正を迫られる仏教の来世観 ・天保十年丁亥八月廿四日夕陰霊出現発端の事 ・「無念のことありて割腹せし者の霊なり」 ・「死後の世界は生前に考えおるものとはいたく異なるものぞ」 ・「百里千里も一瞬の間にて行くべし」 ・「儒仏の説くところを信ずるは、みなその道におもねる者のすることにて」 ・霊の誓約書 ・いったん霊界へ戻る ・火事騒ぎ ・「今は包み難ければ物語らん」 ・災厄の原因と厄払い ・「いまだ墨痕の乾かざる四、五百年前の古筆を拝覧するとは・・・」 ・御霊遷しの神事 ・月いっぱいなるぞ 付記 (三) 普遍的宗教としての神道に求められているもの ・脚下照顧 ・いくら自国の遺産を誇ってみても ・もっとインターナショナルなものに ・スピリチュアリズムの原理に照らして総点検を もうすぐ人類史の二日目が始まる──あとがきに代えて シルバーバーチ記念〝サイキックフォーラム21〟 発足のお知らせ |
第一部 霊性の〝昼〟の時代 第一章 神霊の実在を意識した古代人の生活 ・神社にみる古代人の霊的感性 ・卑弥呼は霊能力を持つ女王だった ・ インディアンの素朴な自然宗教 ≪四つの教え≫ ≪十二の戒め≫ 第二章 高級霊の地上への降誕 ・高級霊とは? ・イエスに至る超高級霊の系譜 第三章 地上時代のイエス ・バイブルの中のイエス ・バイブルの〝外典〟ならびに〝偽典〟の 存在 ・〝歴史上最大の陰謀〟のあらまし ・霊界通信に見るイエスの実像 第四章 イエスは十字架上で死んでいなかった? (一)アッピア街道で大工として短い余生を送ったとする説 ・愛犬プルートーを従えて ・ペテロとの再会 (二)インドで伝道と治癒活動を続けたとする説 ・エッセネ派との関わり合い ・ダマスカスにいったん身を隠す ・イエスとマリアの墓 (三)〝目撃者〟と称するエッセネ派の長老の手記 ・イエスもバプテスマのヨハネもエッセネ派に属していた ・大地震が二度起きる (四)その他の諸説 付記 第五章 霊界へ戻ってからのイエス ・人間的努力と霊の援助 ・人類の地上降誕の目的 ・イエスとキリスト教とは無関係 ・教会の原型は交霊会だった ・イエスは今も地上人類のために働いている ・イエス・キリストとブッダ・キリスト ・神々による廟議 ・地球的視野への意識改革 | |
闇の支配するときだ 第二章 ローマ帝国とキリスト教 ・邪霊集団が狂気を増幅する ・悲しむべき〝政略婚〟 ──キリスト教の国教化 ・コンスタンチヌスの二つの顔 第三章 人類の狂気──異端審問と魔女裁判 ・〝しるしと不思議〟を忘れた身勝手な神学の罪悪 ・〝聖なるもの全てが逃げ去った〟聖職者の堕落と 腐敗 ・十字軍の暴虐 ・異端審問 ・魔女裁判(魔女狩り) ・ジャンヌ・ダルクの例 ・霊性の封殺 ・スピリチュアリズムは〝霊性のルネッサンス〟 付 記 |
まえがき
人間が地上に棲息するようになって二百万年余りになるという。ほぼ四七億年という気の遠くなるような地球の全歴史に比べれば、それこそ瞬きするほどの時間にも相当しないかも知れない。地球の誕生から現在までを仮に一日とすれば、人類が誕生してまだ一分も経っていない計算になる。
こうした時間感覚でいくと、〝有史以来〟と呼ばれている数千年の歴史などは、たった一、二秒に過ぎないことになる。しかし一方、現実の時間感覚、つまり百年生きるのがやっとという人間の寿命を尺度として考えると、数千年という歴史は、やはり、長い。
こうした時間感覚を述べたのは、これから本書で扱うほぼ三千年の歴史が、〝霊性〟の消長という視点から見ると、〝昼〟の時代と〝夜〟の時代とに分けられ、今こそ地球人類は、いみじくもイエス・キリストの処刑とともに始まった暗黒時代を終えて、第二日目の夜明けを目前にした、最も厳しい努力を迫られている時期───過去三千年が一日に相当し、現代という世紀末は霊的な夜明け前の漆黒の闇の中にある、ということが明らかとなってきたからである。
それは何を根拠としているのか。ひと口で言えば〝スピリチュアリズム〟と呼ばれる、霊媒現象を基盤とした霊的思想による。そのスピリチュアリズムに関しては、拙訳 『コナン・ドイルの心霊学』 (新潮選書) や 『人生は霊的巡礼の旅』 (ハート出版) その他でその概略を紹介した。
本書でも第三部でさらに詳しく紹介するつもりであるが、その思想の中核をなしている概念は、人間は今この時点においても立派に〝霊的存在〟であるということ、言い換えれば、死んでから霊になるのではないということである。そして、肉体が滅んだあとも幽界・霊界・神界と果てしない生命の旅が続く。
そのことが、十九世紀後半から二十世紀前半にかけてのほぼ百年間に、多くの分野の学者・科学者・知識人による実験・研究によって立証されたのである。コナン・ドイルも言っているように、これはもう〝信仰〟ではなくて確固たる〝事実〟であると言わねばならない。
すでに彼岸へと旅立った先輩たちからのメッセージ、いわゆる霊界通信によると、われわれは今その生命の旅の途中で、何かの縁でこの地球という天体上でいっしょにトレーニングをしているのだという。地上生活をそう位置づけることによって、はじめて地上人生の意義が自覚されるというのがスピリチュアリズムの主張するところである。
本書で私はスピリチュアリズムの淵源を遠く三千年有余年もさかのぼり、歴史的現実に即しながら、今日の人類が抱える問題を見つめ直してみたいと思う。
その歴史はローマ帝国とキリスト教との関わり合いの中で展開するが、読者にお願いしておきたいのは、それを日本と無縁の遠い西欧の問題としてではなく、根本的には人類史の第一日目に生じたグローバルな問題と受けとめていただきたい、ということである。
その影響がこの世紀末に至って、今、地球人類全体に及んでいると私は見るのである。もはや自分の家の周りを掃除するだけでは済まされない事態に立ち至っている。さきの中東湾岸戦争で世界中の人間がそれを思い知らされたばかりである。
さらに、スピリチュアリズムが手にしている高等な霊界通信によって、地球神界ではそうした事態を早くから察知して、三千年も前からそれに対する手段を講じてきていることも分かってきた。
神道流の表現を用いれば、地球浄化の神勅が三千年も前に下されていたのである。それが今、スピリチュアリズムという名の思想活動となって顕現しているということである。
その思想の根幹は、さきも述べたように、われわれ人間は肉体をたずさえた霊的存在であり、神の分霊として各自がその霊性を発揮していくことが地上生活の目的であるということである。人生をそうした視野で捉えるようになった時にはじめて、この掛け替えのない緑の地球を大切にしなければ、という自覚が芽生えるのではなかろうか。
少なくとも人類の先輩たちはそういう発想のもとに、後輩であるわれわれのために、顕と幽との間の幾多の障害を乗り越えて地上界とコンタクトし、警鐘を鳴らしてくれたのである。その趣旨を、本書を通して正しく伝えることができればと思っている。
序論 暗黒時代はまだ終わっていない
・一九八二年の魔女裁判
つい先頃(一九九〇年)刊行され、映画化も企画されているというノンフィクション〝迷信〟superstition は、キャロル・コンプトンという当時十八歳の英国人女性が〝魔女〟としてイタリアで裁判にかけられ、放火と殺人未遂で有罪の評決を受けた経緯を本人自ら綴ったもので、日本ではまったく話題にされていないが、欧米では超心理学者や超常現象研究家が連名でその理不尽な裁判に抗議し、キャロルの即時釈放を求める嘆願書を提出したほどで、今なお関心を持ち続けている学者が少なくない。
あら筋を述べると、スコットランドに住むキャロルは、一九八二年、休暇旅行にきていたイタリア人青年と恋仲になり、帰国したその青年からイタリアに来るようにしきりに求められ、言語・習慣・気候の違いに不安を抱きながらも、結婚を夢見て一人で旅立った。
二人ともローマ・カトリック教徒で、とても信仰が厚かったことから、正式に結婚式を挙げるまでは同棲すまいと誓い合って、キャロルは結婚資金を貯めるために、二軒の家でベビーシッターとして働くことになった。
そのことが思いも寄らなかった悲劇を生むことになる。働きはじめてわずか三週間の間に、五度の火事を含む異常現象、いわゆるポルターガイストが続発したしたのである。
壁から絵画が落下する。彫像やケーキスタンドが目の前で移動する。ガラスの花瓶がいきなり破裂する。水が一気に沸騰する、等々。
そして五度目の火事では、キャロルが面倒を見ていた三歳の子供が煙に巻き込まれて危うく死にそうになったことから、その子の親がキャロルが故意にやったと訴えたために、警察に連行されてそのまま拘置される。
新聞があれこれと書き立てていくうちに、いつしかキャロルは〝魔女〟であるとのうわさが出はじめる。頼りにしていた恋人もいつしか心が遠のき、よく掛っていた電話も途絶えてしまう。
拘置中の取り調べも、前例のない事件だったことから検事の尋問と精神科医の診断などで長引き、実に十七か月もの拘留期間を経て一九八三年の十二月に裁判となり、放火と放火未遂罪で二年六カ月の懲役刑を言い渡される。が、拘留期間が長すぎたことを理由に、即時釈放される。
殺到するマスコミを避けながら、大金を払うという英国の新聞社の記者とカメラマン、そして母親の四人で車でフランスへ逃れ、空路、故郷のスコットランドにようやく辿り着く。自著の〝まえがき〟でキャロルはこう述べている。
《私はスコットランドに住む平凡な主婦であり、二児の母親です。
二十七歳になった今、これまでひたすら夢見てきたもの、すなわち愛する夫と子供という〝自分自身のもの〟を手にしております。それが私の唯一の望みだったのであり、ひたすらそれのみを求めてまいりました。
思い起こせば今からほぼ七年前、皮肉にもその平凡な望みが禍して、私は悪夢のような体験──今なお奇怪で説明不可能な恐怖の体験をさせられることになったのです。
人は私のことを〝魔女〟扱いにしました。私のいた場所から遠くないところで物が何の原因もなしに落下する。冷たい水が沸騰しはじめる。火事が起きる。そうした現象をすべて私のせいにしました。一度は、私がベビーシッターをしていた幼い女の子が危うく焼死しそうになりました。
私はたちまちイタリアの報道機関のさらし者にされました。それまで優しく面倒を見てくれていた人たちからも悪者扱いにされました。そして、単なる状況証拠だけで投獄されて、一度の審理もないまま、言葉の通じない異国で十七か月間も拘留されました。そしてついに一九八三年十二月十五日に、放火と殺人未遂のかどで裁きを受けました。
殺人未遂は〝証拠不十分〟で却下されましたが、放火と放火未遂罪は有罪となりました。
裁判所側が検察側の証人の言い分を全面的に信じたことは明らかです。でも私は、逮捕の時点でも、拘留中も、そして公判が終了するまで、一貫して全く身に覚えのないことであることを主張し続けました。
もちろん今なお、私は無実を主張いたします。(中略)
この本は、スティーブン・ヴォルク氏とジェラルド・コール氏との長期間にわたる対話の末に、私がまとめたものです。ヴォルク氏は映画化のためのシナリオを書いてくださり、コール氏は本書の執筆を手伝って下さいました。
私の体験は、世界で最も近代的な国家においてさえも、今なお迷信というものが、悪魔的な威力を持つことがあることを警告していると言えるのではないでしょうか。(後略)》
・世界中の超常現象研究家が結束
さて裁判が進行中に、このキャロルの弁護のために世界中の超心理学関係の専門家を動員する案を出したのは、キャロルの故郷のエアー出身のジャーナリスト、故アイリーン・ロス女史で、その訴えに賛同して、博士号を持つ石油会社の取締役で〝異常現象研究協会〟の創設者でもある H・ピンコット氏と超常現象研究家のG・L・プレイフェア氏の二人が、その訴えの輪を広げた。
ピンコット博士は一九八二年十二月十八付の 〈サイキック・ニューズ〉 紙上で、
「私は、この文明と科学技術の発達した時代に、これほど硬直した偏狭と無知と迷信の壁があることを知って、身の毛もよだつ思いがしております」
と語り、またプレイフェア氏は十二月十二日付の 〈ニューズ・オブ・ザ・ワールド〉紙上で、
「キャロルは断じて犯罪人でも魔女でもありません。私のほかにも、いかなる犠牲を払ってでも彼女の弁護に立つ用意があると言明している研究家が大勢います」
と語った。その二人の呼び掛けに応じて 〝弁明書〟を寄せてきたのは、次の十三名だった。
・A・R・G・オーエン教授 トロント大学医学部、予防医学並びに生物統計学科。
・D・F・ローデン教授 アストン大学 (バーミンガム)数学部部長。
・ハンス・ベンダー教授 フライベルク大学、心理学ならびに精神衛生の境界域研究所所長。
・H・G・アンドラーデ博士 電気工学者。ブラジル精神生物物理学研究所の創設者。
・J・ベロフ博士 エジンバラ大学、心理学上級講師。心霊研究協会(SPR)前会長。
・A・J・エリソン教授 シティ大学(ロンドン)電気・電子工学部部長。
・J・B・ヘイステッド教授 バークベック大学(ロンドン)物理学部部長。
・A・E・ロイ教授 グラスゴー大学(スコットランド)天文学部部長。
・アーサー・ノース氏 北ロンドン・ポリテクニック上級講師。
・J・F・マックハーグ博士 顧問精神科医。ダンディ大学(スコットランド)名誉精神医学講師。
・A・O・ゴールド博士 ノッティンガム大学心理学上級講師。
・ジーン・ダーケンズ博士 エノ―州立大学(ベルギー)教育心理学科主任。
右の〝弁明者〟からの回答には証拠資料としていくつかの〝前例〟が挙げられている。その中から顕著なものをあげれば───
《スザノ事件》 (一九七〇年・ブラジル)
サンパウロのスザノという小さな町の平凡な家庭で、確認できる原因はなにも見当たらないのに、計十六回も火災が発生した。燃えたものはマットレス、ソファ、タンスの中の衣類、そしてそのタンスそのものなどだった。
このケースは、その火災のいくつかが市の警察署長と法廷関係の専門家が立ち会っていた。その目の前で発生したという点で特殊性を持っている。署長は事件発生後ただちにブラジルの超心理学の大家 H・G・アンドラーデ氏に詳しく報告している。
《ホロウェイ事件》 (一九七八年・ロンドン)
夫婦二人きりで住まっている公営アパートで七回も原因不明の火災が発生し、そのつど消防車が出動した。燃えたものはセーター、食器用ふきん、積み重ねた新聞、それにベッドなどだった。現場で消火に当たった消防士の一人は「こんな火事は初めてです」と言い、ホロウェイ市火災防止委員会の主任も、
「原因は全く不明。どういう具合にして出火したかは、何一つ手がかりがつかめない」 と結論付けている。
《セロン事件》 (一九七九年・フランス)
この事件はまさにギネスブックものである。ピネレー山脈の麓の小さな村セロンで、一九七九年の八月中だけで実に九十八回もの火事が発生している。それも二十人の警察官を含む大勢の村人や報道関係者が見ている前での出来事である。やはり出火原因は解明されていない。
証人の一人は、ベッドや衣類の一部が小さく焦げてくるのが見え、やがて炎となって燃え上がったという。キャロルと同じように、二人の若者が拘置されて取り調べを受け、証人もおらず動機も不明のまま起訴されたが、すぐに釈放されている。
《バーミンガム事件》 (一九八〇年・イギリス)
これはカッサンドラ・ウィッケンデンという名の三歳の女の子が寝室で煙に巻かれて窒息死した事件で、検死官による陪審の記録が残っている。検死官が別の寝室に捨てられていたタバコが出火の原因ではないかという曖昧な憶測発言をしたために、母親が激しい口調でこんな抗弁をしている。
「とんでもありません! あの部屋には一日中だれも入っておりません! なぜ信じようとなさらないのですか? そんな出火の仕方ではなかったのです!」
この事件の特徴は、両親とも、出火の原因はある種の未知の力しか考えられないと主張し続けたことである。
第一部 霊性〝昼〟の時代
第一章 神霊の実在を意識した古代人の生活
・神社に見る古代人の霊的感性
〝祭り〟は世界中どの民族にもある。が、そのことを〝どの民族もお祭りが好きである〟と解釈すると、そこに〝祭り〟の意味にズレが生じるように思う。お祭りが好きだったのではなく、太古にあっては神をマツルことがその地域の生活の最大の行事だったのである。
そのことは、かつては政治のことを〝まつりごと〟といったことに端的に表れている。ただ、祭り方が少しずつ形を変えながら受け継がれていくうちに、その意義が忘れられて、次第に〝お祭り〟となっていったのである。
現代では〝お祭り〟という言葉に〝神を祀る〟という観念を読み取る人はすくないのではなかろうか。
ちなみに辞典で〝まつる〟の項を調べてみると──
《神仏をまつること。神仏・祖霊などに奉仕して慰撫・鎮魂したり感謝・祈願するための儀式・祭祀》 (小学館・日本国語大辞典)
とあり、現代人が〝お祭り〟という言葉から連想しがちな、のどかで楽しい行事とは異なる、厳粛で真剣なイメージをほうふつさせる。
むろん現代においても、その厳粛さが受け継がれている儀式はある。例えば天皇家に伝わる〝大嘗祭〟(だいじょうさい)がその最たるもので、平成元年に今上天皇の即位後に行われた時も、そのクライマックスともいうべき〝霊と語る〟場面は、テレビカメラによる撮影は許されなかった。
これは、その年に新たに収穫された穀物を、天皇自ら祖神・天照大神を始め天地の八百萬の神々に差し上げる行事である。解説者による図解説明を見ていて私は、そのあまりの単純素朴さに、かりにテレビで放映されても、視聴者は 「なんだあんなものか」 といった印象を抱くにちがいないと思った。
同じことが神社の形式にも言えるであろう。まず社殿の作りそのものが極めて簡素である。白木造りで、それは何の装飾も施されていない。その奥に祀られている御神体も、ただの玉だったり石だったり鏡だったりする。
辺りを取り囲むのは老松老杉(ろうしょうろうさん)の木立で、少なくとも見た目には、キリスト教の大聖堂や仏教の大伽藍に見られるような、目を奪うようなきれいさは見られない。もしあちらを芸術的と評するのであれば、こちらには芸術性は見られないことになりそうである。
が、霊的観点からみた時、つまり心霊と人間との念波の感応の場という観点からみた時、日本の神社ほど霊的原理に適ったものはないと言えるであろう。
鳥居をくぐることによって気持ちを引き締め、玉じゃりを踏みしめながら神殿に近づき、石(いわ)の階段(きざはし)を上がるにつれて厳かさが次第に増し、御手洗(みたらし)で口をすすいで清浄な気持ちになって神殿を拝む。そのすべてが精神を統一させ、波動を高める上で無言の助けとなっているのである。
こうした祭祀の伝統の中に残されている古代日本人の霊的感性の高さと鋭さに感嘆の念を禁じ得ないのである。
・卑弥呼は霊能力を持つ女王だった
その神社で取り行われる行事も、今日ではかなり形骸化してそれ本来の意義が見失われているように見受けられるが、その由来をたどると、実に霊的原理に適っていることに驚かされる。
神主とはカミを祀る行事のヌシ、つまりは司会者のことで、一般的にはサ二ワと言い、〝審神者〟という漢字を当てている。これを字解すれば〝神を審(つまび)らかにする人〟という意味で、かつてはカミという用語は目に見えない存在のすべてに当てていたので、要は霊媒に憑かって語る霊の素性を判断する役目の者が、神社では神主と呼ばれるようになったのであろう。
交霊会においてもサニワの能力と人格の高さが、低級霊や邪霊集団によるイタズラを防ぐと言われる。霊媒の能力がいくら強力でも、霊媒現象においては霊媒は大なり小なり無意識状態に入るので、いわば無防備状態になり、いかなる素性の霊に操られるかわからない。そこでサニワの存在が大切となってくるのである。
神社においてその霊媒に相当する役が巫女で、〝神子〟という文字を当てることもある。〝神和〟(かんなぎ)と呼んだこともあるらしい。
つまり神前で神楽を舞って神を和ませる役ということで、それが神憑(かみがか)りとなってお告げを述べることもした。大体において未婚の女性だった。現代では女性と決まっているようであるが、霊媒的な役目はしていないように見受けられる。
さて、女性霊媒として古い文献に出てくる有名な人物としては、かの卑弥呼がいる。最近発掘が完了した筑後川流域の吉野ケ里遺跡が邪馬台国論争に油を注ぎ、ヒロインの卑弥呼が劇画や漫画でさまざまな人物像に描かれている。が、スピリチュアリズム的に見れば〝霊媒能力を持った女王〟であって、祭政一致の原始的な社会形態の中心的人物だったといえると思う。
その証拠となるのは有名な 『魏志倭人伝』 で、その中の一節にこう出ている。(安本美典著 『吉野ヶ里の証言』 による現代語訳)
《その国はもと、また男子をもって王としていた。住(とど)まること七、八十年、倭国は乱れ、あい攻伐して年を歴(へ)る。すなわち、ともに一女子をたてて王となす。名づけて卑弥呼という。鬼道につかえ、よく衆を惑わす。年はすでに長大であるが、夫はいない。男弟があって佐(たす)けて国を治めている。王となって以来その姿を見た者は少ない。
婢(はしため)千人をもって自らに侍(はべ)らせている。ただ男子が一人あって飲食を給し、辞(ことば)を伝え、居処に出入りしている。宮室(居所)・楼観(宮殿)・城柵を厳かに設け、つねに人がいて兵器をもち、守護している。》
ここに言う〝鬼道〟とは、中国の影響を強く受けていた当時(三世紀)のことであるから、道徳的な呪術のことと察せられるが、スピリチュアリズム的に見れば霊媒現象のことで、さらに〝よく衆惑わす〟とは、目をみはるような超常現象を見せて人々をびっくりさせたということであろう。
また、姿を見た者はいない云々というのは、神聖なものとして宮室に控え、男子一人に身の回りの世話をさせ、儀式に際しては弟が神主の役をしたということであろう。千人もの下女がいたというから、よほどの勢力をもった武装国家だったことが想像される。
・インディアンの素朴な自然宗教
北沢図書出版から出版された拙訳 『レッドマンのこころ』 The Gospel of the Redman は 『動物記』 で有名なアーネスト・シートンがスピリチュアリズムの観点から、インディアンの伝統的精神文化──信仰・教育・戒律等──と、それがキリスト教徒である白人の侵略によって破壊されていった歴史を紹介したもので、比較的少ないページにぎっしりと中身の詰まった好著である。
これまでにもインディアンを扱った著書は少なくない。日本人が著わしたものも多いし、英米人が著わしたものはさらに多い。が、私がシートンの著書をぜひ訳したいと考えたのは、その観点が他の多くの著書にとかく見られがちな、滅びゆくインディアンに対する同情心と、侵略者である白人に対する反感や憤りからではなく、インディアンの純粋この上ない心と、霊的知識、そして自然と一体となった信仰が実にスピリチュアリズム的だからである。
いつだったか、テレビ番組でアイヌ人の音楽家が、アイヌ語には〝自然〟という言葉がないが、それはアイヌ人の思想では人間も自然の一員であり対立的に捉えないからだと述べているのを聞いて、虚を突かれた思いをしたことがある。
インディアンの思想もまさにそれで、NHKテレビ〝海外ドキュメンタリー〟『インディアンの悲劇』 の中でインディアンの一人が、
「人間が大地を所有しているのではなく、大地が人間を所有しているのです。人間は大地の一部なのです。そうした考えを日々再確認すべきです」
と語っていた。もう一人のインディアンは、
「大地から何かを受け取ったら何かを返すべきです。一方的に大地から奪う自己本位の姿勢は問題です。私たちが信じているのは宗教ではなく、〝生き方〟です。〝大いなる霊〟の存在を信じ、その摂理を信じる生き方です。周囲のすべてのものに宿る偉大なる霊と調和する、畏敬に満ちた深遠なる生き方です」
と語り、最後に、聡明そのものの容貌をした女性インディアンがこう締めくくった。
「私の祖父が死ぬ前に大地の話をしてくれました。私たちの世代にこう言い残したのです──〝いつかは大地は泣くだろう。命乞いをして血の涙を流すだろう。大地を救うか死なせるかは、おまえ達の選択次第だ。大地が死ぬ時、人も死ぬ〟と。
大地が破壊されて取り返しがつかなくなりつつある今こそ選択の時であり、自分や自分の子供のためでなく、万物のための選択です」
彼女はそう述べて、目をうるませていた。ここは環境問題を論ずる場ではないのでこれ以上深入りはしないが、〝賢人会議〟でいかなる対策を論じ合い、国連でいかなる議決をしても、その基盤としてこうした素朴な自然認識がないかぎり、効を奏さないであろう。さきの 『インディアンの悲劇』 でもう一人の賢者の風貌をしたインディアンが、さりげなくこう言っていた。
『世界平和を叫ぶ前に、自分と仲間たちの平和を願うのです。その小さな平和から尊敬と愛の念が生まれ、仲間への敬意が生まれます』
シートンの著書の第一章は、そうしたインディアンの素朴な思想と信仰を取りあげ、その冒頭に、代々語り継がれてきた 《四つの教え》 と 《十二の戒め》 が紹介されている。次の通りである。![]()
《四つの教え》
(一)唯一絶対の大霊が存在する。万物の創造者であり支配者である。われわれはその分霊としての存在を有する。
それは永遠の存在であり、形体をもたず、全知にして全能であり、言語で描写することのできない存在である。あらゆるものが大霊の中に存在し、大霊を通して活動する。われわれの崇拝心と忠誠心は、その大霊に向けなければならない。![]()
恵みはすべて大霊より下される。ゆえに、敬虔なる気持ちで大霊を志向しなければならない。その恩恵に浴するためには、祈りと犠牲と思いやりのある生活を重ねることが必要である。大霊についての知識を得るためには、鍛錬と断食と寝ずの行を重ねる必要がある。その知識(さとり)とともに導きが得られる。
大霊は本質的には非人格的存在である。それが動物や小鳥、雲、雨、山河、人間あるいは動物に宿り、個性をもって顕現してるのが現実である。その大霊のもとに無数の個霊が控えている。
(二)地上に誕生した人間が第一に心掛けねばならないことは、人間として円満な資質を身につけることである。
それは、人間を構成する器官とエネルギーを正常に発達させ、それを正しい手段で満足させることによって達せられる。すなわち、肉体的に、霊的に、そして人のために役立つ資質において、成人となることである。
(三)成人としての高度な資質を身につけたら、その資質を部族のために捧げないといけない。何よりもまず自分の家族の大黒柱となり、勇気ある保護者となり、親切で頼りがいのある隣人となり、家族とキャンプ、及び部族全体を外敵から守らねばならない。
(四)人間の魂は永遠に不滅である。
いつこの世にやってきて、去ったあと、いずこへ行くかは、誰にもわからない。しかし、いよいよ死期が訪れたら、これから次の生活の場へ行くのだということを知っておくべきである。
その世界にどういうことが待ち受けているかは確かめることはできない。が、恐怖心を抱いたり、やり残したことや為すべきでなかったことを後悔したり泣いたリしてはいけない。与えられたかぎりの才能と制約の中で最善を尽くしたという自覚、そしてその死後の境遇は地上での所業で決まるという認識をもって、腹を決めることである。
〝死の歌〟を高らかに口ずさみながら、勝利の凱旋をする英雄のごとくに、死に赴くがよい。 (〝死の歌〟は死ぬ間際に自らうたう歌として、自分でこしらえておく。)
《十二の戒め》
(一)神はただ一つ〝大霊〟がおわすのみと心得よ。
永遠にして全知・全能であり形体をもたない。いついかなる時も、あらゆる存在の中に行きわたっている。
その大霊を畏敬せよ。が、同時に、他人がそれがどういう形で敬おうと、それを尊重せよ。なぜなら、すべての真理を手にしたものは一人としていないのであり、自分が敬虔なる気持ちで敬っているものを他人からとやかく言われる筋合いはないのと同様に、他人が聖なるものとしているものには敬意を払わなければならないからである。
(二)大霊を形あるもの、つまり目に見える存在として描いてはならない。
(三)言葉の信義を神聖に保つこと。
いついかなる時でも、ウソをつくことは恥ずべきことである。大霊はいついかなる時も遍在しているからである。大霊の名のもとに偽りの誓いをすることは、死にも値する罪である。
(四)祝日を大切にし、インディアン・ダンスをきちんと習い、タブーには敬意を払い、部族の慣習を守ること。それが部族内における良き一員として、その恩恵に浴する道である。そうしたものは太古から伝えられてきた先輩たちの英知から生まれたものだからである。
(五)父と母、およびその父母を敬愛し、その言に従うこと。年令はすなわち英知であり、自分への厳しい躾は、終生、きっと力となり利益となるであろう。
(六)人を殺(あや)めてはならない。もしも部族の仲間を故意に殺した時は、それは死にも値する罪である。万が一誤って殺した時は、評議会にかけて、それ相当の償いが課せられるであろう。
(七)思考と行為において常に純潔であれ。結婚式の時の互いの誓いを忘れず、人に同じ誓いを破らせることがあってはならない。
(八)盗むべからず。
(九)必要以上の富を蓄えてはならない。
部族の他の仲間に困っている人がいるのに、自分だけ大きな蓄えを所有することは恥ずべきことである。同時にそれは、下劣な罪の最たるものである。
戦勝の結果にせよ、取引の結果にせよ、あるいは大霊から賜った才能のお陰にせよ、自分ならびに家族の生活にとって必要以上のものが手に入った時は、部族のものを集めて〝施しの会〟を開き、余分のものを、困っている人たちにその度合いに応じてわけてあげるべきである。とくに未亡人、孤児、身寄りのない人を優先すること。
(十)健康に有害な火酒類 (度の強いアルコール類) に手を出すべからず。体力を奪い、賢明なる者を愚かにし、洞察力を狂わせるものは、食べものであろうと飲みものであろうと、試してみることもならない。
(十一)つねに清潔を心がけるべし。身体のみならず住居の中も清潔に保たねばならない。毎朝の水浴を欠かさず、必要とあらば蒸し風呂で体調を整えよ。肉体は霊の聖なる殿堂だからである。
(十二)自分の生活を大切にし、それを完全なものとし、その中で生じるものを全て美化し、自分の力と美を誇りとせよ。
生きているということに魂の奥底からの喜びを覚え、一日でも長生きして、部族のために役立つことを心がけよ。そして、いずれ訪れる死に備えて、堂々たる〝死の歌〟を用意せよ。
これをお読みになれば、さきのインディアンの男女が語っているところがよく理解できるであろう。それは第三部で紹介するシルバーバーチと名のる古代霊の教えとそっくりである。同時に、日本の古神道、いわゆる〝かんながら〟の思想とも相通じるものがあることもお気づきと思う。
実は太古の人間は、万物に霊が宿ると信じ、従って自分たちも自然の一部としてやはり霊を宿しており、肉体の死後も霊として永遠に存在し続けることを、当たり前のように信じていたのである。
もちろん民族によって洗練の度合いがあり、信仰の形態は異なっていたであろうが、基本的認識においてはほぼ同じだった。霊的にそう直感していたのである。
ただ、それが時代と共に人間的な脚色がなされていったということである。そのことを物語るエピソードとして、シートン氏は〝まえがき〟で次のような興味ある話を紹介している。
《・・・・・・草稿が完了して間もなくのことであるが、ユダヤ教の博学な律法学者が訪ねてきた。そしてその草稿に目を通してから、驚いた口調で 「これはまさしくユダヤ教そのものじゃないですか」 と言った。
それから何週間かして訪れた長老派教会の二人の牧師は 「これはまさに現代の長老派教会の教えそのものですよ」 と言った。
さらにギリシャ正教の大司教は 「これは儀式典礼がないだけで、純粋のカトリック教ですよ」 と言った。
クェーカー教徒の一人は 「うちの教会で教えていることと同じ」 だと言い、ユニテリアン派の牧師は 「純粋のエマソン主義的ユニテリアン」 であると言い、最後に、つい先日のことであるが、フリーメーソンの一人が 「うちの教団の教え以外の何ものでもない」 と言った。
こうしてみると、どうやらレッドマンの信仰は普遍的であり、基本的であり、根源的であり、本当の意味での宗教であると言うことであろう。となれば、当然それは、ドグマから脱け出て真実なるものを求めている求道(グドウ)者には、等しく受け入れ入れられるべきものであるに相違ない。・・・・・・》
第二章 高級霊の地上への降誕
・高級霊とは?
〝純正〟の折り紙つきの霊界通信によれば、地球上のいずこの国においても、又いつの時代にあっても、したがってこの現代においても、〝導師〟というべき高級霊が自発的に、あるいは勅命を受けて、地上に誕生しているという。
そういう人物は、必ずしも側から見てそれとわかる風采をしているわけでもなければ、それらしい指導的地位にあるともかぎらない。むしろ、どちらかというと身分の高い階級、由緒ある家柄、社会的地位の高い職業は避けるものだという。なぜか。霊性の進化という至上目的にとって、それがプラスどころか、マイナス要因にしかならないからである。
高級霊ともなると、その目的とするところは徹底して〝向上進化〟なのである。そして、その人の〝存在〟そのものが縁ある人々に、人知れず、霊的影響を及ぼしているという。
これを逆の視点から見れば納得していただけるであろう。すなわち、もしも高級霊が好んで身分の高い階層、由緒正しい家柄に生を受け、社会的地位の高い職業に就いてくれれば───そんなことが簡単にできるとすれば───社会は、そして世界は、もっともっと明るく住みよいところとなっているはずである。
なぜそうならないのか、なぜそうなるように配慮してくれないのか、という疑問は誰しもが抱くところであろう。
国王や首相や大統領をはじめとして、閣僚のすべて、重要ポストのすべてに、英知と決断力に富む高級霊が就いてくれれば、戦争も悲劇もない地上天国が今すぐにでも実現するはずである。それがそう理想どおりにいっていないところに、因果律の絶対的な公正の働きがあることを知らねばならない。
人間の一人一人に遠い過去───霊的に言えば〝類魂〟(〝血縁〟の家族とは別の、〝魂〟の家族とも言うべき、同じ霊系に属する霊の集団のこと。グループソールとかアフィニティといったりする。)が代々こしらえてきたカルマ───があり、それが地上的環境条件を機縁として発現し、そして解消されていく、
その営みだけは絶対に避けて通れないように、家族単位、社会単位、国家単位で犯してきた罪過も、何らかの形で解消していかなければならないらしい。ちなみに、パイパーという女性霊言霊媒を通じて一八九九年に次のような予言がなされ、そして見事に現実となっている。
《来るべき二十世紀には、このスピリチュアリズムが驚くほど多くの人々の理解を得ることになるでしょう。が、ここで私から一つの大切な事実を予言しておきます。必ずや現実となることを確信します。
すなわち、霊界から新しい啓示が届けられるに先立って、世界各地で恐ろしい戦乱が生じます。霊的視野を通して、霊界の同胞の存在を確信するには、前もって地上世界の浄化と清掃が必要なのです。完成へ向けての一過程として、敢えてそういう作用を必要とすることがあるのです。友よ、よくよく心されたい》
因果律の働きによって、どうしてもそうなるというのである。なぜかは人知では測り知ることはできない、否、高級霊でも知り得ないことがあるという。素晴らしい指導者に有能な後継者がいなかったり、せっかく立派な後継者に恵まれたと思ったら早世したり暗殺されたりするのも、その裏に、童話的単純発想のようには行かないカルマの絡み合いがあるようである。
そうした複雑なカルマの絡み合いの中での地上生活は、上流社会と下流社会、農業社会と工業社会、政治社会と経済社会とでは、表面的には大きな違いはあっても、霊性を磨くためのこやしとしての苦難という観点からすれば、本質的には同じである。
高級霊が、特殊な場合を除いて、平々凡々とした境涯に生をうけ、慎ましい人生を送る方を選ぶのはそのためである。見栄の張り合いや権力闘争などに明け暮れる人生の愚かさを悟っているのである。〝マイヤースの通信〟と呼ばれて親しまれている知的霊界通信の一つである Beyond Human Personality に次のような一節がある。
《偉大なる霊が全く無名の人生を送ることがよくある。ホンの一握りの人たちを除いて、その存在は世界一般にはほとんど知られることがない。したがってその一握りの人たちがこの世を去ってしまえば、後にはもう、その人が存在した痕跡は何ひとつ残らない。生き方一つではスーパーヒーローとして崇められたかもしれないほどの特性を秘めた、無私にして崇高なる努力の生涯を証言してくれる者は誰一人いない。
そういう高級霊が平凡な労務者、事務員、漁師、農夫といった身分に生をうけることがよくあるのである。その生涯は、これといって目立った活動は見られない。
にもかかわらず、その実、所属する類魂によって直接のインスピレーションを受けながら、霊性の偉大さと崇高性が発揮されている。イエスが〝あの世では先なるものが後になり、後なる者が先になること多し〟と言ったのはそのことである。》
・イエスに至る超高級霊の系譜
もとより、カルマの絡み合いの中にも自由意思の行使が許される範囲がある。環境条件の展開は一定のワクがあっても、そのワク内での意識的生活は背後霊団とのタテの関係であり、外部から拘束されることがないから、それは当然推測されることである。
もっとも、現段階の人類の大半は、その意識生活までもが物的次元に縛られ、ただ食べて働いて寝るだけの生活に終始してるといっても過言ではなかろう。スピリチュアリズムが主張している〝意識改革〟というのは、そうした物的次元での生活からの脱却である。
そこで、地球の支配階層の神々が合議を重ねた末に、適切な高級霊を地上へ送り込み、歴史の流れの大転換を計ることがあるという。その際、超高級霊みずからその任を買って出て、言わば捨て身の冒険的手段に出ることもあるらしい。
これをインペレーターは〝国籍離脱〟にも似た行為と述べている。その意味は、たとえ高級霊といえども、肉体という最も低次元の波動の物的身体に宿ることによって、先在、つまり霊界での自分の身の上についての記憶がシャットアウトされて、結果的には何もかも白紙の形で一から地上人生を始めることになる。
すべてが〝初体験〟となるわけである。したがって、中には本来の使命を忘れ、肉体の煩悩や世俗的欲望に負けて、取り返しのつかない過ちを犯してしまう危険性をはらんでいるということである。
さて、そうした高級霊の地上への降誕は、各時代の必要性に応じて、各民族において太古から連綿として行われているという。日本の歴史の中にそれと覚しき人材を探し求めるのも興味ある課題であろう。
それを指摘する〝霊示〟があればと思って幾つかの資料を検討してみたが、残念ながら低級霊による大言壮語としか断じようのないものばかりであった。願わくば私の灯台もと暗しで、私の知らないところで立派な霊示が届けられていてほしいものである。
そういうものとの出会いを楽しみにすることにして、少なくとも私が信頼している資料をもとに申せば、紀元前十二世紀ごろの人物であるメルキゼデクに始まってイエスに至る系譜が、地球史上最大の流れ、言わば霊的大河の主流だったようである。
メルキゼデクについては旧約聖書に〝いと高き神の祭司〟(創世記14・18) と出ているのみで、他に何一つ資料はない。たとえあっても果たして信が置けるかどうか疑問である。ひとつだけ確かなことは、その名のヘブル語 Malki-sedeq(英語綴りは Melchizedek)が〝わが王は正義なり〟を意味しているということで、〝正義の王〟として崇められていたことを窺わせる。
また新約聖書の 「へブル人への手紙」 の中でイエスのことを〝メルキゼデクに等しい大祭司〟(5・10) と称えているところをみると、よほど傑出した王であり祭司であったことが推察される。
さて、紀元前五世紀ごろの霊覚者であり、たぶん、私の推測ではその霊的系譜に属する高級霊の一人で、十九世紀末にステイントン・モーゼスという牧師の自動書記能力を利用して Spirit Teachings (日本語訳 『モーゼスの霊訓』 太陽出版)を送ってきた、
インペレーターと名乗る霊によると、そのメルキゼデクは死後、モーゼの背後霊団の支配霊として指導に当たったという。モーゼについては多言を要しないであろう。日本では〝十戒〟の映画でよく知られている。
インペレーターによると Moses という用語は元をたどればインドの大革命家であり説教者であった Manou からきており、それがエジプトで Manes となり、ギリシャへ渡って Minos となり、そしてヘブライ伝説で Moses となったという。 メルキゼデクと同じく固有名詞ではなく、一種の称号のようなものだった。
つまり〝人間〟Man を意味する普通名詞で、真理の開拓者を The Man と呼んだのである。現在でも最高に活躍した人物を The Man of the year と呼ぶのと同じである。
同じくインペレーターによると、〝モーゼ五書〟を始めとして、旧約聖書で語られている話は伝説や口承の寄せ集めに過ぎず、ほとんどが事実とは掛け離れているという。となるとモーゼという人物についてわれわれは、シナイ山頂で〝十戒〟を授かった霊能者で、それをもとに祭政一致の政治(マツリゴト)を行ったすぐれた人物、という程度の認識に止めておくのが無難のようである。
しかし、それほどのモーゼでさえ〝霊〟に関する理解は平凡な人間と同じく、物体身体をそなえた今の自分こそ実在で、霊を実在として実感するところまでは至っていなかったという。
お経を読み上げお布施をいただくだけの職業としての僧侶、祝詞を仰々しく奏上しお祓いをするだけで、神や霊、罪穢れについては、神道の書物の中の存在としてしか理解していない神官と同じ程度と思えばよいのであろうか。
が、そのモーゼも、死後は本来の霊格を取り戻して、後継者エリヤの指導霊として末永く後世へ影響を及ぼしたという、そしてそのエリヤの背後霊として指導に当たったという。
旧約聖書をたどってみると、二人について史実とも伝説とも判じがたい話がいくつも述べられている。が、ほぼ三千年も過ぎた今となっては、その事実性をうんぬんするよりも、むしろこの中でも明らかに伝説にすぎないと思われる幼稚な話をもって、二人の活躍ぶりと人望の大きさを物語るものと受け止めておく程度にしておくのが無難なのではなかろうか。
以上述べた高級霊の系譜は、主としてインペレーター霊による自動書記通信にそったものである。といっても、極めて断片的にしか述べられていないので、私の叙述も大ざっぱなものとなった。が、インペレーターも霊媒のモーゼスから 「メルキゼデクの前にも神の啓示をうけた者がいるか」 と問われて、こう答えている。
《無論である。われわれは最後にイエスに至る流れの最初の人物としてメルキゼデクを持ち出したにすぎない。その流れの中でさえ名をあげることを控えた人物が大勢いる。すでに述べたように、その多くが神の啓示を受けていた。エノクがその一人であった。彼は霊覚の鋭い人物であった。同じくノアがその一人であった。
もっとも、霊覚は十分ではなかった。デボラも霊覚の鋭い人物であり、歴史の中で〝イスラエルの土師(ハジ)〟と呼ばれている行政官はすべて、霊感の所有者であるという特殊な資格をもって選ばれたのであった。
そのことについて詳しく述べる余裕はない。ユダヤの歴史に見られるその他の霊力の現われについては、こののち述べることもあろう。今は、まずその古い記録全般に視点を置き、さらにその中の霊的な流れの中からイエスにつながる系譜一つに絞っていることを承知されたい。》
そうした〝事実〟や〝真実〟を人間に明かすか明かさないか、またいつ明かすかは、人間の理解の届かない霊的な事情があってのことのようである。それを暗示しているものが、同じ自動書記通信 Spirit Teachings に出ている。インペレーターの輩下での霊が、キリスト教会による記念行事───クリスマス・レント・イースター・グッドフライデー・エピファニー・アセンション・ペンテコステ───についてその本来の意義を詳しく解説したあと、次のように述べているのである。
《以上がキリスト教徒の祝日に秘められた霊的な意味である。われわれの最高指揮者であられる霊(インペレーター)がキリスト教的独善主義の壁を打ち崩し、迷信に新たな光を当てて下さったお蔭で、われわれが今こうしてすべての行事に秘められた真理の芽を披露することを許されたのである。人間的誤謬が取り除かれれば、それだけ多くの神の真理が明かされるのである。》
第三章 地上時代のイエス
・バイブルの中のイエス
イエス・キリストについて一般の人々が抱いているイメージは、新約聖書の中で語られているものがその全てであるといっても過言ではないであろう。
処女マリアを母としてベツレヘムに生まれ、ヘロデ王による幼児虐殺の風聞を耳にした両親に連れられてエジプトへ逃れ、ナザレで幼少時代を過ごし、二十数年の空白ののちに、三十歳になって祖国に帰ってきて独自の真理を説いた。その説くところが当時の国教とも言うべきユダヤ教と対立するものであったために各地でユダヤ教の指導者と衝突し、論争となった。
が、イエスは同時に〝しるしと不思議〟つまり目を奪うような心霊現象を起こしたり重病人を奇跡的に治したりするために、ローマの圧政に苦しめられていたユダヤの民衆は、イエスこそわが民族の救世主だと信じるようになり、その人気は高まる一方だった。
その勢いをみて、このままでは自分たちの地位や名誉、そして生活の基盤までが失われるのではないかと危惧したユダヤ教会は、当時のローマの総督ピラトに訴え、それを聞きいれたピラトは、渋々、イエスの処刑を許した。かくしてイエスは、ゴルゴダの丘で十字架にはりつけにされた。
ところが、刑死後三日目に、その遺体が納められているはずの墓の石蓋が取り払われていて、遺体そのものも無くなっていた。しかも、そのすぐ後からイエスが次々と弟子たちの前に生前そのままの姿を現して、死後も生きている証を見せた。それがのちに〝復活〟の信仰を生み、イエスを信じた者は生身をもって昇天するとの信仰が生まれた。
・バイブルの〝外典〟ならびに〝偽典〟の存在
旧約聖書にも新約聖書にも〝外典〟とか〝偽典〟とされた文書がおびただしく存在する。旧約聖書の方はイエスと直接の関係はないので、ここでは除外することにして、そもそも新約聖書が今日のような二十七書によって構成されるに至ったのは四世紀末のことである。中心人物のイエスが処刑されてほぼ三百年も経っている。
その間、イエスの〝しるしと不思議〟にまつわる話がきわめて簡略な形で綴られたものが各地域にいくつも存在していた。数にして百種類、ギリシャ語、ラテン語、コプト語、アルメニヤ語などで書かれていた。
その記述には、当然、間違いもあれば誇大化されたものもあったであろう。書き写す際の間違いもあったであろう。
中には〝してはならない〟という否定文の否定語 (英語の not に相当するもの) が脱落してしまって〝しなさい〟になったものもあったらしい。そうしたおびただしい数の書を四世紀初頭にカイザリアのユーセビウスという司教が〝認可された書〟〝問題のある書〟〝異端の書〟の三種類に分類した。
その後いくつかの紆余曲折をへて、四世紀末に現在の二十七書が、〝本物〟とされたということになっている。ところが、その後発掘された資料によって、その内容に大幅な改ざんがなされたことが判明している。
西暦三二五年、小アジアのニケアにおいてローマ全土の司教による第一回宗教会議が三カ月余りにわたって開かれたが、時のローマ皇帝コンスタンチヌスの命令で、その会議の舞台裏で改ざん作業が進められていたらしい。
歴史上ではコンスタンチヌスはキリスト教を容認した寛大な皇帝として〝大帝〟(グレイト)と尊称されてるが、実際は、政策上の一手段として都合のいいキリスト教をでっち上げたにすぎなかったのである。
その事実を示唆する資料の一部をまとめた書物が一八八六年に出版されている。His-tory of the First Council of Nice by D. Dudley (第一回ニケア会議の真相) がそれで、私が入手したのが第七版であるところを見ると大変な反響があったはずであるが、なぜか日本では紹介されていない。
・〝歴史上最大の陰謀〟のあらまし
そのあらましはこうだった。帝政となってからのローマは、旧約聖書の 「ダニエル書」 の中でユダヤ人がローマ帝国は〝滅ぶべき第四の帝国〟と見なしていることから、ユダヤ人への偏見が根強く、とくに原始キリスト教徒のユダヤ人を徹底的に迫害している。
紀元三年の暴君ネロに始まった迫害は暴虐をきわめ、〝狂気の獣性〟以外にその根拠を見いだせないほどのものだった。が、その他の宗教にたいしては寛大で、コンスタンチヌスの治世下には、東洋のヒンズー教と西洋のドルイド教とが勢力を二分していた。
その二派が共に自分の宗教の神の方が絶対であることを主張するようになり、何かと争いが生じるようになった。ヒンズー教はクリシュナ神を、ドルイド教はヘサス神を立てて譲らず、コンスタンチヌスも手を焼くようになった。
それに対処するために、コンスタンチヌスはまず、クリシュナとヘサスとを相殿(アイドノ)として併立させるか、それともどちらかが譲って一つの神のもとに統一しては、という考えを提案した。いかにも宗教とか信仰に縁のない人間のご都合主義から出た安直な考えで、そんなもので両者が納得するはずはなかった。
そこでコンスタンチヌスが目をつけたのは、それまでの迫害つぐ迫害にもかかわらず根強くユダヤ人の間で受けつがれてきているイエスなる人物への信仰心だった。
そのイエスを神に祭り上げて、これをローマの国教とすることによって民意を収攪しようという考えを抱いた。その下心をもって三二五年五月にローマ全土の司教を小アジアの二ケアに招集したのである。
ローマ領とはいえ、そんな辺ぴな属国を開催地としたことにも、その本当の目的を悟られまいとする深謀があった。
表向きの目的はギリシャの神学者アリウスの説を討議することになっており、ほぼ三百名の司教が出席したことになっている。そして、イエスは神ではないとするアリウスの主張が退けられて、イエスを神とすることに満場一致で決して、ここにイエス・キリストなる架空の人物が誕生し、キリスト教がローマの国教として容認されたことになっている。
ところが、実際はそうではなかった。出席者は実に二千人前後にものぼっていた。そして、そのうちコンスタンチヌス派が三百名で、残りは全部アリウス派だった。したがって採決を取った時は当然コンスタンチヌスの望む、イエスを神とするキリスト教案は否決された。これにコンスタンチヌスは激怒した。
そしてアリウス派が提出した反対声明文を皇帝派の者がその場で破り棄てた。そのことで議場は混乱に陥った。が、数では到底勝てないと見たコンスタンチヌスはローマ兵を呼び入れて、アリウス派を強引に議場から連れ出し、全員の聖職権を剥奪し、アリウスを国外追放処分にした。
あとに残った三百名の皇帝派が改めて採決し、かくして〝満場一致〟でイエスを救い主とするキリスト教が誕生した。
その論拠とすべきバイブルも、世界各地の神話・伝説から都合のいいものを借用して、それらしく書き改めていった。そして、さらにその上に次々と人工の教義をこしらえていった。贖罪説、最後の審判説、等々。ある聖書学者はこうしたニケア会議での一連の出来事を〝歴史上最大の陰謀〟とまで呼んでいる。
その陰謀を、それから実に二百年後になって、アリウス説の後継者ユノミウスが嗅ぎつけた。
そしてその真相を公表し始めた。これに慌てたローマ教会は、当時すでに握っていた強大な権力で持って、その真相を記したユノミウスの全著作、さらには、そのユノミウスを告発しようとする動きに抵抗する者たちの著作まで、一片の痕跡も残らないまでに隠滅する工作に出た。そして一応その目的は成就され、真相は再び闇の中に葬られた。
が、真実が永遠に葬り去られることはない。西ローマ帝国の滅亡後、その遺跡の中から唖然とさせる黒い陰謀を暴く物証が、古代史家の手によって発掘された。その問題の会議に出席した司教たちが書き残した記録や、その後お互いに交し合った手紙の中に、その事実が述べられていたのである。
もとよりそれは各自が後で思い出して書き記したものなので、細かい点、たとえば出席者の数などは一八〇〇名というものや二〇〇〇名とする者まであって、必ずしも一致していない。が、さきに述べた会議の経緯そのものは紛れもない事実であることを証明するには十分であった。
ダドレーの著書は十四章から成り、コンスタンチヌスが会議を招集するに至った原因と目的、そして会議の経過と結果とを整然と叙述しながら、それを裏付ける証拠資料を〝脚注〟の形で紹介している。その脚注が全体のほぼ半分を占めるほど豊富である。
・霊界通信に見るイエスの実像
イエスと同時代の人物であるクレオパスは、今では地上と直接の交信ができないほどの高い波動の世界へ進化してしまったために、七人の〝書記〟を通して───七つのトランスで波動を変えながら───カミンズ女史の霊的能力を活用して、イエスの弟子たちの行状を生々しく伝えてきたものといわれている。
それを解説する〝序文〟は聖書学者や司教、神学博士、心霊研究家等、実に二十数名によって共同で執筆されたもので、霊界通信の検討はかくあるべきという見本のようなものである。
さてイエスに関するナゾの一つに、その幼少時代と修業時代がある。布教活動を開始するまでの三十年近くを一体どこでどう過ごしたかが、まったく空白なのである。あからさまに言えば、イエスの実在の人物とする確たる証拠は何一つないというのが本当のところらしい。聖書学者の中にはイエスを架空の人物と断定している人もいるほどである。
が、われわれスピリチュアリズムの資料に幅広く親しんできた者には、実際の記録と同じ、あるいはそれ以上に信頼のおける、霊界からの通信がある。『クレオパスの書』(日本語訳 『イエスの弟子達』 潮文社) もその一つである。バイブルの 「使徒行伝」と 「ロマ書」 の欠落部分を見事に埋める形になっているといわれている。
が、その後、イエスの少年時代と青年時代に関する通信も届けられている。文字どおり The Child-hood of Jesus と The Manhood of Jesus の二冊である。
その訳書が 『イエスの少年時代』『イエスの成年時代』のタイトルで潮文社から出版されている。訳者で元牧師の山本貞彰氏は 『イエスの少年時代』 の 〝訳者あとがき〟で次のように述べておられる。
《イエスの伝記というものは、正確な意味で何一つ存在しないといってよい。新約聖書の中の福音書は、元来イエスの受難物語 (十字架上の死と復活) に重点を置かれて書かれたものであるから、イエスの重要な背後をなす 「生いたち記」 が完全に欠落していることになる。
カミンズは、彼女の偉大なる霊能によって 「母マリアの背景」 と 「イエスの成育史」 いうもっとも重要な部分を提供してくれたのである。
聖書にまったく見られない人物や出来事をも加えながら、イエスの少年時代を中心に展開されている雄大なドラマは、読む者の魂をゆさぶり、救いに導く大切な霊的養分をふんだんに注入してくれる。多感な少年イエスが、あらゆる苦渋をなめさせられても、真の救いを求めて修行をつんでいく姿には、感涙相むせぶ場面が幾度もあり、読む者の魂を浄化してくれる不思議な力がこもっている。
さて、本書は一体なにを言わんとしているのであろうか。イエスは最初期待していた神殿(ユダヤ教)には救いが無いことを知らされた。
ユダヤ教を代表する大祭司アンナスは、ローマの金権政治の犬になっており、ユダヤ教のラビ(教師)は徹底した教条主義で、少なくともイエスにとっては腹黒い偽善者であり、稀に見る善人として登場する老パリサイ人シケムでさえ、神殿という建造物にしがみついている臆病者であった。
結局イエスは、組織としての宗教や儀式的教条主義に救いが無いことを見抜いて、名も無い異国の浮浪者ヘリを真の指導者と仰いで山野において修行を続け、遂にアラビヤの 「流浪の部族」、もとをたださば皮肉なことに脱ユダヤの人々に兄弟として迎えられるのであった。では一体何が救いであったのだろうか。
学者の高邁な哲理でもなく、組織伝統的宗教団体でもなく、・・・・・・それは賢明なる読者にお委せすることにしよう。》
そして 『イエスの成年時代』 の〝訳者あとがき〟で、それをこうまとめておられる。
《二年がかりでカミンズ女史のイエス伝を完訳できたことを嬉しく思う。上巻にあたる 『少年時代』 は、涙ぐみながら翻訳にあたり、今回の 『成年時代』 では、納得のできる解答が与えられた時に誰もが味わう理性的満足を得ながら進めてきた。やさしく言えば、「なるほど」 の連続であった。
もうひとつ、つっ込んで言わせてもらうならば、本書のイエスほど自然で、すなおに感じられる人物はいないということである。正統派が大事にしている新約聖書の中でのイエスは、実に不自然で不明な事柄が少なくない。どだい、数多くの断片をつぎはぎして作られたものであるから無理もないとは思うが、鮮明なイエス像が浮かんでこない。
まず第一に強調したいことは、今更言うまでもないことであるが、イエスの徹底した信仰と実践である。かれが絶対的に信頼していた神の本質は 「愛」 であるから、当然の帰結として人間性を無視する現象や、それを否定する状況を許すことはできなかった。
権力を笠に着たパリサイ人や律法学者がとった冷酷な態度や、自分さえよければという利己主義と闘い、あるいはまた、全く無防備なか弱い羊を餌食にしようとする狼とは、命がけでたたかうイエスであった。
この勇気はどこから生まれてきたのであろうか。神が愛であるということを心から信じていたからだと思う。彼は凶悪な泥棒の前や殺生の場面において、 「肉体を滅ぼす者をおそれてはいない」 と語り 「いつでもこの世を去る準備はできている」 とも語っている。
『神を心から信じている』 という極めて単純なキー・ワードに注目してもらいたい。「信仰」と「愛の実践」とは全くイコール (同等)なのである。
このような信仰の原点を見事に伝えてくれた本書のイエスに改めて惚れなおしているところである。この点を欠いている現代の教会については、今更ふれる必要もあるまい。死んでいるものを批判しても始まらないからである。
第二に考えさせられたことは、自分に与えられている使命を、長い時間をかけて追及していく真剣な態度である。
「もし私が預言者ならば ・・・・・・」というセリフが何度か語られている。心から愛していたアサフ (障害者)がローマ軍によって無残にも殺されてからのイエスは、ややニヒルになり、何もかも空しくなり、一旦は隠遁修道会として名高いエッセネ派の生活を始める。
それでも彼はそこで満足が得られず、隠者として一生を終わることに本来の使命を感ずることができなかった。言い換えれば〝召命感〟が得られなかったのである。
ついに彼は故郷のナザレに帰り、叔母のマリヤ・クローパスとの会話から電撃的な閃きを得るのであった。それからのイエスの態度は一変した。
神の愛の実践者として、非人間化による犠牲者たちを片っ端から救済し、非人間化を行使する権力者(体制)を徹底的に糾弾した。つまり目まぐるしい奇跡と論戦の連続であった。
人間には誰にでも使命が与えられている。イエスのような霊覚者でさえ、真剣に追及している姿に心うたれるものがある。イエスが使命に関して終始考えていたことは、本書によれば、二者択一であった。一つは、洗礼者ヨハネやエッセネ派の指導者からも強力に勧められた道、即ち隠遁生活である。
瞑想によって常に神と交わり、世俗と縁を断つことである。他の一つは、世俗の中に入り、人々の間で神の愛を実践することである。結局は、人間が本来あるべき道を選択したのである。彼の選択は、私たちに言い尽くせない勇気と目標を与えてくれたのである。
第三に、大変うれしく思ったことは、実践の原動力が何によって得られるかが明示されていることである。つまり神との合一のことである。イエスはこれなくしては前へ進まなかった。全く一人になって人けのない所に行き、霊的交わりをした。
その状態を何と表現しようが問題ではない。とにかく神と霊的に交わるのである。それによって莫大な霊力が与えられ、死人をも生き返らせる力となり、体制を論破するエネルギーとなる。その断片をアサフやヨハネがかいま見ている。このこと一つを取り上げてみただけでも、今の組織的宗教の欠陥が分かるというものである。
イエスは手で作った神殿を嫌った。組織宗教は豪華な建物を持ちたがる。イエスは腐敗しきった組織宗教の仰々しい儀式や意味不明の教義、そして豪華な祭服を糾弾した。
皮肉にも、今の教会はイエスが嫌ったものを全部揃えてしまったのである。本書のイエスがはっきり示していることは、『信仰は個人のもの』『宗教は実践』 ということである。信仰と組織は全くなじむものではないと思われる。
信仰が集団となって生きる道は、エッセネ派のような隠遁修道会であろうと考えている。イエスが愛に満ちた奇跡を行っているのを見て、当時の宗教的指導者は、言うことにことかいて、ベルゼブル (悪魔の頭目) の力をかりてやっているのだと言った。
あれから二千年たった今、再びイエスが現れたなら、今の教会の連中もパリサイ派と同じようなことを言ってイエスを非難するであろう。いみじくもシルバーバーチ霊が、この点を明快に指摘していることをご存知の読者もおられることであろう。》
シルバーバーチは〝今もしイエスが現れて教えを説いたら、まっ先に石を投げつけるのはキリスト教徒でしょう〟と言い、インペレーターも、〝今もしイエスが当時のありのままの教えを説いたならば、現代の知識人、博士、神学者、科学者と呼ばれる階層の者も、こぞってイエスを嫌い、あるいは迫害もしかねないであろう〟と述べている。
右の『イエスの成年時代』 の巻頭を飾らせていただいた私の一文 『求道者としての極限を生きた〝人の子〟イエスの実像』 の中で、私はあらましをこう述べた。
《本書のもつ意義については二つの視点があるように思う。一つは、従来のバイブルの記述を絶対としてそれのみに頼ってきたイエス像とその行跡を見直すという視点である。が、これについては山本氏が〝訳者あとがき〟でご専門の立場から述べておられるので駄弁は控えたい。
もう一つの視点は、そうした通信霊が述べているイエス像とその行跡との比較という視点である。キリスト教の専門家でない私は、どうしてもそこに視点を置いて読むところとなった。
私が〝三大霊訓〟と称している 『モーゼスの霊訓』、オーエンの 『ベールの彼方の生活』、そして 『シルバーバーチの霊訓』が申し合せたように強調していることは、〝スピリチュアリズム〟の名のもとに進められている現代の啓示と人類の霊的覚醒事業の中心的指導霊が、かつて地上で〝ナザレのイエス〟と呼ばれた人物だということである。
これをすぐに〝同一人物〟とするのは早計である。一個の高級霊が幾段階もの〝波長低下〟の操作の末に母マリアの胎内に宿り、誕生後それが肉体機能の発達とともに本来の霊的資質を発揮して、そこに人間性をそなえた〝ナザレのイエス〟という地上的人物像ができあがった。
その幼少時の〝生い立ちの記〟が前巻であり、いよいよ使命を自覚して当時のユダヤの既成宗教の誤りと、その既得権にあぐらをかいている霊職者の堕落ぶりを糾弾していく〝闘争の記〟が本巻である。
こうした救世主的人物の生い立ちや霊的悟りへの道程はとかく超人化され、凡人とはどこか違う扱いをされがちであるが、〝十字架の使者〟と名のる通信霊の叙述するイエスの生涯は、どこの誰にでもあるような、いや、それ以上に人間臭い俗世的喧騒に満ちており、また苦難の連続だった。兄弟間のいさかい、親の無理解、律法学者やパリサイ人による怒りと軽蔑、同郷の者による白眼視・・・・・・最後は〝浮浪者〟扱いにされるまでに至っている。
「イエスの成年時代はこのようにして孤独の体験から始まった。イエスは故郷の人々に心を傾けて天の宝を与えようとしたのであるが、彼らはそれを拒絶したのである」
という一文には、胸をしめつけられる思いがする。
しかし、イエスはそうしたものをすべて魂のこやしとして霊性を発揮していき、愚鈍で気の利かない平凡な少年から、威厳あたりを払う風格をそなえた青年へと成長していく。
そこには求道者としての極限を生き抜いた姿がほうふつとして蘇り、二千年後の今、こうした活字で読むだけでも、その意気込み、精神力、使命の忠誠心に圧倒される思いがする。シルバーバーチが、人間的産物である〝教義〟を棄ててイエスの生きざまそのものを模範とするようにならないかぎり、人類の霊的新生は望めない、と述べている言葉が思い出される。
そのイエスが、死後、物質的現象でその姿を弟子たちに見せて死後の存在を立証して見せたあと、地上的なほこりを払い落して本来の所属界へ帰っていった。そして〝私はまた戻ってくる〟の予言どおりに、今、人類浄化の大事業の総指揮者としてその霊的影響力を全世界に行使しつつある。
それが各種の霊界通信、奇跡的心霊治療、自由解放の運動となって現れているのである。》
スピリチュアリズムが基盤としている驚異的な心霊現象は、本質的にはイエスが見せたのと同じものだったのである。イエスはそのうち自分よりもっと大きなことをする時代が来ると予言しているが、クルックス博士の実験室内での物質化現象を見れば、間違いなくイエスが見せたものよりも大きかったであろう。
そうした現象をキリスト教では〝しるしと不思議〟signs and wonders と呼び、イエスは神の子だからこそ出来たのだと説くのであるが、そんな神懸かり的で曖昧なこじつけではなく、スピリチュアリズム的に明快な解釈を施してくれた人がいる。
G・M・エリオット氏である。英国国教会の司祭でありながら、心霊現象に関する豊かな知識と経験をもち、〝死後の存在〟の事実と〝霊的法則〟の存在の普及につとめた異色の宣教師だった。
当然のことながら保守的な教会組織から強い弾圧を受け、一時は説教を差し止められ、懲罰が課せられ、収入が断たれ、ついには破門されるという憂き目を経験した。
そもそもエリオット氏がスピリチュアリズムに関心を抱くようになったきっかけは、エリオット夫人に優れた霊的能力があったことである。その異常能力を見てエリオット氏は、これがバイブルに言う、〝しるしと不思議〟だと考えるようになり、夫人とともに他の霊媒による交霊会にも出席して、死後存続について確たる信念を持つようになった。
そうした体験を通してバイブルの中のイエスの言動をまったく新しい角度から理解するようになり、当時親交のあった〝フリート外の法王〟の異名をもつハンネン・スワッハーの強い要請を受けて、The Psychic Life of Jesus を出版した。それを山本貞彰氏が 『聖書(バイブル)の実像』 と題して訳しておられる。その〝訳者あとがき〟の中で山本氏はこう述べている。
《現代のクリスチャンの最大の欠陥は、〝イエスの死から昇天の過程〟が全然理解できていない点であろう。ここが人間として最も重要な〝知識〟なのである。
少しでも良心的な者なら、この過程の中に何かしら重要な秘密が隠されているのではないかと感じるはずでる。イエスは神だからそのくらいのことなら出来る、という程度の知識なのであれば情けない話である。この部分が分からないということは、失礼ではあるが、唯物主義者と何ら異なることはない。
本書の著者が情熱の限りを尽くして書き著していることは、イエスの復活と昇天にある。謙虚な読書なら、きっとこの部分を素直に受け止めることができるのではないかと思う。
あの多弁なパウロでさえ「死は変化にすぎない」と〝コリント人への第一の手紙〟のなかで力説している。従って、死から霊の存在に変化するときの具体的な知識がなければ、絶対にこの部分は分からないはずである。
すぐれた聖書学者なら、この部分が最もキリスト教にとって重要なところであるということを否定しない。しかし彼らも充分に理解できていないのが現状である。訳の解らない屁理屈を並べているからである。牧師の説教を聞けばすぐ分かる。聖書学者の二番煎じを聞かされるのがおちである。
霊的知識を持っていない学者や牧師が、どうして霊への変化の過程について語れるというのであろうか。この点に本書の著者がにがにがしい体験を味わっていることを書いている。「信仰とは、もはや神を信じ神の与えたもうた霊力を信じることではなくなった。
信仰とは教会の組織を信じ、人間が作った〝信仰箇条〟や聖職者・法王を信じることに変わってしまった」
本書を霊能者の立場から眺めてみることも有益であろう。心霊現象にまったく無関心な唯物主義者や、教団に属している信条クリスチャンとは、正反対な人々である。
心霊現象の知識がある人、霊的能力のある人というのは、えてして〝組織〟をつくりたがる傾向を持っている。組織は権力と金を生み出し、ついに教祖的存在となってしまう。著者が至るところで強調しているように、イエスは全く〝組織〟を作らなかった。霊覚者と言われる所以である。
現代流の表現を用いるならば、イエスは心霊治療家を養成し、不治の病人と言われた人々の救済に全力を尽くしたと言える。心霊治療に当たっていたスタッフ (弟子) の生活費は、当然のことながら、完治した人々からの成功報酬によって賄われていたのである。取り過ぎもせず、足らないということもなかった。
組織としての宗教が今日堂々と行っている〝定額献金〟とか、〝冠婚葬祭〟によって得られるお布施の類などは、当時影も形もなかった。イエスは、終始、〝宣教と治療〟に専念していたのである。
まして立派な建物や儀式などは、思いもよらないことであっただろう。もし仮に聖書の中に〝組織〟の匂いのする文章があるとすれば、完全に後世の改ざんである。
ある学者の研究によれば、聖書は、歴史上最大の〝詐欺的〟書物であるとさえ言われているのである。聖書の一字一句は神の御言葉であって、全く誤りのないものであると信じ切っている方には大変ショックなことではあろうが、教会の組織が生まれようとしていた四世紀の初期頃までは、イエスの実像が大がかりに変えられてしまったようである。
ガリレオの名句と言われていると言葉 「それでも地球は動く」 も伝記作家の創作であったらしい。原本が後世の人々の手によって様々に改変される例は無数にあるのである。何はともあれ、霊能をだしにして多額の寄付や寄進を要請し、けばけばしい大伽藍を建立してきた宗教組織とイエスとは全く無関係であることを強調しておきたい。
イエスが教えてくれた〝霊能〟とはそれを必要としている人々のためにひそか用いられていること、それによって真の神を知らせるチャンネルにしていたこと、であった。この点を明確にしておけば、現代においても単なる霊能者と真の霊覚者の違いがはっきりすると思う。》
第四章 イエスは十字架上で死んでいなかった?
イエスが十字架上ではりつけにされている姿───それは悲愴感と残酷性と崇高さを覚えさせずにはおかないものだが、あの時、実はイエスは十字架上で死んでおらず、奇跡的に生き返ってこっそりと国外へ逃亡したと聞かされると、どことなく複雑な気持ちになるのは私だけではなかろう。
しかもその逃亡先はローマだとするもの、インドだとするものほかに、この日本にきたとする説が根強く残っていることは、いったい何を物語るのであろうか。
逃亡先はともかくとして、イエスはあのまま死んでいなかったのではないかと想像させる何かが起きたはずで、それは一体何だったのかを考えるのも、一種のミステリーとして興味あることではないかと思うのである。
これからそのうちの三つの説を紹介するに当たってあらかじめ断っておきたいのは、仮にイエスがその後何年か生き延びていたことが事実だとしても、イエスという人物の存在にとって、それは実にささいなことだということである。それは、その後で述べる霊界でのイエスの本来の霊格と霊力のすごさを考えれば、容易に理解していただけることと思う。
(一)アッピア街道で大工として短い余生を送ったとする説
・愛犬プルートーを従えて
英国人の F・V・Reuter の著者 The Man From Afar (はるか彼方から来た人) によると、イエスは伝道活動の期間中ずっとプルートーという名の愛犬従えていて、そのプルートーが処刑直後に大きな意味を持つことになる。
即ちイエスをはりつけにした十字架が立てられた直後から一天にわかにかき曇り、稲妻が走り、大粒の雨が落ち始めた。慌てたローマ兵たちはイエスの息が絶えているかどうかを確かめるために、脇腹をやりで突いた。
すると鮮血が流れ落ちたが、イエスの体がピクリともしないので、もう死んでいるとみて十字架から引き下ろして、マントを被せた。折から雨が激しくなってきたので、番兵たちはイエスの遺体をそのままにしてその場を去った。
ふつうならジャッカル(野生の犬)が死体を食い荒らすところだったが、愛犬のプルートーが片時もそばからはなれず、烈しい雨も幸いして、ジャッカルも近づけなかった。
その夜は滝のような雨が降り続き、母親のマリアとマグダラのマリア、それに弟子のペテロとヨハネは、ラマタイスのヨセフの家でまんじりともしない悲しい夜を過ごした。そして雨が止むとすぐ、また暗いうちに遺体を確認しに出かけた。その日は安息日なので埋葬は行われないことを知ってのことだった。
刑場へ来てみると、二人の盗っ人は十字架にはりつけにされたままなのに、真ん中のイエスの姿が見当たらない。更に近づいてみると、何かを覆っているマントのすぐそばにうずくまっていた犬が起き上って激しく吠えた。
が、マリアの姿を見るとすぐに大人しくなった。そこでもしやと思ってマントをめくってみると、まさしくイエスの遺体だった。あたりを見ると、ジャッカルの群れが遠巻きにしている。
「危ないところだった。いっそのこと家へ連れて帰ろう」───大変な禁を犯すことになる行為ではあったが、そのときの事情ではそうせずにはいられなかった。そしてヨセフの家で棺に安置してその遺体を見つめているうちに、唇と頬が赤みを帯びてきて、やがてイエスは息を吹き返した。手のひらと足の甲のクギの跡もきれいにふさがっている。奇跡が起きた───みんなそう思った。
そう思うと、みんな、このままもう一度あの十字架にかけられるのは忍びなく思えた。ローマの統治下にあって、それは絶対に許されないことだった。もしも見つかったら、さらに重い刑罰が科せられ、かくまったものも同罪になる。が、それを恐れる気持ちはもうなかった。さっそく逃亡のための変装に取りかかった。
逃亡の途中で何度か芝居もどきのハラハラさせられる場面が展開するが、それは省略して、ローマの方角へ向けてイエスは、アッピア街道をただ一人落ちのびていった。
当然のことながら、体力は疲弊しきっていた。とくに一晩中豪雨に打たれて冷え切っていたために、すでに気管支炎を患っていた。が、ローマにほど近い村で大工の家を見つけて、雇ってくれるよう頼んだところ、その大工は老齢で一人暮らしだったせいもあって、喜んで雇ってくれた。やがてその大工が死に、イエスは一人でほそぼそと暮らし、四十歳余りで他界している。
・ペテロとの再会
その他界の少し前にペテロが、ローマからの帰り道で偶然そのイエスの家に水を貰いに立ち寄った時の話が、最後に語られている。
イエスは白いあごひげをたくわえていたので、ペテロは最初、それが主イエスであるとは気がつかなかった。が、イエスの方はペテロであると分かっていた。そして、できることなら気づかれないままであった方がいいと思っていた。しかし、
「少し休んでいかれては?」
という言葉を聞いて、その声の響きにペテロは、ふと、思いが昔に引き戻された。
その瞬間、すべてが蘇った。そして思わずひざまずこうとした。するとイエスはそれを制した。ペテロが、
「先生、これは夢では?」というと、
「夢ではない、ペテロ。私にはすぐ分かったが、気づかれなければ、そのままにしておこうと思ってたよ」
「先生、いったいこれはどういうことですか。わたしには何が何だかさっぱり分かりません」
こうして二人は一晩中語り明かした。イエスは時おり苦しそうにセキ込んだ。物を取りに行く時の足取りも危うかった。
翌朝、イエスはペテロとともに、一マイルほど同行し、いよいよ別れぎわにこう語ったという。
「ジャイルスはいずれ手記を書くといっていたが、この事実は知らないはずだから、会って真実を伝えてやってほしい。そしてマグダラのマリアには、私が死んだら、まっ先に声を聞かせるといってやってくれ。どこにいようと同じことだ。私の生命はもう長くないことは分かっている。呼吸が日に日に苦しくなってきた ・・・・・・」
そう言ってからペテロの頬に口づけをした。ペテロはアッピア街道を進みながら、何度も振り返ったが、そのたびにイエスは手を振っていた。そして、ついにそのイエスの姿も遠くかすんで見えなくなった。
この書はタイトルからして小説的であり、副題も A Flight into the Past as it might have been となっていて、言ってみれば〝こうではなかったかという一試論〟というかたちをとっている。いくつかの資料をもとに、著者の想像力を混えて書いたもののようである。
その中で浮き彫りにされているイエス像は、宗教家というよりは社会革命家といったイメージが強い。ストーリーは実に面白くて、私は三度も読み返している。
(二)インドで伝道と治療活動を続けたとする説
ドイツ人ジャーナリスト Holger Kersten の英語版の著者 Jesus Lived in India (イエスはインドで生きていた)によると、イエスの処刑は正午ごろに始まって、遺体が下ろされたのは三時頃だったという。
天変地異は起きていない。慣習どおりに遺体は布でくるまれて石棺に埋葬された。それから三日目にマリアたちが訪れると、その石蓋が取り払われていて、イエスの遺体は無くなっていた。
そこまではバイブルの話どおりであるが、実はイエスの遺体が埋葬されたその夜のうちに、エッセネ派の者たちが忍び込んで運び出したという。スリラーもどきのプロットが展開する。そしてその後の筋は〝外典〟の一つである 『トマス福音書』 ときわめてよく似ている点が興味ぶかい。
・エッセネ派との関わり合い
話を進める前に、イエスの遺体を運び出したとされるエッセネ派について、簡単に説明しておきたい。
今から半世紀ほど前の一九四七年に、アラブの遊牧民の一つであるベドウィン族の少年が死海に面した険しい岸壁で洞窟を見つけた。中に入ってみると細長い土製のつぼが数本ころがっていた。中のものを取り出してみると巻物が入っている。もしかしたら金になるかもしれないと思った少年は、それを持ち帰って古物商に売った。
それがさらに数人の商人を転々とするうちに、聖マルコ修道院の大主教 A・I・サミュエルの手に渡った。巻き物を一目見て大主教は、それが途方もなく貴重な資料であることを直感した。こうして俗にいう〝死海巻物〟正式には〝クムラン文書〟がキリスト教会を震撼させる大問題へ発展していった。
まずヨルダンの古物管理局のハーデングとフランスの聖書考古学院のドゥ・ヴォ―神父の指揮のもとに組織的な発掘作業が進められ、蒐集された膨大な数の遺物を、英米仏の専門家を中心に組織された国際的研究機関によって、復元と解読が行われた。
その結果判明したことは専門的すぎるので、ここですべてを列記するわけにはいかないが、その中にイエスの実像と直接結び付く発見として、
従来の認識ではユダヤ教はサドカイ派とパリサイ派によって二分されていたというのが通説だったが、実はもう一つエッセネ派と呼ばれる宗団があって、ちょうどイエスが活動したころに一つの集団生活圏を築いていて、イエスもどうやらそれに所属していたことがあるらしいという推測が、かなりの信憑性をもって語られるようになった。
エッセネ派の全体としての印象は〝男性的戒律〟の宗団である。禁欲を第一とし、肉欲を禁じ、財産はすべて共有、他人への親切、特に年長者・貧者・見知らぬ人への思いやりを説いた。奴隷制度を排斥したのもエッセネ派が最初と言われる。
学問的にはギリシャ哲学を重んじ、東洋の思想や教訓を積極的に取り入れていた。
こう並べてみると、一つ一つは実に結構なことのようであるが、それがいちいち型にはめられた行為であり、しかも最大の問題として、現在の常識で言う〝結婚〟は許さず、原則として養子を向かえることにし、唯一、子孫を絶やさないという目的のためにのみ性行為を許し、子供が生まれれば、そこで妻の籍を除外したという。
エッセネ派に関する文書の主な作者は三人で、その述べていることにいくつかの矛盾点があるが、それは時代の推移による戒律の変遷を物語っていると理解してもよいであろう。が、問題はこのエッセネ派とイエスとの関係である。
バイブルに出てくるイエスの教えの中にエッセネ派の教えときわめて類似したものが多く見られるところから、イエスもエッセネ派だったのではないかという推測がされているのであるが、右の〝女性蔑視〟と〝型にはまりすぎ〟の二点から考えて、イエスが居心地よく思ったとは考えられない。
現に、霊界通信 『イエスの成年時代』 でも、確かにイエスはエッセネ派に所属していたこと自体は事実であるが、ごく短期間だった。私の理解しているイエスは自主的判断力を重んじ、怖じけることのない積極的な生き方を奨励し、この世にありながら俗人となり下がらないための霊的自覚と節度を説いたのである。
その上イエスは、ケタ外れの霊的能力をそなえていた。言うなれば当時のスーパーヒーロー的存在だったと考えてよいであろう。だからこそ総督のピラトやユダヤ教の聖職者がイエスに対して嫉妬と恐怖を覚えたのだった。こうしたイエスの実像については、改めて取りあげることにして────
・ダマスカスにいったん身を隠す
処刑直後にイエスの遺体を持ち去ったのは、こうしたエッセネ派の一味で、多分イエスが所属していた時分にイエスとともに修行をし、イエスがただの人間でないことを見抜いていた、かつての同志たちだった。
イエスは、その運ばれて行く途中で覚醒する。そしていったんダマスカスに落着き、そこで追手の目を避けながら、体力の回復につとめた。
さて、ペルシャに伝えられる話によると、やがてそのイエスのもとにトルコのニシビスの王から病気治療の依頼が届けられた。が、体力の回復が十分でなかったからか、他に理由があったのか定かではないが、取りあえず弟子のトマスを行かせて、自分も必ず後からいくという手紙を持たせたという。が、約束通りイエスが訪れた時は、王の病はトマスによって癒されていたという。
ニシビスを出てから北西への旅に出て、最後にインド北部のスリナガルで死亡するまで、イエスはいくつかの名前を使い分けながら、霊的真理の伝道と病気治療を行っているが、その根拠は、四世紀にシリアで書かれたといわれる〝外典〟の一つ 『トマス行伝』 と 『トマス福音書』 である。
イエスと最後まで共にしたのはこのトマスで、ほかに母親のマリアとその妹、それにマグダラのマリアの三人で、マリアの妹は、すでに紹介した霊界通信 『クレオパスの書』 のクレオパスの妻だったという。
・イエスとマリアの墓
著者のドイツ人ジャーナリストはトマスの二つの書を克明に実地検証し、母マリアの墓(パキスタンのマリ) とイエスの墓の存在を確認して、その写真まで掲載している。最後にイエスが名のった名前は ユズ・アサフ Yuzu Asaf でスリナガルの中心地にあるロザバル Rozabal という建造物の中に葬られているという。
ロザバルというのは〝予言者の墓〟という意味で、それがイエスであることの絶対的証拠として、考古学者がその墓を調査したところ、墓石に〝足型〟が彫ってあり、その甲のところに、はりつけの時のクギ穴と思われる大きな傷痕があることを発見した事実をあげている。
その傷跡の様子から判断して、イエスは左足を右足の上に重ねて撃ち抜かれた、ということまで記している。インドにははりつけの刑がないことも、これをイエスであるとする根拠の一つにあげている。年齢は記してないが、ストーリーをたどったかぎりでは、かなりの高齢だったことは間違いない。
(三)〝目撃者〟と称するエッセネ派の長老の手記
二十世紀になって間もないころ、古代史跡研究家のエルシー・モリス博士 Elsie L. Morris がロサンゼルスにある図書館で古代イスラエルに関する資料を書写しているうちに〝エルサレムのエッセネ派の長老がアレキサンドリアの同志へ宛てた手紙〟と言うのが目に止まった。
一読してその重大さに気づいた博士は、慎重に書き写してから、出版社を経営している B・F・オースチン氏のところへ持ち込んだ。そのオースチン氏も一読してただならぬ内容に感動し、内容の解読とエッセネ派についてに一文、それにバイブルによる通説を添えて、 The Crucifixion of Jesus by an Eye-witness というタイトルで一九一九年に出版した。
私が入手したのはその復刻版である。Eye-witness というのは目撃者または生き証人ということで、書簡のタイトルの意味は〝目撃者が語るイエスのはりつけ〟ということになるが、目撃者の実名は記されていない。
現物はラテン語で書かれていて、それがドイツに持ち込まれてドイツ語に翻訳され、さらにスウェーデンに持ち込まれてスウェーデン語に訳され、そして右の書の出版のために三人の翻訳家によって英語に翻訳されている。
それによると、これ又、前の二つの説とはガラリと筋書きが違う。(一)ではイエスとエッセネ派との関わり合いは一言も述べられていない。徹底した革命家で、ローマの圧政からユダヤ民族を救うために民衆を煽動し、ひそかに武器まで用意している。親にも兄弟にも孝行している。
バイブルに出てくる〝しるしと不思議〟がなるほどと思わせる場面で出てきて、小説を読むように面白い。といって、決して芝居じみてもいない。そしていよいよ革命が実行される直前になって例のユダの裏切りがあって謀反は挫折し、イエスは逮捕されてゴルゴダの丘で (いったん) 処刑される。が、紹介した通りのいきさつで覚醒してアッピア街道を逃げ のび、そこで生涯を閉じる。
最初から最後まで〝これぞまさしく救世主(メシア)だ〟と思わせるほどの霊力と人格力をそなえた人間として描かれていて、エッセネ派との関わり合いは一切出てこない。
これが (二)になると、直接の関わり合いは述べられていないが、処刑直後にエッセネ派の一味がひそかに遺体を持ち去っている。そしてその後も陰に陽に援助している。が、行動を共にしたのは母マリアとその妹、マグダラのマリア、それに弟子のトマスで、このストーリーの中ではトマスはイエスの本質を最も深く理解した人物とされており、『トマス行伝』 では〝キリストの双子の弟〟という言い方までされている。そして二人して処刑前と同じように数々の〝しるしと不思議〟を行い、難病を癒している。
著者は、イエスをほうふつさせる人物がインド各地に逗留した事実を証拠づける遺物や遺跡を紹介している。たとえばデリーの南一七五キロにある、今では廃墟となっている古代都市の寺院の一つの巨大なアーチ門に、
「イエス曰く〝この世は橋である。渡るのはよいが、そこに安住してはならない〟と」
という刻文があるという。
信頼できる霊界通信、たとえばシルバーバーチの霊言では、イエスは若き日にインドで修行していると述べているところから考えて、そうした遺物はもしかしたらその修行時代のものかもしれないという推測も成り立つ。が、ともかく著者は、インドでマホメット教が猛威をふるうようになる以前に、イエスの教えが広まっていたことは間違いないとしている。
・イエスもバプテスマのヨハネもエッセネ派に属していた
このように、(一) は小説作法的であり、(二) は考証学的である。がこれから紹介するのは〝私はその場でこの目で見たのです〟と言う人物が、同じエッセネ派の同志へ宛てて書いたもので、その中でのイエスは熱心で有能なエッセネ派の修行者ということになっている。しかもパブテスマのヨハネ、すなわちイエスに洗礼を施したヨハネもエッセネ派の長老で、あの洗礼はエッセネ派への入門を許す儀式だったのだという。
さて、この〝目撃者〟はイエスが十字架を担がされてよろめきながらゴルゴダの丘を歩いていく様子、それを見て女性たちが大声をあげて泣き叫ぶ様子、一方パリサイ人たちが遠巻きにしてあざけ笑っている様子などを克明に描写している。
そのあと、いよいよ十字架に両手足を縛りつけられてクギを打ち込まれるのであるが、面白いことに、この目撃者が言うには、クギは両手に打ち込まれただけで、足には打ち込まれなかったというのである。
「同志諸君、私はこの点を特筆しておきたい。風聞(ウワサ)では両手両足に打ち込まれたとされているからである」
と述べて、足にクギを打ち込むのはローマのはりつけの慣習ではないと念を押している。
・大地震が二度起きる
(一) ではそのあと雷鳴とともに大洪水となるが、この目撃者が言うには、太陽が沈んでから大地震が二度発生したという。そしてローマ兵たちは、これはもしかしたら、やはりイエスは神の子で、それを処刑した天罰ではなかろうか、と不安になった。
そんな時にバイブルでも登場するアリマタヤのヨセフとニコデモが現場に到着する。
そして、まさかこんなに早く処刑が執行されるとは、と、師の最期に間に合わなかったことを嘆き悲しむ。しかし、この二人がイエスの蘇生に大きな意味を持つことになる。ヨセフが金持ちだったことと、ニコデモが医学にも通じた教養人だったことがその要因である。
二人は十字架上でうなだれて息絶えているイエスを見て、せめてこのあとローマ兵によって(当時の慣習で)手と脚を打ち砕かれることだけは免れさせてあげたいと思い、総督ピラトを買収してその許しを得ようと、ヨセフが走って行った。ピラトはよくそうやって金をとって許していたという。が、実際にそのことを頼んだ時は、ピラトは地震による恐怖におののき、自分がイエスの処刑を許したことを悔いていて、金は取らずにヨセフの頼みを聞いてやったという。
ヨセフがそのことで奔走している間に、ローマの百人隊長がイエスの骨を砕きにやってきた。が、幸いこの目撃者はこの隊長と顔見知りだったので、イエスはもう間違いなく死んでいるから、そこまでやらないでほしいと頼んだ。その頼みは受け入れられたが、そこへピラトの使いの者がやってきて、隊長に、イエスは間違いなく死んだか、と尋ねた。
「確かに死んでいる。だから骨は砕かなくてもよい」 と言うと、 「では確かめさせてもらう」 というなり、ヤリでイエスのヒップのところを突き刺した。すると血と体液が流れ出たが、イエスの身体がピクリともしないのを見て、その使いの者は納得して去っていった。
その様子を見ていたニコデモは、本当に死んでいればあんなに出血はしないはずなのに、おまけに体液まで流れ出たのは、イエスがまだ完全には死んでいない証拠と見た。そこで、戻ってきたヨセフと〝私〟に小さな声で 「先生はまだ生きていらっしゃる。体力を消耗しているだけだ。さっき、こういう時によく効く薬草を取ってきてある」と言った。
三人は早速十字架にのぼり、縄をほどき、両手のクギを抜いて、ゆっくりと地面に下して横たえた。そこでニコデモが大急ぎでイエスの体全体に薬味と膏薬を塗りつけた。さらにその上から白い布でぐるぐる巻きにして、埋葬場所である洞窟の中へ運び込んだ。そして、その入り口を大きな石で塞いでおいて、中でアロエなどの薬草をいぶした。
それがよく効いて、ニコデモが予測したとおり、イエスは蘇生する。そして逃亡という筋書きになるのであるが、その目撃者の話では、イエスは意識は取り戻したものの、体力の消耗が激しくて、エッセネ派の者にかくまわれながら各地を転々とするうちに、ついに生命が尽き果て、処刑後六カ月ほどで死亡したという。そしてその遺体は死海のほとりに埋葬されたという。
(四)その他の諸説
以上、私は手元に原典があるものだけを選んで紹介したが、実際には、他にもいくつかの説がある。多分ご存知の方も多いと思われるものに、イエスは日本に渡来して青森県の戸来村で百十八歳で死んでいるとする説もある。
これは、〝竹内文書〟(タケノウチモンジョ)と呼ばれる日本の古史古伝の中の〝外典〟または〝偽典〟とされているものの中の一つに述べられている説で、その根底にはユダヤと日本が同一民族である───正確に言えば、二五〇〇年前にユダヤの一支族が流浪の旅の末に日本列島に住みついたとする説から出ている。
参考までにあらましを紹介しておくと、イエスは双子の兄弟の兄で、弟はイスキリといい、それが身代わりとなって十字架上で死に、イエスは長い逃亡の旅の末に日本にたどりついたという。
イエスが双子であったというのが事実かどうかは問わないとしても、私がまったくおかしいと思うのは、イエスがこれ程までに騒がれるのは〝これぞ救世主か〟と騒がれるほどの人物だったからこそで、それが弟を身代わりにしておいて逃亡し、最後は日本にきて片田舎でひっそりと余生を送ったことが、さも日本にとって意味ありげに扱われていることである。本当かウソかの問題以前の、どうでもいい話ではなかろうか。
そのほかにも、イエスは逃亡中にマグダラのマリアとの間に子供をもうけたという〝下衆の勘ぐり〟ていどのものもある。
右のアレキサンドリアの〝目撃者〟もエルサレムとパレスチナで起きたイエスの処刑前後の事実に羽根が生え尾ひれがついて、とんでもない話に発展していくのを放置しておくに忍びず、その真実を書き残しておきたいと思ったというのである。と言って、私はこの目撃者と称するエッセネ派長老の話が事実であると断定しているわけではない。
事実の誤認はあるにしても、先に紹介した三つがそれなりに筋道が通っており、そうだったかも知れないと思わせるものを備えている。
が、互いに突き合わせてみると、たとえば (二) ではイエスの墓とされるものの石板に足型が彫られていて、それにはちゃんと処刑の時のクギの穴まで彫られているのに、 (三) の長老の話では、当時のローマの慣習として、はりつけの時は両手にしかクギを打ち込まない───足にも打ち込まれたという話が伝わっているようだが、それは断じて事実に反する。とまで言っていて、完全に矛盾している。
また、(一)では処刑の時刻ごろから雷鳴をともなった大雨となり、それがイエスを救うきっかけとなるのであるが、 (三)では大地震が二度も起きて、それがイエスが助かるきっかけとなっている。一体どっちが本当なのだろうか。
いずれにせよ、こうしたことが話題となるのは、〝死ぬ〟ということへの人間のこだわりが強いからではなかろうか。実際には自我にも個性にも〝死〟はないのである。
凡人が死を悲劇と受け止めるのは人情として当然のことであろうが、イエスほどの超高級霊ともなると、その使命は生死を超越している。次章でそのことを見てみたい。
付記───平成三年五月十三日付けの朝日新聞に 「キリストの復活は失神後の意識回復」 と題する、次のような記事が出ている。
「キリストの復活は失神後の意識回復」
十字架上で受刑のため死亡、二日後に復活したことになっているイエス・キリストは死後復活したのではなく、気を失った後に、意識を回復した可能性が高い───との新説を英国の医学博士がロンドンの王立医大学内誌に発表した。
定説への挑戦者は英雇用省の医学顧問を務めたこともある元医師の トレバー・ロイド・デービス氏(八二)夫妻。
二人は、 一、キリストは十字架上でショック状態となって血圧が下降、意識を失った、
二、キリストが血の気を失い、動かなくなったため、そばにいたものが死んだと間違えたことは疑いない────と主張。
その根拠の一つとして二人は、十字架上での受刑死が通常三、四日かかるのに、キリストはわずか六時間後に死亡したとされていると指摘している。
(共同)
第五章 霊界へ戻ってからのイエス
・人間的努力と霊の援助
以上、私は超高級霊の降誕の最後を飾る人物としてイエスの実像に、いくつかの角度から光を当ててみた。
読者の中には、真実性を証明する証拠のない、しかも明らかに矛盾する説をなぜ紹介するのかという疑問を抱かれる方もいらっしゃるであろう。
が、その辺に私の霊界通信の受け止め方の違いがあることを知っていただきたい。私はこれまで〝三大霊訓〟と言われる英国の霊界通信ばかりを翻訳してきた。年代順に言えば 『モーゼスの霊訓』 が全三巻 (国書刊行会の文語体訳 『霊訓』 全一巻は絶版)、 『ベールの彼方の生活』 が全四巻、 そして 『シルバーバーチの霊訓』 が第一期十二巻と第二期三巻 (〝愛のシリーズ〟)、第三期三巻(翻訳中) を併せて二十五冊にもなる。
が、このことをもって私が霊界通信に夢中になっている人間のように想像されては困るのである。
たしかに二十五冊というのは冊数としては多いかもしれないが、その霊的淵源は、かつて地上で〝ナザレのイエス〟と呼ばれた人物を中心とする地球浄化のための大霊団であって、その中の〝霊的真理の啓示〟を担当する三つの霊団から届けられたものなのである。同じ始源からのものが三人の霊媒を通して届けられたということである。
地上におけるスピリチュアリズムを一応十九世紀半ばからとして計算して、以来百五十年間に、日本のものも含めて〝啓示〟と呼ばれるもので私が入手できたかぎりのものを渉猟(ショウリョウ)してきて〝これこそは〟と確認できたもの、つまり純正かつ高等な本格的霊界通信 (計画性をもったもの) と言えるものは、その三つしかないという結論に達したのも、当然といえば至極当然の結果だったと言えるであろう。
その判断方法はいろいろあるが、基本的には、全体として矛盾撞着がないこと、そして、ベストセラーにはならなくてもロングセラーを続けていること (順に、およそ一二〇年、七五年、六五年) といったことがあげられるが、そういうものとは別に読む者の魂の琴線に触れるものを持っていることが最大の特質と言えよう。
逆の見方をすれば、そんなことはわざわざ霊から聞かされなくても、人間の知恵で十分に間に合いますと言いたくなるような内容のことを勿体ぶってのたまっているものは、まずもって高級霊からのものではないということである。
ある一定レベル以上の高級霊ともなると、地上世界を経綸している地球神庁の計画と意図をよく理解した上で行動するので、人間の努力の範囲に属することに干渉することは絶対にしないものである。シルバーバーチの霊言の中に、その点をはっきりと述べている一節がある。
《霊界から手を差しのべてよい範囲があり、出しゃばってはならない限界があり、しゃっべてはならない時があり、今こそ述べるべき時があり、それに加えて、その時々の環境条件による制約があります。
しかし、そのパターンは厳然としており、指導に当たるスピリットはすべからくそのパターンに従わなくてはなりません。前もってそういう取り決めがしてあるからです。
私も、私よりはるかに霊格の高い霊団によって計画された枠の外に出ることは許されません。そもそも地上で成就すべきものと判断を下した、もしくは計画したのは、その高級霊団だからです。光り輝く存在、高等審議会、神庁、天使団───どうお呼びになっても結構です。要するに私たちが行う全仕事について進化せる高級霊の集団です。
私には、もうすぐその方たちとお会いする喜びが待ち受けております。その時、まず私の方からそれまでの成果をご報告申し上げ、次に私がどの程度まで成功し、どの点で失敗しているかについて言い渡され、それによってそれから先の私のなすべきことを判断することになるのです。
その霊団の上にはさらに高級な霊団が控え、その上にもまたさらに高級な霊団が控えており、連綿として事実上無限につながっているのです。》
また別のところで、出席者から 「イエスは本当にはりつけにされたのでしょうか」 という質問を受けてシルバーバーチは、
「そんなことについて私の意見をご所望ですか。そんなことはどうでもいいことではないでしょうか」
といって返答を避け、そんなことを知っても霊的進化には何のプラスにもならないと諌めている。
常識的に考えれば、もしも処刑されたのが事実ならば、「そうです」 と答えるだけで済むはずである。バイブルではそういうことになっているのである。それを、なぜか返答せずに、そんなことを知っても魂の成長のプラスにはならないなどと言うところを見ると、どうやら十字架上では死んでいなかったのではないかという推測をしたくなる。
が、多分、右の引用文をにある通り、その問題に深入りするのはシルバーバーチの領分ではなかったのであろう。
こうしたシルバーバーチの態度は、人間的努力と霊による援助との兼ね合いについて非常に大切なことを教えてくれているように思う。守護霊を中心とする背後霊団と人間との関係、あるいは一国の守護神と国民との関係、さらには地球の守護神と地上人類全体との関係の基本にあるのは、あくまでも人間の霊的進化であり、そのために絶対条件として、自由意思の尊重が第一に考慮されねばならない。
ただの操り人形となってしまっては、安全第一は保証されても、そこに進化はありえない。そこで人間側の自由意思による判断と選択の権利を尊重しつつ、カルマの解消と霊的進化へ向けて霊的援助を与えてやらねばならない。
何でも簡単に解決してやっていては、それは例えば子供の宿題をぜんぶ親が教えてやるようなもので、本人のためにならないどころか、逆にマイナスの素地を作って行くことになるであろう。
イエスの処刑後の真相についても、やはり人間の努力によって少しずつ解明していくべきであるというのが私の考えであり、また、いつかは必ず解明されるものと信じている。第一回ニケア会議の真相が十数世紀のちに解明されたように、イエスの死の真実を物語る資料もいつかはきっと発見されるであろう。
私が互いに食い違う説をあえて紹介したのも、今の段階では私の独断は控えるべきであるとの考えから発している。そうやって幾つもの説を検討していく作業の過程で得られるものからいろいろと教えられる。それが人間としての正しい有り方だと思うのである。
・人類の地上降誕の目的
霊の世界から物質の世界への誕生にはいくつかのタイプがある。鉱物・植物・動物として顕現してきた霊が、いよいよ自我意識をもって人間的身体を通して顕現できる段階まで進化した、言うなれば人間学校の新入生がその一つ。原始的生活を送っている人種に多く誕生しているとみてよいであろう。
また、同じ再生でも、みずから求めて、一つの願望をたずさえてやってくる場合と、カルマの解消のために強制的に生まれ変わらされることもあるらしい。と言っても実際には摂理の働きによる一定の制約があり、その摂理の背後には〝向上進化〟という至上目的のための〝愛の配慮〟があると考えるべきであろう。
さらには、かなりの霊格を身につけた高級霊が、霊力の不足を自覚して、その補強のために厳しい生活環境の中に生を受けることもある。霊格が高いからといって必ずしも霊力が強いとは限らない。厳しい環境と言ってもいろいろと考えられるが、世間から軽蔑されるような身の上であることもある。
その場合、脳を通じてその意識ではそうした身の上を嘆き世を怨むが、本当はみずから求めたものなのである。イエスが、霊界へ行けば地上で上だった者が下になり、下だった者が上になることがよくある、といった意味のことを言っているのはそのことであって、現在の身の上だけで霊格をうんぬんしてはならないという戒めである。
さて、では一体イエスはいかなる目的をもって地上に生をうけたのであろうか。それに答えるには、〝ナザレの大工の息子〟として地上に生をうけた人物の先在 (誕生前の霊としての実像) は何だったのかについて述べておかねばならない。この問題になると、もはや人間的努力の範囲を超えて、信頼のおける霊界通信から霊的直観力によって読み取るほかはない。
・イエスとキリスト教とは無関係
私が〝イエス・キリスト〟という名前を知ったのは、高校三年の時に モーゼスの 『霊訓』 を浅野和三郎の抄訳で読んだ時であるが、そのときはキリスト教との関連におけるイエスという人物については何の認識もなかった。
それから間もなく明治学院大学の英文科へ進学することになるが、その大学を選んだのは当時の日本の大学で英米人教師がいちばん多いからという、きわめて単純な理由からで、そこがプロテスタント系のキリスト教のミッション校であることなど、まるで知らなかった。
だから、一年次から必修科目としての 「キリスト教概論」 の授業に出席したときは、世の中にこんなバカバカしいことを熱心に信じている人がいるのかと不思議に思ったことを覚えている。〝三位一体説〟や〝贖罪説〟を説き聞かされても、キリスト神だの聖霊だの原罪だのについて何の概念も抱いたことのない私には、それを知って一体どうなるのだ、と胸の中で反発を覚えたものである。
が、そのことが、モーゼスの 『霊訓』 の原書 Spirit Teachings を初めから読み通すきっかけともなった。ご承知の方も多いと思うが、著者のモーゼスは元牧師で、オックスフォード大学の神学部に学んだ秀才であり、将来を嘱望された人材だったが、三十歳ごろからの霊的能力が発現し、身近にかずかずの物理的現象が起きるようになった。
そのうち、ふと〝書きたい〟衝動を覚えるようになり、紙と鉛筆を用意すると、自分の頭の中にあるものとは無関係のことが自動的に綴られるようになった。
初めのうちは内容的にどうということもなかったので気にもかけなかったが、そのうちキリスト教の根幹にかかわる問題について、モーゼスの信仰と正面衝突する内容のものが綴られるようになり、それに反発を覚えたモーゼスが 「一体あなたは何者なのか」 という問いを綴ると、「新しい啓示を届けに参った霊団の指揮者である」 と答え、 Imperator Servus Dei (神の僕インペレーター) と署名し、その頭に十字(クロス)を冠した。
そこでモーゼスが、キリスト教の専売である十字を冠しながらその説くところがオーソドックスなキリスト教と違うのはどういうわけかと尋ねた。それに答えてインペレーターがキリスト教の間違いをこう綴った。
《友よ、主イエス・キリストの教えとして今地上に流布しているものには、主の生涯と使命を表象するあの十字架にふさわしからぬものが少なからずあるという事実をまず述べておきたい。各派の狂信家は、字句にのみこだわって意味をおろそかにする傾向がある。
執筆者一人ひとりの用語に拘泥し、その教えの全体の流れをおろそかにしてきた。真理の探究と言いつつも、実はあらかじめ説を立て、それをこじつけて真理と銘うっているにすぎない。
そなたたちの言う聖なる書(バイブル)の解説者をもって任ずる者が、その中から断片的な用語や文句を引用して勝手な解説を施すために、いつしかその執筆者の意図しない意味をもつに至っている。
又ある者は、いささかの真理探究心もなしに、ただ自説をたてるためにのみバイブルから用語や表現の特異性をいじくりまわすことに喜悦を覚える者、自説を立てそれをこじつけることをもって良しとする者たちによって、一つの体系が作り上げられていく。いずれもバイブルというテキストから一歩も踏み出せないことになる。》
《正統派のキリスト者たちは、一人の神秘的人物───三位一体を構成する一人が、一握りの人間の心を捉え、彼らを通じて真理の全てを地上にもたらしたと説く。それが全真理であり、完全であり、永遠なる力を有するという。神の教えの全体系がそこにあり、一言一句たりとも削ることを許されず、一言一句たりとも付け加えることも許されない。
神が語った言葉そのものであり、神の御心と意志の直接の表現であり、顕在的にも潜在的にも全真理がその語句と言い回しの中に収められているという。》
《かくして単なる用語と表現の上に、かの驚くべき教義と途方もない結論が打ち出されることになる。無理もないことかもしれない。彼らにとっては、その一言一句が人間的謬見(ビュウケン)に侵されていない聖なる啓示だからである。
しかるに、その実彼らのしていることは、おのれに都合のよい文句のみを引用し、不都合なところは無視して勝手なドグマを打ち立てているにすぎない。》
《同じことがすべての教派についても言えよう。各派がそれぞれの理想を打ち立て、それを立証するためにバイブルから都合のよい箇所のみを抜き出す。もとよりバイブルの全てをそのまま受け入れることのできる者は皆無である。
何となれば、全てが同質のものとは言えぬからである。各自が己の主観にとって都合のよい箇所だけを取り出し、それを適当に組み合わせ、それをもって〝啓示〟と称する。他の箇所を抜き出した者の〝啓示〟と対照してみる時、そこに用語の曲解、原文の解説 (と彼らは言うが) と注釈、平易な意味の曖昧化がなされ、通信霊も説教者も意図していない意味に解釈されていることが明らかとなる。
かくして折角のインスピレーションが一教派のドグマのための方便と化し、バイブルはお好みの武器をとり出す重宝な兵器庫とされ、かくして神学は、誤った手前勝手な解釈によって都合よく裏づけされた、個人的見解となり果てたのである。
そなたは、こうして組み立てられた独りよがりの神学に照らして、われわれの説くところがそれと異なると非難する。
確かに異なるであろう。われわれはそのような神学とは一切無縁なのである。それはあくまでも地上の神学であり、俗世のものである。その神の観念は卑俗かつ低俗である。魂を堕落させ、神の啓示を標榜しつつ、その実、神を冒瀆している。そのような神学とは、われわれは何のかかわりも持たぬ。
矛盾するのは至極当然のことであり、むしろ、こちらより関わり合いを拒否する。その歪んだ教えを修正し、代って神と聖霊について、より真実の、より高尚な見解を述べることこそ、われわれの使命なのである。》
これでお分かりの通り、イエスはその後発生したキリスト教とは何の関係もないのである。そもそも〝キリスト教〟などという言葉はイエスの口から出たことは一度もなかったし、組織とか集団を作ったこともない。各地で霊的真理を説き、たぶん人生相談にものり、不治の病で苦しんでいる人々を癒して回っただけである。
・教会の原型は交霊会だった
インペレーターという霊は、その後の通信で紀元前五世紀ごろに地上で活躍した霊能者であることが分かっているが、それよりさらに古い紀元前十世紀ごろ、つまりイエスより一千年も前に地上で生活したことがあるというシルバーバーチもキリスト教のドグマを〝人類にとっての呪い〟と極言するほどその害毒の深刻さを指摘している。
それは、三千年という長い歳月を地上と霊界で生きてきた者の目から見て、そうしたドグマを信じながら死んで霊界入りした者たちのその後の向上進化にとって、それが測り知れない障害となっている事実をつぶさに見て来ていることが主な理由であるが、もう一つ、このあとで扱う歴史に名高い〝暗黒時代〟が、そのドグマを根拠として生じたからである。
そのシルバーバーチがある日の交霊会で、司会者のハンネン・スワッファーとの間でこんな対話をかわしている。
スワッファー 「私の見る限りでは、今日の国教会はたしかに欠点もありますが、かつてよりは良くなっていると思います。英国民が進歩しただけ、教会も進歩しています」
シルバーバーチ 「なるほど。でも、それはかなり苦しい評価ですね。というのは、今日の国教会は、私から見れば現在かかえている悪弊の多くとは無縁だった初期の教会の後継者たるべきものです。はるか遠くさかのぼって、イエスの時代のすぐ後に設立された教会を見ならう必要があります。
当時は、わずかな期間だけではありますが、真の意味で民衆をわが子のように世話しようとする気概がありました。それが霊の道具である霊媒を追い出した時から道を誤りはじめました」
スワッファー 「三二五年のことですか?」
シルバーバーチ 「もっと前です。三二五年に霊媒と聖職者との分離が決定的となったということです。霊媒を追い出そうとする動きは、それ以前からありました。が、霊力の最良の道具である霊媒を追い出すことによって霊力を失い、聖職者が運営するだけとなった教会は次第に尊敬を失いはじめます。
もともと聖職者は、神の道具である霊媒とともに仕事をする者として尊敬されていたのです。自分でも霊媒と同等の価値を自覚していたのです。その仕事は俗世の悩みごとの相談にのり、霊媒が天界からの御告げを述べるというふうに、民衆が二重の導き、つまり霊と聖職者の双方からの導きが得られるようにすることでした。
ところが優越感への欲望が霊媒を追い出し、それといっしょに教会に帰属していた権威までもすべて追い出すことになりました。そのとき以来ずっと衰退の一途をたどることになったのです。
私が指摘したいのは、大主教のテンプルは真摯な気持ちでいる───そのことに疑問の余地はない。しかし、側近の中にはリーダーへの忠誠心を尽くしておくにかぎるといった考えから、口先だけの忠誠を示しているにすぎない者がいることです。そういう連中は改革事業などには情熱を持ち合わせません。
改革者などと呼べる人種ではないのです。おのれの小さな安全さえ確保しておけば、それでいいのです。事を荒立てたくないのです。何であろうと命令にだけ従っておくにかぎると心得ている連中です。
また一方には、教会が俗事に関わることを好ましく思わない連中もいます。さらに、戒律に背きたくない者、教わったことを忠実に守ることが何より安全と考える連中がいます。こうした様々な考えを持つ者が内部抗争のタネとなります。
一人の人間の〝それ行け〟の掛け声で全員が一斉に立ち上がるという具合にはまいりません。何らかの進展はあるかもしれません。しかし、意見の衝突が激しいことでしょう。》
・イエスは今も地上人類のために働いている
別の日の交霊会で、ナザレのイエスは今どういう仕事に携わっているのかということが話題となった。それにシルバーバーチはちょっぴり皮肉もこめて、こう答えている。
《誤解され、崇められ、今や神の座にまつり上げられてしまったイエス───そのイエスは今どこにおられると思いますか。カンタベリー大聖堂ではありません。セントポール寺院でもありません。ウェストミンスター寺院でもありません。実はそうした建造物がイエスを追い出してしまったのです。
イエスを近づき難い存在とし、人類の手の届かぬところに置いてしまったのです。神の座にまつりあげてしまったのです。単純な真理を、寓話と神話を土台とした教義の中に混ぜ合わせてしまい、イエスを手の届かぬ存在としてしまったのです。
イエスは今なお人類のために働いておられます。それだけのことです。それを人間が (神学や儀式をこしらえて) ややこしくしてしまったのです。しかも、今こうして同じ真理を説く私たちのことを、キリスト教会の人たちは天使を装った悪の勢力であり、サタンの声であり、魔王のそそのかしであると決めつけております。
しかし、キリスト教の時代は過ぎ去りました。人類を完全に失望させました。人生に疲れ、絶望の淵にいる地上世界に役立つものを、何ひとつ持ち合わせておりません。》
シルバーバーチによると、イエスは年二回、イースターとクリスマスに行われる指導霊ばかりの会議、つまり地球浄化のために組織されている世界各地の霊団の責任者が一堂に会する審議会を主宰しているという。その時期は交霊会も休暇となる。次に紹介するのは、ある年の休暇に入る直前の霊言である。
《この機会は私にとって何よりの楽しみであり、心待ちにしているものです。このときの私は、わずかな時期ですが本来の自分に立ち帰り、本来の霊的資産の味を嚙みしめ、霊界の古くからの知己と交わり、永年の向上と進化の末に獲得した霊的洞察力によって実在を認識することのできる界層において、生命の実感を味わうことができるのです。
自分だけ味わって、あなたがたに味わわせてあげないというのではありません。味わわせてあげたくても、物質界に生きておられるあなた方───感覚がわずか五つに制限され、肉体という牢獄に閉じ込められて、そこから解放されたときの無情のよろこびをご存知ないあなた方───たった五本の鉄格子の間から人生をのぞいておられるあなた方には、本当の生命の実感を味わうことはできないのです。
霊が肉体から解き放たれて本来の自分に戻った時に、より大きな自分、より深い自我意識に宿る神の恩寵をどれほど味わえるものか、それは今のあなた方には想像できません。
これより私はその本来の自分に帰り、幾世紀にもわたる知己と交わり、私が永い間その存在を知りつつも地上人類のために喜んで犠牲にしてきた〝生命の実感〟を味わいます。これまで大切に仕舞っておいたものをこの機会に味わえることを、私がうれしくないと言ったらウソになりましょう。
この機会は私にとって数あるフェスティバルの中でも最大のものであり、あらゆる民族、あらゆる国家、あらゆる分野の担当者が大河をなして集結して一堂に会し、それまでの仕事の進捗(シンチョク)具合を報告し合います。
その雄大にして崇高なる雰囲気は、とても地上の言語では表現できません。人間がインスピレーションに触れて味わう最大級の感激も、そのフェスティバルで味わう私どもの実感にくらべれば、まるで無意味な、ささいな体験でしかありません。
その中でも最大の感激は、再びあのナザレのイエスにお会いできることです。キリスト教の説くイエスではありません。偽り伝えられ、不当に崇められ、そして手の届かぬ神の座に祭り上げられたイエスではありません。
人類のためをのみ思う偉大な人間的存在としてのイエスであり、その父、そしてわれわれの父でもある大霊のために献身する者すべてに、その偉大さを分かち合うことを願っておられるイエスです。》
そのイエスが、死後、地球規模の大霊団を引き連れて〝地球浄化〟の神意を成就するために降下してくる様子はオーエンの 『ベールの彼方の生活』 の第四巻〝天界の政庁〟篇にでてくるが、その中で通信霊のアーネルが〝キリスト〟の概念について極めて意味深長なことを述べている。
・イエス・キリストとブッダ・キリスト
《地上の神学者は絶対神についてまでも、その本性と属性とを事細かくあげつらい、しかも断片的に述べていますが、吾々よりさらに高い界層の天使ですら、絶対神はおろか、キリストについても、そういう畏れ多いことはいたしません。
信仰だけは剥奪せずにおく方がよい人種がいるとはいえ、その種の人間からはキリストの名誉回復は望めません。それは、大胆不敵な人達、思い切って真実を直視し、驚きの体験をした人たちから生まれるのです。少なくとも偏見を混じえずに〝キリスト人間説〟を理解した人から生まれるのです。
実は、私はこの問題を出すのに躊躇しておりました。キリスト教徒にとっては根幹にかかわる重大性をもっているとみられるからです。ほかならぬ〝救世主〟が不当とも思える扱われ方をするのを聞いて心を痛める人が多いことでしょう。それだけに私は躊躇するのですが、それを敢えて申し上げるのも、やむにやまれぬ気持からです。
というのも、彼らのキリストに対する帰依の気持ちは、キリスト本来のものではない、単なる想像の産物にすぎないモヤのようなものから生まれているからです。
いかに真摯であろうと、あくまでも想像的産物であることに変わりはなく、それを作り上げたキリスト教への帰依の心は、それだけ価値が薄められ、容積が大いに減らされることになります。その信仰の念もキリストに届くことは届きます。しかしその信仰心には〝恐怖心〟が混じっており、それが効果を弱めます。
それだけに願わくはキリストへの愛をもってその恐怖心を棄て去り、たとえ些細な点において誤っていようと勇気をもってキリストの真実について考えようとする者を、キリストはいささかも不快に思われることはないとの確信が持てるまでに、キリストへの愛に燃えていただきたいのです。
同じことを貴殿にも望みたいのです。そしてキリストはキリスト教徒が想像するよりはるかに大いなる威厳をそなえた方であると同時に、その完全なる愛も、人間の想像をはるかに超えたものであることを確信なさるがよろしい。》
───キリストは地上に数回にわたって降誕しておられるという説があります。たとえばクリシュナやブッダなどがそれだというのですが、本当でしょうか。
《事実ではありません。そのことを詮索する前に、キリストと呼ばれている存在の本性と真実について理解すべきです。
ガリラヤのイエスとして顕現し、そのイエスを通して〝父〟を顕現したキリストが、ブッダを通して顕現したキリストと同一人物であるとの説は真実ではありません。またキリストという存在が唯一ではなく数多く存在するというのも真実ではありません。
イエス・キリストは父の一つの側面の顕現であり、ブッダ・キリストはまた別の側面の顕現です。しかも両者は唯一のキリストの異なれる側面でもあるのです。
人間も一人一人が創造主の異なれる側面の顕現です。が、すべての人間が共通したものを有しております。同じように、イエス・キリストとブッダ・キリストとは別個の存在でありながら共通性を有しております。
しかし顕現の大きさから言うとイエス・キリストの方が優ります。この二つの名前を持ち出したのは、たまたまそうしたまでのことで、他にもキリストの側面的顕現が数多く存在し、そのすべてに右に述べたことが当てはまります。
貴殿が神の心を見いださんとして天界へ目を向けるのは結構です。しかし、たとえばこのキリストの真相の問題で思案に余った時は、バイブルを開いて、その素朴な記録の中に兄貴として、また友人としての主イエスを見出されるがよろしい。その孤独な男らしさの中に、崇拝の対象とするに足る神性を見出されることでしょう。》
・神々による廟議
右と同じ著書の、一九一九年二月二十六日の通信に、更に意味深長な事実が披露されている。
───その〝尊き大事業〟というのは何でしょうか。
《それについてこれから述べようと思っていたところです。このテーマは、ここ何世紀かの出来事を理解していただく上で大切な意味をもっております。
まず注目していただきたいのは、その大事業は、これまでお話した界層よりさらに高い境涯において、幾世紀も前からもくろまれていたということです。いつの世紀においても、その当初に神界において審議会が開かれると聞いております。まず過去が生み出す結果が計算されて披露されます。
遠い過去のことは簡潔な図表の形で改めて披露され、比較的新しい世紀のことは詳しく披露されます。前世紀までの二、三年のことは全項目が披露されます。それらが、その時点で地上で進行中の出来事の関連性において検討されます。
それから同族惑星(※)の聴聞会を開き、さらに地球と同族惑星とをいっしょにした聴聞会を開きます。それから審議会が開かれ、来たるべき世紀に適用された場合に、他の天体の経綸に当たっている天使群の行動と調和するような行動計画に関する結論が下されます。悠揚迫らぬ雰囲気の中で行われるとのことです。》
(※発達の程度においても進化の方向においても地球によく似通った惑星のこと──訳者)
───それらの審議会においてキリストはいかなる位置を占めておられるのでしょうか。
《それらではなく、そのと単数形で書いてください。審議会はたった一つだけです。が、会合は世紀ごとに催されます。出席者は絶対不動というわけではありませんが、変わるとしても二、三エオン (EON 地質学上の時代区分の最大期間で、億単位で数える──訳者) の間にわずかな変動があるだけです。創造界の神格の高い天使ばかりです。その主催霊がキリストというわけです。》
───どうも有り難うございました。私なりに分かったように思います。
《それは結構なことです。そう聞いてうれしく思います。というのも、私はもとよりのこと、私より幾つかの上の界層の者でも、その審議会の実際の様子は象徴的にしか理解されていないのです。私も同じ手法で貴殿に伝え、貴殿はそれに満足しておられる。結構に思います。》
・地球的視野への意識改革を
以上で〝物質界への霊力の奔流〟という観点から見て、それが最も豊かに、そして自由に流入した時期───これを私は 「人類史の〝昼〟の時代」 と呼ぶ───が終わり、やがて黄昏(タソガレ)から闇の時代へと移行し、世界史に悪名高い〝暗黒時代〟が始まるわけであるが、この第一部を閉じるに当たり、これから筆を進めていく内容について読者にあらかじめお断りしておきたいことがある。
その一つは、私の観点はあくまでも人類の〝霊性〟の消長というところに置かれているということである。
どの歴史的事実にも、必ず裏と表とがあるもので、そのどちらに光を当てるかによって意義が違ってくる。卑近な例でいえば、日本の鎖国時代は近代化を著しく遅らせ、島国根性を大きく醸成したことは確かであるが、他方において、日本的文化を純粋に温存させ花開かせた時代でもあった、という見方もできるであろう。
ヨーロッパの暗黒時代がもたらしたものは何か、この命題について総合的な答えを出すとなると議論百出であろう。
本書を執筆するに当たって私も西洋史に関する書物を何冊か繙いてみたが、著者によって事実の述べ方に相違がみられるのみならず、同じ事実の捉え方述べ方にもニュアンスの違いが大きいことを知った。
たとえば同じローマ皇帝とキリスト教との関係について述べたものでも、著者がただの歴史家である場合と、クリスチャンである場合とでは、かなりの違いが見られる。そこにやはり偏見が入るということであろう。
そこで私の場合は、同じ歴史にスピリチュアリズムがもたらしてくれた霊的知識の光を当てながら、私独自の目によって見直してみたいと思う。
たとえば第一回ニケア会議においてコンスタンチヌス一派による大掛かりな陰謀があったことはシルバーバーチ霊が再三指摘しているが、一般の歴史書には、私が知るかぎり、その事実に触れたものは一冊もない。が、近代に至って紛れもなくそれを物語る資料が歴史家によって発掘され、それをまとめた本 『第一回ニケア会議の真相』 が発行されていることを知った私は、英国の古書店を通して、一年がかりでついに入手した。
通読してみて資料のすべてではないことが分かったが、たとえ断片的であっても、そうした新しい資料による検証によって歴史が書き変えられていくことは必然の成り行きであろう。
もう一つは───これはとくに日本人の読者ということで私が懸念していることであるが───霊的奔流の主流がユダヤにあり、その後の西欧の暗黒時代を地球人類の霊性の封殺とする私の見解を、国粋主義的な方は快く思わないであろうし、反対に、日ユ道祖論者、つまりユダヤの一種族が流浪の末に日本列島にたどりついたのが日本民族であると信じている人たちは、快く思うかもしれないということである。
大方の人たちは、日本には西欧の暗黒時代とは無関係に〝かんながら〟という素晴らしい霊的遺産が豊富に存在すると自負するかもしれない。
そうした問題について今ここでその是非を論じている余裕はない。私が申し上げたいのは、私にとっては国家の別、ないしは民族の違いは、基本的理解においては全く存在しないということである。そう述べる根拠は、ほかでもない、学術的霊界通信として名高い〝マイヤースの通信〟で明かされた〝類魂説〟にある。
すなわち、人間には身体上の先祖、つまり血でつながった先輩とは別に、霊性でつながった先祖、いわば〝霊的家族〟の集団があって、そこでは国家や民族の別はなく、霊的親和性によって結ばれた生活が営まれている。
そして、今こうして自分が日本で生活しているように、他の類魂はユダヤ人として、フランス人として、イギリス人として、あるいはインド人として、もしかしたらどこなの難民として生活しているかも知れない。しかも、もしかしたら自分は、来世では南アフリカ人に生まれ変わるかも知れない。ロシア人になるかも知れない。
要するにわれわれ地上人類は、一つの大きな共同体であり、自分の霊的な家族がどこのどの国のご厄介になっているかも分からないのである。そう理解したときから醜い人種的偏見が消え、愚かしい仲違や戦争は止そうという気持ちが湧いてこないだろうか。自分の家の前だけを掃除するようなケチ臭い根性は捨てて、地球全体を住みよい環境にしようという考え方が出てこないだろうか。
第二部 霊性の〝夜〟の時代
第一章 キリスト教徒への迫害
・イエス・キリストという名前
イエスなる人物が今日いうところのキリスト教の教祖でないことは、すでに述べた。
並はずれた霊的能力によって次々と〝しるしと不思議〟を演出しては霊的真理を説き、それが高潔な人格と相まって、イエスを慕うものが日毎に増えていった。その中から幾人かの弟子を選び、それらと行動をともにしたが、宗教としての〝組織〟はこしらえなかったし〝宗派〟を名のる看板を出したわけでもなかった。
第一、イエスは、生涯、定まった居所というものをもたなかった。インペレーターの次の一節は極めて大切である。
《イエスの生涯の特質は、威厳と謙虚の合体であった。威厳さと平凡さの結合にあった。威厳さが発揮されたのは誕生時と死亡時、その他、ヨルダンにおいて霊がイエスを試し、その使節を神聖なものと認めたときなど、その生涯の節目にいくつかみられる。住民はイエスがその生誕から死に至るまで尋常の人間でないことに気づいていた。
その生活が俗世間の社会的生活や家族関係によって束縛されるべき人物でないことを知っていた。と言っても、イエスをとりまく生活の和気あいあいたる雰囲気は、イエスにとって心地良いものであった。
それを住民はよく理解していた。聖書はそうしたイエスとの関わりについての叙述がきわめて不十分である。
イエスの言葉と行為が住民に及ぼした影響に関する言及があまりに乏しく、一方、いつの時代にもあるように、新しい真理に楯ついた当時の学者ならびに貴族階級の愚かしい誤解についての言及があまりに多すぎる。律法学者、為政者、パリサイ派、並びにサドカイ派の学者はこぞってイエスの敵にまわった。
今もしイエスが当時のありのままに教えを説いていたならば、現代の知識人、博士、神学者、科学者と呼ばれる階層の者も、こぞってイエスを嫌い、あるいは迫害もしかねないであろう。》
イエスは常に庶民の家に宿を取らせてもらい、病気治療をしても報酬はいっさい取らなかった。成功報酬として食事と衣料と宿を提供してもらうという形をとった。そうしたイエスの生活態度を見て人々は、旧約聖書にいう救世主(メシア)というのは、もしかしたらこの人ではないかと思うようになった。
が、一方、日毎に募っていくイエス人気を見て、当時の国教だったユダヤ教の指導者たちは自分たちの身の上に不安を抱くようになり、時のローマ総督ピラトに訴えて、イエスを亡き者にしてしまった。
ところが、墓に葬られているはずのイエスの遺体が消えていたことから、あの方はやはりユダヤ民族の救い主だったのだ ・・・・・・肉体を持ったまま昇天された・・・・・・またいつか救いに戻ってこられるはずだ ・・・・・・との信仰がひろまり、有志の間でイエスの〝しるしと不思議〟や〝教え〟を書き残す作業が進められた。
シルバーバーチによると、それは至って簡単なもので、今もバチカン宮殿に仕舞い込まれていて、今日までの二千年近く、一度も公開されたことがないという。そして三二五年のニケア会議の期間中にそれを大々的な書き改めと書き加えがなされ、それが今日の新約聖書となったという。
それはともかくとして、ユダヤ庶民のスーパーヒーローの悲劇的な最期と復活のうわさは、やはりイエスさまは〝救世主〟(クリストス)だという信仰を増幅させ、Jesus, the Christ (語源がギリシャ語の Christos )という呼び方をするようになった。
その時点では〝キリスト〟というのは尊称にすぎなかったのであるが、それがいつしかイエス・キリストという固有名詞となっていった。そういうイエス崇拝の信仰宗団を〝キリスト教徒〟と呼ぶのも、その時点としては適当ではないのであるが、便宜上そう呼ばせていただくことにする。
・暴君ネロに始まった迫害
初期のキリスト教徒の歴史は、迫害への抵抗の歴史であったといってよい。ローマは諸国を制圧して属州とし、イエスの時代のユダヤもローマの支配下にあったが、大体において宗教というものに対するローマ帝国の態度は寛大だった。
私はそれは、たぶん軍事大国の皇帝として、宗教とか信仰というものを理解する感性が欠けていたからであろうと見ている。
キリスト教を公認してローマの国教としたコンスタンチヌスにしても、その動機はいたって身勝手で、かつ幼稚なもので、敬虔なる宗教心などカケラもなかった。
それに関しては後で述べるとして、歴代のローマ皇帝は、西暦一五〇年ごろまでキリスト教徒への残虐きわまる迫害に始まって、一〇〇〇年ごろまで続いたローマ教会による知的弾圧、いわゆる暗黒時代、さらに十二世紀ごろから猛威をふるった〝魔女狩り〟という狂気の歴史に関わってきている。
迫害の最初の引き金となったのは西暦六四年のローマの大火だった。九日間にわたって燃え続け、ローマの大半を焼き尽くした。大帝国ローマの大失態の責任が自分にかかってくるのを恐れたネロは、その原因をキリスト教徒による放火であると決めつけて、おびただしい数のキリスト教徒を処刑した。というのが、タキトゥスという歴史家の著書『年代記』 の説である。
《そこでまず、信仰を告白していた者が審問され、ついでその者らの情報に基づき実におびただしい人が、放火の罪というよりむしろ人類敵視の罪と結びつけられたのである。彼らは殺されるとき、なぶりものにされた。すなわち、野獣の毛皮をかぶされ、犬に噛み裂かれて倒れる。》 (国原吉之助訳)
この中に〝人類敵視〟の罪というのが理解出来ないが、そういう曖昧な理由をこじつけたところに、すでにユダヤ教ナザレ派の信仰活動にローマが手を焼いていたことを窺い知ることができる。
『エンサイクロペディア・アメリカーナ』 によると、放火の犯人は実はネロ自身で、帝国議会はその責任の代償として、ローマ市を前よりさらに壮大な都市に立て直すことと、もう一つ、キリスト教徒を放火犯に仕立てて、徹底的に弾圧を加えることをネロに要求したという。
・邪霊集団の暗躍
ネロという人物はそれ以前の所業にも病的なところが見られる。母親と妻と、それに息子の家庭教師として雇ったローマの哲学者セネカまでを、死に追いやっている。まさに暴君の名にふさわしい皇帝だったが、その後継者たちも、ネロほどではなかったにしても、キリスト教徒の迫害と弾圧を行っている。
私は本書を執筆するに当たって、関係書を十冊ばかり読んだ。参考までに主なものをあげれば、新田一郎著 『キリスト教とローマ皇帝』 (教育社歴史新書)、 鈴木宣明著 『ローマ教皇史』 (同右)、 橋口倫介著 『十字軍』 (同右)、 浜林正夫・井上正美共著 『魔女狩り』 (同右)、 森島恒雄著 『魔女狩り』 (岩波新書)、 そして上田和夫著 『ユダヤ人』 (講談社現代新書) である。
とくに最後にあげた 『ユダヤ人』 は、右のネロに始まったユダヤ人キリスト教徒の迫害、中世における十字軍の虐殺行為、近代ではナチスドイツによるユダヤ人の大虐殺、ユダヤ人であるがゆえの差別といった。ユダヤ民族に対する一連の行為の原因は何なのかという問いに対する回答を見出したくて読んだのであるが、著者自身もその理由を見いだすことはできないと述べている。
そこで、人生百般に共通して言えることとして、私が本書で主張し続けているように、人間の霊的要素の存在を無視しては何一つ解決しないことを、ここで改めて指摘したい。
人類はこの地球上にあって、いつも目にしている動物や植物や小鳥、魚類などとともに生命活動を営み、しかもその頂点に立っているつもりでいるが、実際には目に見えない霊的存在───自然界では精霊、人間界では他界した人霊───による働きかけが大きく左右しているということである。
自然界の造化にいそしむ精霊は知的存在ではなく、上層界のデーバと呼ばれる高級自然霊の指示によって働いている、個性も自由意思も持たない存在である。したがって悪いこともしない。もっとも、わずかながら知性の発達した種類もいて、それが時折イタズラ半分に悪ふざけをすることはあるらしい。
たとえば田舎道で散々歩き続けたつもりだったのに、正気に返って見たら同じ場所をぐるグルまわっていたという話が時たま聞かされるが、あれはタヌキの仕業ではなくて、聖霊の一種がやるのである。タヌキの出そうな場所でそういう体験をしたところから、タヌキが犯人にされたのであろう。
また、死肉をあさるハゲワシのように、人間の死体から出る死臭をあさりに来る種類のものもいる、未開民族の葬儀の風習を見ると、禁じられていることがいろいろある中に、必ずしも迷信ではなく、死者の霊による祟りのほかに、その死者のまわりに集まるさまざまな精霊による禍から逃れるためと思われるものが、数多く見受けられる。
各種の霊界通信が異口同音に述べていることの一つに、死体は埋葬よりも火葬の方がよいというのがある。
死体に限らず〝もの〟が腐敗すると必ずウジ虫のようなものがわくように、目に見えない世界でも、死体を放置しておくとそういう薄気味悪い聖霊が発生するのである。地球上で火葬が徹底すれば、そういうウジ虫のような聖霊は地上から姿を消すはずである。
いずれにしても、その種の存在は、たとえ目に見えなくても普段は人間界とほとんど関わりはないので、まず気にかける必要はないが、日本では〝地鎮祭〟というのが行なわれる。基本的にはその土地に生息する精霊への挨拶と考えればよい。日本人の先祖が考え出した、世界に誇ってよい実に気の利いた風習で、ぜひとも守り続けるべきものの一つであろう。最も神主や施主がその本来の意義を理解していなければ何にもならないが・・・・・・
それよりもはるかに規模が大きく、かつ深刻で、油断のならないものに、かつて地上で生活した者で、非業の死を遂げたり、無念残念の思いの中で他界したり、たとえ罪科は明白であったにしても、処刑されて霊界入りした者たちが、同じ怨恨のもとに結集して地上界へ〝お礼参り〟を企んでいる霊の集団の存在がある。
・〝これからはお前たちの出番、闇の支配するときだ〟
「ルカ伝」 によると、イエスを捕えにきた者たちに向かってイエスは、そう言ったという。私の推察では、この時イエスは、その連中の背後に邪霊集団の存在を霊視していたはずである。憎たらしい笑みを浮かべて、してやったりと計略の成就に満足してたことであろう。
イエスは、霊性がふんだんに流入した〝昼〟の時代も自分の捕縛と処刑をもって幕を閉じ、急速に〝夜〟の時代へと入っていくことを察知していたと私は確信する。
私は今〝イエスは察知していた〟と簡単に述べたが、たとえ高級霊といえども、肉体に宿ったあともなお先在時代の知識を思い出すということは、至難のことなのである。それを理解していだたくために、少し話はそれるが、次のような事実を紹介しておきたい。
英国の物理学者で心霊学者でもあったオリバー・ロッジが言っているように、霊と物質とが結合するということは一種の異常現象であり、奇跡と言ってもよいほど大変なことなのである。
その最初、つまりこの地球上に初めて霊が物的身体をまとって生息するようになった時の具体的なプロセスは興味ある課題であり、いずれ機が熟せば稿を改めて世に問うてみたいと考えているが、現在では女性の子宮をキャビネットとして、十カ月をかけて地上環境に適応できるだけの抵抗力を身につけて大気中へ出産してくるというパターンが定着している。
その十カ月間の母胎内における霊と物質との関係も今後の研究にまたれる興味ある課題であるが、霊が肉体に宿るという言い方をした場合、大ていの人が、まるで肉体というカプセルの中にでも入りこむような、簡単なプロセスを思い浮かべられるのではなかろうか。
しかし、霊と物質とは宇宙における両極端の波動をもった存在であり、それが結びつくためには、霊の側が波動を物質の次元に近づける、つまり波動の調整が必要であり、それも幾段階かのプロセスがあるという。
その結果、先在時代および前世での体験の記憶などは意識できなくなるのがふつうで、シルバーバーチなどは、地球の大気圏に近づくだけでも息苦しくなる───霊的波動が鈍って意識がもうろうとしてくるいう。例えてみれば、われわれが水中深くもぐるのと同じ状態を想像すればよいのであろう。
大気圏に近づくだけでその状態であるから、もしもシルバーバーチが直接バーバネルの身体に宿ったら、本来の所属界のことが意識できなくなるであろう。それでは意味がないので、例のインディアンを中継役として使用した。
あのインディアンはいわば霊界の霊媒である。おなじみの肖像画はその霊媒のものであって、シルバーバーチ本人ではない。ただし、完全に一体となって仕事をしているので、あたかも自分がそのインディアンと同人物であるような言い方をしているだけである。
さて、これまでにも何度も述べているように、イエスは地球神庁の最高位の高級霊の一柱が肉体に宿ったもので、これは悠久の地球の歴史にあっても空前絶後のことであったろうと思われる。モーゼスの 『霊訓』 の続編である More Spirit teachings (拙訳) 『インペレーターの霊訓』(潮文社)の中でインペレーターが霊言でこう述べている。
《キリストが所有していた強大な霊力はとうてい皆さんには理解できません。完全な自己滅却が、人間界にあってなお神のごとき生活を可能にならしめました。その奇跡は天使の背後霊団によって演出されました。そしてその思想は、一つの気高い目的に集中しておりました。すなわち人類の福祉への献身です。
キリストは悠久の先在を有する高級霊の一柱が宿ったものであり、その高い界層においてもなお高い位にありました。人類の更生のための大事業はすべて、そのキリストを淵源としております。その聖なる影響力は、地上のいかなる暗き場所をも啓発しております。
これ以後も、人類の霊的受容力が開発されるにしたがって、その影響力がますます広がっていくことでしょう。
われわれは、そのキリストの御名のもとに参ります。そのキリストの霊力のお蔭をもって語ります。そしてそのキリストの祝福をみなさんにおあずけしてまいります。その上に安らぎを、安らぎを、安らぎを・・・・・・・。》
この事実から次の二つのことが推察される。一つは、地球の霊的サイクルの一日がそろそろ黄昏を迎え、これから〝夜〟の時代に入っていくのは避け難い摂理であるとしても、その闇の中に予見されている惨状は、まかり間違えば地上環境を完全な破滅へと追いやりかねないほど危険的なものであり、これに対処するには、最高責任者であるイエスみずからが降誕して霊性を注入し、かつその三十年に及ぶ物的体験によって霊力を強固なものにする必要があったということである。
そう結論づける根拠として、モーゼスの 『霊訓』 に次のような一節がある。
《さて、救世主イエスは神の使命を帯びて至福の天界における霊的生活より地上界へと降りられた。至純なる霊が一個の人体に宿り、ベツレヘムの飼い葉おけの中にて誕生した。ありとあらゆる不完全さと煩悩をそなえ、進歩のための唯一の手段である悲しみと誘惑と試練とから逃れられない、一個の人間となられたのである。
そこに進歩の唯一の手段としての、霊から物質への降誕の一つの典型を読み取ってもらいたい。悠久の過去から存在し続けて、必要かつ十分な発達をとげた霊が、他の手段では絶対に得られない、進化に不可欠の葛藤と試練とを求めて、いよいよ物質的身体による生活の場に降りたということである。
かくして人類の境涯へと誕生したイエスは、たちまちにして〝この世の君〟悪魔(サタン)による迫害に身をさらされた。時の権力者たちは一斉にイエスに敵対し、神の子であることの証を要求した。そして挙句の果てに、はりつけに処する命令を下した。イエスの説くところが彼らの主張するところと相容れなかったからである。》
《救世主の為せる仕事が地上生活の期間にのみ限られていると思うのは間違いである。イエスに場合に見られるごとく、真の影響は、その死後の余波にある場合がよくある。イエスの仕事はその三年間をもって開始されたのであり、そして今なお続いているのである。》
推察されるもう一つのことは、イエスほどの高級霊が地上へ降りたことを知って、暗黒界の大軍が総力をあげて、イエスを通して行われる霊界からの働きかけを阻止しようと躍起になったことである。つまり高級霊の大軍と低級霊の大軍との間で熾烈な戦いがあったはずだという見方である。
私見によれば、ユダヤ民族のその後の受難の歴史は、イエスという、地上に降誕した霊の中でも最高級の〝光の天使〟がユダヤ人として生をうけたという事実に対して、闇の勢力がユダヤ民族に嫉妬と反感を抱いたことに原因があるのではないかと考えている。言うなれば〝とばっちり〟である。
それにしては二千年も続くのは酷すぎると思われるかもしれないが、それは一日を二十四時間、一年を三六五日として数える地上的時間感覚から生まれるもので、宇宙的時間間隔からすれば、地球は今やっと一日を終えようとしているところであるというのが私の見解である。たった一日である。その一日の半分における出来事で、ユダヤ民族を〝悲劇の民〟と見なすべきではないと考えるのであるが、いかがであろうか。
第二章 ローマ帝国とキリスト教
・邪霊集団が狂気を増幅する
キリスト教徒への迫害は、ネロ以後も続いた。その後の迫害の特徴といえば、ローマの市民によるリンチ、虐殺といった形のものまで生じたことである。
こうした現象の背景には、蛮人の侵入、ペストの流行、飢饉、ティベル川の氾濫といった社会不安が生み出す狂気の群集心理が働いていることは事実であるが、さらにそのもっと奥には、そうした狂気を増幅させる邪霊集団のそそのかしがあったというのが、数々の霊界通信を読んできて得た私の推察である。
このあとで取り上げる十字軍の暴虐にせよ、魔女狩りの凄惨さにせよ、ただ人間どうしの関係だけであれば、目を被いたくなるような酷さにまでは発展しないはずである。そうなる前に〝良心〟がストップをかけるものである。その良心をマヒさせる見えざる力が働くところに怖さがある。
そうした邪霊集団の存在を正しく認識して、彼らにつけ入るスキを与えないようにする、あるいは、そういうスキを与える環境を未然に防ぐことが一般のわれわれの日常生活においても大切なのである。邪霊と人間との関係は、病原菌と人体との関係と同じと思えばよい。病原菌は至るところにウヨウヨしている。
目に見えないから平気でいられるだけで、実際に見えたら気味が悪くて一日も生活できなくなるであろう。そんな環境の中でも健康が維持できているのは、それにつけ入るスキを与えない、言い換えれば肉体をむしばませる条件を与えないだけの抵抗力があるからであることは既に常識である。
邪霊との関係も同じで、こちらが健全な心の環境さえ保っていれば、少しも怖くはないのである。
今、世界中で地球の環境破壊が問題化しているが、そうした問題にかまけて忘れてならないものに、心の環境破壊の問題がある。その問題は人間にとって最も大切な問題として、あとがきでも取り上げたいと考えている。
・悲しむべき〝政略婚〟───キリスト教の国教化
話を戻して、キリスト教徒に対するローマ帝国の迫害は、四世紀初頭のディオクレティアヌスの治世下における大迫害でピークを迎え、その後継者のガレリウスによる〝迫害勅令〟の撤回をもって、一応の終止符が打たれる。
そして、一転してコンスタンチヌスによる、キリスト教の国教化へと向かうのであるが、このコンスタンチヌス大帝のキリスト教への改宗が歴史家にとって不可解きわまる出来事であると同時に、キリスト教にとっては迫害以上に大きな不幸の始まりであったと言えよう。
これを機にキリスト教は、ローマ帝国の政略の〝錦の御旗〟として、権力の拡大と富の蓄積という、およそ宗教とは無縁であるはずの目的のための手段とされていくことになった。
その辺のいきさつの問題点をイエズス会司祭の鈴木宣明氏は 『ローマ教皇史』 の中で次のように述べている。
《コンスタンチヌス大帝自身の宗教性はどうであったか。これまで多くの論争がなされてきた。彼のキリスト教への改心は純粋に精神的・宗教的動機からではなかったであろう。
彼はその言葉によれば、迫害時代におけるキリスト教徒の勇気と信念に深い印象を感じていた。しかしキリスト教精神が普遍的であることが、何よりもローマ帝国の世界的支配を求める皇帝の心を魅きつけたと言える。彼は全キリスト教信仰共同体の基礎の上に新しい帝国政策を実現しようとした。
彼が初めてキリスト教を大きくしたのではなく、彼が迫害の中におけるキリスト教の偉大な内的生命力に深く印象づけられたので信仰の自由を承認し、そしてキリスト教を採用したのである。
特に彼は福音から知ったキリストの姿に魅了されて、キリストにおける世界の救済そして死から復活への真理、永遠の生命への道を説くキリスト教的福音の新しい思想に心奪われた。しかしまた、福音の倫理的実践の道が彼をキリスト教へと導き入れた。
彼の深遠かつ遠大な政治感覚は、帝国の不滅な確立と新しい国家秩序のために、キリスト教の信仰と倫理を活かす意義を認識したのである。しかしそこには危険な可能性が潜んでいた。教会は国家との緊密な関係を結び、国家の奉仕的道具になる危険にさらされていった。》
・コンスタンチヌスの二つの顔
そのキリスト教の国教化を決定した三二五年の第一回ニケア会議の目的と経過と結果については、その真相のあらましをすでに述べた。その資料つの一つである 『第一回ニケア会議の真相』 の著者 D・ダドレーは、その〝序論〟の中でいくつかの不審な点を挙げている。それを簡略に箇条書きにすると───
一. あれだけの重要なキリスト教の会議でありながら、バイブルの朗読の儀式が行われた形跡がない。
一. バイブルの内容の解釈が現代とはだいぶ違う。
一. 司教たちは、キリスト教がローマの国教とされると、にわかに自分で書物を書いてはそれを使徒や殉教者の名前をつけることをやっている。その一つが〝へブル人への手紙〟で、パウロのものとされているが、第一級の評論家でまともにそう信じている者はいない。
一. 〝ヨハネ黙示録〟もきわめて疑問の多い書である。四つの〝福音書〟にも、おかしな部分がいっぱいある。たとえば〝ヨハネ福音書〟の冒頭は〝初めにことばありき〟となっていて、〝ことば〟にギリシャ語の〝ロゴス〟を使っているが、教育らしい教育を受けていないガリヤラのヨハネが、ギリシャの大哲学者プラトンの用語をそのまま用いるだろうか。
こうした疑問を投げかけたあと、ダドレーは〝結局ニケア会議はクリスチャンに信仰の型を押し付ける典型をこしらえてしまった。出席した司教たちは、キリストと、キリストの復活への信仰をもってキリスト教の基本的教義であると考えるようになったのだと思う〟と述べている。
以上のダドレーの一連の説は正鵠を得ていると思う。イエスと同時代、さらにはそれ以前に生を受けた霊の証言によっても、バイブルが大幅に改ざんされていること、〝三位一体〟とか〝贖罪〟とか〝永遠の火刑〟といった説はぜんぶ他の宗教や神話・伝説からの借り物であって、イエスはそんなことは一言も述べていないことが明らかとなっている。
またスピリチュアリズムの観点から見ても、みな有り得ないことばかりなのである。
こうしてキリスト教が大きく方向を誤り、宗教としての存在意義を失って、政治的野望の手段となり下がっていった出発点がこのニケア会議であったことを考えると、これを発案し、主宰し、強引にキリスト教を国教としたコンスタンチヌスには、〝大帝〟という称号から受ける輝かしい皇帝像とはまったく異なる、もう一つの顔があったであろうことは容易に想像できる。
その点もダドレーはきちんと押さえている。『コンスタンチヌスの生涯』 と題して、いくつかの歴史家の文章を引用しながら、その〝もう一つの顔〟を浮き彫りにしている。その中から主だったものを紹介すると───
近世の歴史家 E・ギボンによると、コンスタンチヌスは自分の下臣たちには甘く、敵対者には恐怖をもって圧してきた英雄だったが、相次ぐ征服と、それによる富の蓄積によって次第に残忍性と放蕩性を増し、晩年は、そのために下臣の者からも尊敬を失っていたという。
コンスタンチヌスは二度結婚している。最初の妻は平凡な家庭の出で、クリスパスという男子を生んでいる。ユーセビウスによるとクリスパスは〝勇敢で敬虔〟な息子だったという。十七歳の時を初陣として、数々の先頭に出陣、宮廷内でも軍内部でも人民の間でも、なかなかの尊敬を受けていた。
ギボンによれば、その人気の高まりに父親のコンスタンチヌスは王の座に危険を感じるようになった。そこで息子を囚人同様に宮廷内に幽閉し、中傷のうわさを流させた。
さらには皇帝たる自分とローマ政府への陰謀を企んでいるとの容疑を側近の者にほのめかし、息子の寵臣を買収して密告者に仕立てた。その上でついに息子の逮捕と処刑を命じた。その時、コンスタンチヌスの実の妹コンスタンチアの一人息子も、共謀の罪で処刑されている。
わずか十二才だったという。母親の祈りと涙の嘆願にも冷酷だった。その心痛で母親も間もなく他界したという。
フィロストルギウスによると、コンスタンチヌスは結局二人の妻の両方とも殺しており、後継者の三人の息子はみな不義密通の子だったという。
こうした事実は、皇帝の側近の一人であったユーセビウスの著書 『コンスタンチヌス伝』 には一切述べられていない。ダドレーは 『コンスタンチヌスの生涯』 の最後を、あらまし次のように結んでいる。
《コンスタンチヌスは、知性の深さと洞察力においては〝大帝〟と呼ぶにふさわし人物ではなく、ただ抜け目がなく、機を見るに敏で、何事につけエネルギッシュで、その上際限のない野心に駆られて行動したからこそ、何よりも偉大な人物でも克服できなかったであろうほどの困難をしのいでいったまでのことである。
彼は自然科学については基本的原理すら知らなかった。そこから生まれる軽信性と迷信性が、唯一、彼の邪悪な性向を抑制する働きをしていた。が、ある時期から〝国の王〟たる自分と〝天の王〟たる神とを同等に考えるようになり、勝手に法律をこしらえ、好きなように臣下を殺し、敵に対しては剣でも火でも使って徹底的に報復してよいと思いこむようになった。そして、勝てばそれは神が許したことの証である───正しくなかったらその行為を許されなかったはずだ、という都合のよい議論で押し通した。
司教たちも彼におもねて、勝手な教えを説いた。たとえば、神は一人息子のイエスを人類の贖い主として地上へ送り十字架にかけられた。だから、国王たる者は国のためであればわが子を犠牲にしてもよろしいのです、と。
こんな気狂いじみた教えを真にうけてコンスタンチヌスは、その極悪性を感じぬまま、数々の血なまぐさい犯罪を重ねていった。その性格と行為とが、彼みずからでっち上げたキリスト教に暗い影を落とすことになる。》
ダドレーはそのあとで、英国の知性を代表するジョン・スチュアート・ミルの 『自由論』 から次の一節を抜粋している。
《ローマ皇帝の中で最初のクリスチャンとなったのがマーカス・アウレリウスでなくコンスタンチヌスだったことは、全歴史の中で最大の悲劇の一つである。
もしもキリスト教がローマの国教とされたのがコンスタンチヌスの治世下ではなくマーカス・アウレリウスの治世下であったなら、全世界のキリスト教がどれほど違ったものとなっていただろうと思うと、胸の痛む思いがする。》
第三章 人類の狂気───異端審問と魔女裁判
前章では、被征服国のユダヤ民族と、ユダヤ人霊覚者イエスの信奉者たちの集団を、ネロに始まる歴代の皇帝が迫害し続けた歴史をたどり、それがコンスタンチヌス大帝の時代に、一転してイエスをキリスト神の御子とする〝キリスト教〟がでっち上げられ、それがローマの国教とされるに至ったいきさつをのべた。
伝統的宗教というものを絶対視し、霊的真理の真実性に疑問を抱かない人、あるいは懐疑的になること自体が罪であると教えこまれている人は、こうしたコンスタンチヌスの行為を寛容精神の典型として賞賛こそすれ、西欧の暗黒時代の不吉な予兆と見なす意見には到底同意できないことであろう。
しかし、本章が取り上げる異端審問と魔女裁判という、〝人類の狂気〟ともいうべき悪逆無道がほかならぬローマ・カトリック教とプロテスタント双方の聖職者によって行われたという歴史的事実を一切の偏見なしに直視すれば、それを生み出した数世紀間のキリスト教に不健全なものがあったと断ずるのが妥当ではなかろうか。それを私は二つの要素に分けて見てみたい。
・〝しるしと不思議〟を忘れた身勝手な神学の罪悪
イエスを絶対神キリストの唯一の御子とする説は、キリスト教がローマの国教となってから言われ始めたもので、イエス自身はそんなことは言っていない。ましてや、自分が十字架上で流す血によって自分を信じる者の罪が贖われるなどとは、冗談にも言っていない。
後世の神学者がそういう教義をこしらえたのである。これを〝ドグマ〟(独断的教義)という。モーゼスの 『霊訓』 に次のような一節がある。
《われわれから見て許せないのは、神を見下げ果てた存在───わが子の死によって機嫌を取らねばならないような残忍非情な暴君に仕立て上げた幼稚きわまる言説である。
もしも神が人間と縁のない存在であり、すべてを人間の勝手にまかせているのであれば、神が罪深き人間のためにわが子に大権を委ねて地上へ派遣した事実を否定することが、永遠の火刑もやむを得ない大罪とされても致し方ないかもしれない。
キリスト教会のある教派はイエスの贖罪について絶対的な不謬性を主張し、それを受け入れない者は、生きては迫害、死しては永遠の恥辱と苦痛の刑に処せられると説く。それはそなたたちのキリスト教会においても比較的新しい説である。
が、すべてのドグマはこうして作られてきた。かくして、人間の理性のみでは神の啓示と人間のこじつけとを見分けることが困難、いや、不可能となる。同時にまた、その夾雑物を取り除かんとする勇気ある者が攻撃の的とされる。いつの時代にもそうであった。》
バイブルにいう〝しるしと不思議〟というのは、人間的知識と能力を超えた〝霊力〟の実在を見せつけたものであり、言うなれば、死後の世界の実在の証拠だった。スピリチュアリズムにおける心霊現象と同じである。
そしてイエスは、その死後の世界での幸せをもたらすのは、地位や名誉や財産ではなく人のために役立つことをすることだと説いた。神学のようなややこしい条件は述べていない。〝自分が他人からしてほしいと思うことは他人にも同じようにしてあげなさい〟という、マタイ伝に出てくる黄金律である。
ローマの帝国とキリスト教との関わり合いをたどってみて私が痛切に思うことは、その歴史が不幸へ、悲劇へ、暗黒へと向かって行った最大の原因は、いま述べた〝しるしと不思議〟の真意を理解せず、自分に都合のよい教義、いわゆるドグマをこしらえて、それを権力の拡大のための道具とし、イエスの説いた黄金律などクソ食らえといった風潮で押し通していったところにある。
それがやがて〝聖職〟という美名もとでの、およそ宗教とは正反対の悪徳の温床となって行く。それが私の指摘する二つの要素のうちの一つである。
・〝聖なるもの全てが逃げ去った〟聖職者の堕落と腐敗
コンスタンチヌスの治世下でキリスト教を国教としたローマ帝国は、その後コンスタンチヌスがビザンチンのコンスタンチノープルに移り住むようになったことがきっかけで、東ローマ帝国と西ローマ帝国に分けられる。
それは同時に一〇五四年の東西両教会の大分裂へ向けての、教義上の下らぬ兄弟ゲンカの始まりでもあった。インペレーターも烈しい口調で次のように述べている。
《地上のすべての民族に、それ相当の真理の光が授けられている。それをそれぞれの民族なりに最高の形で受け取り、それなりに立派に育て上げたものもあれば、歪められてしまったものもある。いずれにせよ、結局はその民族の必要性に応じて変形されてきた。
ゆえに、地上のいかなる民族といえども、真理の独占に誇り、あるいはそれを他民族に押し付けんとする無益な努力が許される道理はない。
地球が存在してきたかぎりにおいて、すべての宗教は───バラモン教もマホメット教もユダヤ教もキリスト教も───それ独自の特異な真理を授かってきたのであり、ただ、勝手にそれを真理の全てであると思い込んで、わが宗教こそ神の遺産の相続者であると自負したにすぎない。
その過ちをもっと顕著に示しているのが、ほかならぬキリスト教である。教会こそ神の真理の独占者であると思い込み、地上全土にそのランプの光を持ち歩かねばならぬと信じていながら、その実、教会内部において対立する宗派が最も多いのもキリスト教であるという事実が、それを何よりも雄弁に物語っていよう。
教会内の分裂、その支離滅裂の教義、互いに神の愛を独占せんとして罵りあう狂気の沙汰の抗争、こうしたことはキリスト教こそ神の真理の独占者であるという愚かな自負に対する、絶好の回答である。
それにしても、たる醜態であることか! 本来ならば神の本性を明らかにし、そうすることによって神の愛を少しでも魂に吹き込むべき神学であるものを・・・・・・ああ、それが事もあろうに宗派と分派の戦場と化し、児戯に類する偏見と見苦しい感情をむき出しにする不毛の土地と化し、神についての無知をもっともあらわにさらけ出し、神の本質と働きについて激しく非難し合う、わびしい荒地と化してしまうとは!
神学! これはもはやそなたたちキリスト者の間でさえ侮蔑をもって語られるに至っているではないか。神についての無知の証ともいうべき退屈きわまる神学書は、見苦しい悪口雑言、キリスト者として最もあるまじき憎悪、厚顔無恥の虚言の固まりである。
神学! 聖なる本能のすべてをかき消し、敵に向けるべき攻撃の手を同志に向け、聖者の中の聖者とも言うべき霊格者を火刑に処し、拷問にかけ、八つ裂きにし、礼遇すべきであった人々を流刑に処し、あるいは追放し、人間として最高の本能を堕落させ、自然の情緒をかき消すことを正当化するための口実としてきたではないか。
何たる悲しきことであることか。そこは今なお人間として最低の悪感情が大手を振って歩く世界であり、その世界から一歩でも出ようとする者を押し止めんとする。
「退(サ)がれ、退がれ! 神学のあるところに理性の入る余地などあるものか!」 これが神学者の態度である。真摯な人間を赤面させる人間的煩悩のほとんどすべてがそこにあり、自由な思索は息切れし、人間はあたかも理性なき操り人形と化している。
本来ならば神のために使用すべき叡智を、その様な愚劣な目的のために堕落させてきたのである。》
そうした宗派間の抗争とは別に、その抗争の土俵となっていたキリスト教会全体が、いつしか政治権力まで握っていたという事実を忘れてはならないであろう。森島恒雄著 『魔女狩り』 によると、法王権が最高度に伸びた時代の法王インノケンティウス三世は
「聖職者の権力が世俗の権力にまさるのは、あたかも霊魂が肉体にまさるのにもひとしい。・・・・・・キリストの代理である法王は、なにびとをも裁き、かつ、なにびとにも裁かれない」
と宣言したという。コンスタンチヌスが得意の絶頂期にそう考えて、邪魔になった親族や下臣を虫けらのように死に追いやった事実を思い起こすべきである。
ある司教は 「王侯の権力は教会に由来する。ゆえに王候は聖職者の下僕である」 と言った。またある司教は 「最下位の聖職者といえども王にまさる。諸侯とその人民は、聖職者の下臣である。それは輝く太陽に対する月にひとしい」 とも言っている。
私には、これは権力を手中にした者がいつしか陥っていく驕(おご)りのパターンとしか思えないが、森島氏は、この優越感は彼ら独自の崇高な使命感で裏づけされていた、と好意的である。つまりキリストが啓示した真理を教え、救いの恩寵をわかち与えて、すべての子羊を永遠の 「神の国」 へ導いてゆく牧羊者───その牧師の至高の使命を果たしうる者は聖職者以外にはいないのではないかという使命感があったという。
「ところが・・・・・・」 と森島氏も次のような、信じられないほどの聖職者の腐敗ぶりを述べている。
「その聖職者たちは、そのころ、腐敗と堕落の底におちこんでいた。免罪符の売買は常識となり、霊魂の救済は金銭的取引によって行われ、聖餐礼、死者のための祈り、臨終の喜捨、その他あらゆる儀式礼典はその本質を失って形骸化した。聖職売買は普通のことであり、聖職者は情婦をもち、ざんげ室は女をたらしこむ密室であり、尼僧院は赤線区域となっていた。・・・・・・」
私は、例によって、こうした退廃的堕落の背後に、霊界の暗黒集団、地上的快楽への妄執を今だに断ち切ることができない低級霊が存在し、それが良識による判断の限界を超えた痴態へと発展させていったと見ている。
それは現代でも同じことである。私が〝三大霊訓〟と呼んでいるモーゼスの 『霊訓』、 オーエンの 『ベールの彼方の生活』、 『シルバーバーチの霊訓』 の中でも特にしつこい邪霊集団の暗躍を指摘して警戒を呼びかけているのは、 『霊訓』 のインペレーター霊である。現代にもそのまま通じるものがあるので、煩をいとわず、いくつか抜粋してみよう。
《今まさに新しい真理の普及のために、特別の努力がなされつつある。神の使徒による働きかけである。それが敵対者の大軍によるかつてない抵抗に遭遇している。世界の歴史は常に善と悪との闘争の物語であった。片や、神と善、片や、無知と悪徳と邪悪───霊的邪悪・精神的邪悪・物的邪悪───である。
そこで時として───今がまさにその時期の一つであるが───尋常ならざる努力がはらわれることがある。神の使徒が一段と勢力を強めて結集し、人間を動かし、知識を広める。恐るべきは真理からの逃亡者であり、生半可者であり、日和見(ヒヨリミ)主義者である。こうした人種に惑わされてはならぬ。が、神の真理ゆえに迷うことがあってもならぬ。》
───解ります。しかし何をもって神の真理とするか、この判断に迷う者はどうすればよいのでしょう? 真剣に求めて、なお見出せぬ者が多いのです。
《切に求める者にして、最後まで見出せぬ者はいない。その道のりの長く久しい者はいるであろう。さよう、地上を去り高き界へ至ってようやく見出す者もいるかも知れぬ。神はすべてのものを試される。そして相応しい者にのみ真理を授けられる。
一歩進むにも、それ相当の備えがなされねばならぬ。それが進歩の鉄則である。適正あっての前進である。忍耐の必要なるゆえんである。》
───それは解るのですが、内部の意見の衝突、証拠を納得してもらえないこと、偏見、その他、もろもろの要因からくる障害はどうしようもないように思えます。
《そなたにそう思えるというに過ぎぬ。一体、何ゆえに神の仕事に抵抗しようとするのであろうか。もろもろの障害とな? われらが過去に遭遇した障害に比べれば、そなたたちの障害など、物の数ではないことをそなたは知らぬ。
かのローマ帝政の末期、放蕩と肉欲と卑俗と悪徳とに浸りきった地域から聖なるものすべてが恐れをなして逃げ去った、あの暗黒の時代にもしもそなたが生をうけておれば、悪が結集した時の恐ろしさを思い知らされたであろう。
その非情さは絶望のそれであり、その陰気さは墓場のそれであった。肉欲ただの肉欲のみであった。天使はその光景を見るに忍びず逃げ去り、その喘ぎを和らげてやることなど、とても及びもつかなかった。
実に、あるのはただ不信のみ。否、それよりさらに悪かった。世をあげてわれらを侮蔑し、われらの行為をさげすみ、すべての徳を嘲笑い、神を愚弄し、永遠の生命をののしり、ただ食べて飲んで放蕩三昧の日を送るのみであった。
まさしく堕落しきった動物同然の生活であった。さほどの悪の巣窟さえ、神とその使者は見事に掃き清められたものを! ああ、そなたはわずかな障害を前にして、それを〝どうしようもない〟と嘆くとは! 》
・宗教は〝組織〟を持つと堕落する
〝カトリック〟という用語はギリシャ語の Katolikos`現代英語の general ないし universal に相当する用語から来たもので、一般的ないし普遍的といった意味をもつ。
つまりローマ・カトリック教というのは、地上人類のすべてが帰依すべき宗教ということになる。当時のローマ帝国の支配力のすごさと思い上がりを物語っているが、その教会の主権者である教皇(法王)の権力が皇帝のそれをしのぐに至った時、教会の機構も次第にローマ政府と同じものになっていった。いわゆる聖職位階制組織(ヒエラルヒー)である。
宗教上の儀式はもとより、法律、財政、学問、芸術等々に、あらゆる面がローマ教会の統治政策によって支配されるようになった。中世の封建制度は、取りもなおさずローマ・カトリック教会の支配機構にほかならなかった。
が、ごく素直に考えてみて、神学という人工の虚構の上にあぐらをかいた組織が健全なものを生み出すはずはない。先に述べた聖職者の堕落という内部の腐敗はその産物の一つであるが、外的な産物として、そうした封建制度への不満を原動力とした宗教改革の機運が生まれてきた。十世紀から十一世紀のことだった。
教義をいかに飾り立て、儀式をいかに厳かなものにし、法衣をいかにきらびやかなものに仕立てようと、霊性というものを忘れ、あるいは誤解している司教や神学者たちが目指していたとものは、聖ではなく俗、つまりは、いかにして人民から税金と財産を吸い上げるかということでしかなかった。
『ローマ帝国興亡史』 という大著を著した十八世紀の歴史家エドワード・ギボンによれば、キリスト教は、一方では忍耐と無気力の教えをうまく説き、他方では有能な人材を司教職修道院に引き入れつつ国家の中の国家を作り、帝国の旺盛な活力を吸い取ったという。
また、十九世紀のフランスの歴史家エルネスト・ルナンの言葉によると、キリスト教はまさに〝吸血鬼〟のように古代社会の活力を吸い取り、無気力を呼び込んだ、という。しかし、私の観方を言わせていただけば、そもそも宗教というものは〝組織〟をもった時から堕落が始まるものなのである。
日本でも大小さまざまな宗教が生まれては滅んでいっている。中には現代にまで残っているものもあるが、それは宗教という名前が引き継がれてきたというにすぎず、中身は次第に変わってきている。いずれの教祖も、最初は何らかの霊的能力をもち、イエスと同じ〝しるしと不思議〟をみせることで大勢の人の心を引きつけた。
その当初においては純粋に霊的なものに魂の目を開かされた者のみが帰依し、教祖も信者も宗教という名にふさわしい生活を心掛けていた。しかし、その後の〝発展〟の仕方に二つのパターンがあるように思う。
一つは、その教祖みずからが慢心することから始まる。自分は途方もない大神ないしは高級霊の生まれ代わりであると思うようになる。信者たちにそう宣言し、信者たちもそう信じる。すると必ず野心が顔をのぞかせる。教祖さまにお目どおりするだけでも法外な金銭を取るようになる。
かつては一銭も取らず、慈悲心と奉仕的精神から病気治療を行っていたのが、今ではたとえ治らなくても大金を出させる。その段階ではすでに高級霊団から見放されているから、治るはずはないのである。
ところが信者の真理とは妙なもので、いったん信じ切ると、法外な金をとられながら少しもよくならなくても、それを不審に思わなくなってしまう。莫大な金をかけて作り上げた金ぴかの祭壇や、教祖の厳かそうな衣装に目がくらんでいるからでもあろう。
もう一つは、最後まで霊的自覚を失うことのなかった霊能者が他界したあとから始まるパターンである。それまでは帰依者による真心のこもった布施や喜捨によって賄われていた生活費が、その霊能者の他界と共に断たれることになる。
そのことに不安と危惧の念を抱いた家族や側近の者が、信者をつなぎとめておく手段を講じることを始める。〝しるしと不思議〟を見せる人はもういない。
そこでそれに代わる方策を考えださないといけない。そこから〝営業〟が始まるのである。その時点では、もはや霊性はカケラもなくなっている。
この後者のパターンを途方もなくスケールの大きなものにしたのがキリスト教だったというのが私の見方である。イエスは奇跡的な病気治療をしても、金銭はいっさい取らなかった。生活費はそうして治してもらった人たちによる喜捨によって賄われていた。
うわさを聞いて生地ガリラヤはもとより、シリヤ、ガラテヤ、エルサレム、ユダ、ヨルダンの向こうからも、続々と群衆が集まってきた。その時、もしイエスが慢心を起こして自分が教祖におさまり、大金をとっていれば、大堂伽藍をこしらえるのも容易だったはずである。
もしかしたら、そうやって〝ナザレ教〟でもこしらえていた方が、ローマ帝国の国教として歪められた形でのキリスト教となるよりは、世界人類にとって幸いだったかもしれないという見方も出来ないことはない。
しかしそれは、イエスという地上人類として空前絶後の高級霊に対して、不謹慎な見方というべきであろう。およそそういう俗気とは縁のない人物だったからである。
・十字軍の暴虐
さて、話を戻して、ローマ・カトリック教という大組織になってしまった宗教的支配態勢に対する不満は、まず南フランスから起きた。
革新家たちはローマ教会の形骸化した儀式典礼を拒否した。イエスによる贖罪説、幼児の洗礼などの教理を否定した。教会堂は不要であり、祈るのに場所は問わない───教会堂であろうと酒場であろうと馬屋の中であろうとかまわない。神の教会は建造物の中ではなく信徒の交わりの中にある・・・・・・彼らはそう主張した。
十字架さえも、キリストを虐殺した道具であり、焼き捨てるべきだと主張した。そして教会維持税の納入を拒否するようになった。
彼らは禁欲と使徒的清貧の手本を身をもって示しながら、熱心に福音を説いてまわった。それに共鳴する者の数も急速にふくれ上がり、その勢いは南フランスからドイツ、ボヘミヤ、北イタリア、スペインへと広がっていった。
ローマ教会は、彼らを〝異端者〟と呼び、〝正統派〟のカトリック教に改宗させようとして、いくつかの手を打った。が、ことごとく失敗し、その勢力のものすごさに脅威さえ抱くようになった法王インノケンティウス三世は、〝改宗〟ではなく、〝異端討伐〟のための軍隊を結成した。以後、断続的に二十年にもわたって凄惨をきわめた思想弾圧のための戦いは、こうして始まった。歴史に有名な〝十字軍〟である。
本稿を執筆するにあたって私は、この十字軍の歴史をいくつかの角度から読んでみた。その中で十字軍そのものを専門に扱ったものとして橋口倫介著 『十字軍』 が当然のことながら〝詳しい〟内容になっている。が、正直言って、ただの歴史の本、という印象を拭い切れないまま読み終えた。歴史家の書としてはそれでいいのであろう。
むしろ著者の個人的見解はさしはさむべきではないかも知れない。しかし、これほどまで残虐をきわめた、ただの暴徒と変わらない伝統的キリスト教徒の行為の数々を 「光輝ある足跡を歴史の上に残した」 と称賛しているのをみて私は、多分この著者はクリスチャンだろうと推察した。そこにやはり偏見がある。
その点 『魔女狩り』 の森島恒雄氏は、異端審問が魔女裁判へと移行していった過程を捉えて、 「異端審問の歴史・制度。性格が、本質的にはすべて〝魔女裁判〟の中に集約されている、という重要なことに気付いた」 (あとがき) と述べている。
さらに同じ〝あとがき〟の終りで 『科学と宗教との闘争』 の著者 A・D・ホワイトのことに言及し、敬虔誠実なキリスト教徒だったホワイトが、科学は宗教の敵ではなくむしろ宗教を高めるものであり、科学の敵は宗教ではなく神学的ドグマであることを繰り返し強調している、と述べている。
ここで、くどいようであるが改めて私の観点を述べさせていただくが、コンスタンチヌスがキリスト教を国教と定めて以来、〝神学者〟と称する霊的体験など何もない、したがって、〝しるしと不思議〟の意味がまるで理解できていない司教たちによって、〝三位一体〟とか〝贖罪〟といった教義が勝手にこしらえられていったことが、その後のキリスト教の政策を大きく誤らせ、暗黒時代を招くことになったのである。
こしらえられたという事実は、そうした教説の採択をめぐって愚かしい論争が繰り返されていることからも明らかである。〝教皇不謬説〟などと言った実に都合のよい教説もこしらえている。その〝絶対に間違いを犯すことのない〟法王が、ガリレオを異端審問の末に獄中死させている。
そして、つい先般、その死から三百五十年もたってから、現法王ヨハネ・パウロ二世が、あれは間違いだったという〝公式の声明〟を勿体ぶって出している。何という硬直した世界であろうか。
ほぼ二十年に及んだ十字軍による虐殺と掠奪の数々は、正常な良識をもつ人間の想像を絶するもので、まさに悪魔的だった。その具体例をあげることは、ここでは控える。むごすぎるからではない。これからまだまだ恐ろしい残虐行為が教会の手によって、しかも神の名において為されることになるからである。
・異端審問
二十年にも及んだ陥落と奪回の繰り返しの戦闘の末に、さしもの革新派は全滅した。ローマ教会による異端撲滅のための十字軍は一応その目的を達成した。が、その間の幾度もの教会の危機的状態の体験から、時の法王グレゴリウス九世は次のような異端者対策をまとめた。『魔女狩り』(森島恒雄著)から抜粋させていただく。
《異端者を向こうにまわして神学論争をたたかわすに十分な学識をもち、しかも異端者に非難されることのない高潔な人格をそなえ、なによりも、異端の防止と撲滅に宗教的熱意を持つという、この三拍子そろった適格者を選び出し、それに強力にして広範な権限を与え、管轄上の地域的制約を受けることなくどこの司教をも支配下に置き、もっぱら異端撲滅だけに専念することのできるような、そういう 「専門的な」 異端撲滅の恒久的な組織をつくること、であった。
残虐と不正と貪欲と欺瞞と衒学(ゲンガク)───あらゆる悪徳を駆使して、良心と思想の自由を圧しつぶし、幾万、幾十万、ことによると幾百万の人間を虐殺して、中世史に陰惨な影を投げる 「異端審問」 の制度は、この構想の実現であったのである。》
・
・魔女裁判(魔女狩り)
十一、二世紀のキリスト教会にはもはや〝霊性〟といえるものはカケラも無くなっていた。それを何よりもはっきりと証明しているのは、その時代を代表する大神学者トマス・アクィナスが大著 『神学大全』 の中で 「教会は異端者を死の危機から救う必要はない」 と述べていることである。この言葉の中に、アクィナスがどう弁明しようと許すことのできない、理性を失った悪魔性を見る思いがする。
当時のキリスト教会は、邪悪性に快感を覚える病的精神状態に陥った低級霊集団のとりこになっていたと私は見る。〝異端狩り〟という当面の目標を達成した教会は、こんどは〝魔女〟という、わけの分からないものを粛清の口実として、政策上の〝邪魔者〟を片っぱしから処刑していった。魔女といっても女ばかりとは限らない。男性もいたのである。
英語では witchで、英和辞典でもみな〝魔女〟〝女魔法使い〟〝鬼ばば〟等々、みな女性として訳出してある。これは明らかに間違いである。もしかしたらこの魔女狩りの歴史用語に影響されているのかも知れないが、といって〝霊媒〟や〝霊能者〟でもないので、私もここでは混乱を避ける意味で〝魔女〟という用語を用いることにする。
さて、政略上の〝邪魔者〟として粛清した例としては、歴代法王の中でも最も残忍にして陰湿、野心と貪欲と偽善と迷信、その他ありとあらゆる悪徳の上に、当代髄一の〝神学的博識〟を備えていたというヨハネス二十二世が、法王選挙をめぐって自分と対立した側の者数名を、即位後まもなく 「悪魔の力をかりて未来を占い、人を病気にし、死亡させた」 と言い、魔女的行為を拷問によって自白させ、処刑したという。(『魔女狩り』)
当時の有名な例としてはジャンヌ・ダルクの事件があるが、これは次の項で扱うことにして、その後、例によって天変地異や疫病の流行による社会不安心理が、そのすべてを魔女のせいにされるようになり、密告、うわさなどによって、まったく何の根拠もない、ごく普通の善男善女が片っぱしから逮捕され、裁判にかけられ、拷問の末に処刑されるようになった。
参考させていただいたもう一冊の 『魔女狩り』(浜林正人・井上正美共著)の〝序章〟冒頭を転載させていただく。
《人類はときどき狂気におちいることがある。しかも集団的に───。いちばんひどい例は、戦争の時である。戦争はいったん始まってしまうと、際限なくエスカレートしてゆき、敵を殺すだけでなく、味方の中でも戦争に非協力なものを殺しはじめる。
殺し方もしだいに残忍になり、ふだんはふつうの市民として平和に暮らしている人びとが、どうしてあんなにひどいことをしたのかと思うようなことを、平気でやってのける。日本軍の南京大虐殺がそうであったし、ナチスのユダヤ人虐殺がそうであった。
しかし、戦争のとき以外にも、集団的狂気としか思えないような残虐行為がおこることがある。十六世紀から十七世紀にかけて、主として北西ヨーロッパで吹き荒れた 「魔女狩り」 の嵐は、その一つの典型例であろう。
罪もない老婆が魔女という疑いをかけられ、ロープでつるし上げられたり、爪をはがされる、まんりきで骨が砕けるまでしめつけられる。焼きゴテをあてられる、熱した鉄の靴をはかされ、ハンマーで足をたたき潰されるなど、
考えてみただけでもゾッとするような拷問を受け、あげくの果てには火あぶりになったり、四頭の馬に手足をそれぞれ一本づつしばりつけられて四つ裂きにされるというような極刑に処せられたのだった。こうして殺されていった魔女の数の総数は数万とも数十万に達するともいう。
ふつうの人間の感覚でいえば、それは目をおおいたくなるような光景であった。人間のなかにはこういう残虐性がほんらいひそんでいるものなのであろうか。私はそうは考えたくない。しかしこれは疑うことを許さない歴史的事実なのである。したがってこの歴史的事実はそれとして解明されなければならない。
いったい人びとは何におびえて罪もない老婆をとらえ、死に追いやったのか。しかも、ルネッサンスと宗教改革という近代ヨーロッパの夜明けを告げる大きな思想運動がまさに高まりつつあった時代に、こういう暗黒の悲劇がくりひろげられたのはなぜなのか。どこで、どのようにして、魔女の血は流されたのか。
そしてこの惨劇に終止符をうつことができたのは、どういう力によるのか。こういう問題の解明は、やはり歴史家の仕事の一つであろう。人類の狂気をくり返させないためにも、歴史の暗黒面の解明を忘れてはならないのである。》
・ジャンヌ・ダルクの例
さきに私は〝魔女〟という用語のあいまいさを指摘したが、〝悪魔〟との関係は勝手な言いがかりであるとしても、逮捕され処刑された人々の中に霊的ないし霊媒的能力をそなえていた者が相当数いたであろうことは、想像に難くない。
〝オルレアンの少女〟こと、フランスのジャンヌ・ダルクは明らかに霊聴力を持っていた。
イギリスとフランスによる百年戦争のさ中、十二才だったジャンヌは精霊がよく遊びに来るといわれる森の中で〝天使〟の声を聞いた。最初は、まわりに誰もいないのでびっくりしたが、そのうち同じ声が繰り返し聞こえるようになった。
その内容は、いま南部に逃げているシャルルこそ正統のフランスの王たる人物だ。シャルルはきっとオルレアンを奪回することができる、ということだった。同じことが何度も聞こえるのでジャンヌはついにシャルルに直訴することを決意した。十六才の時だった。
その少女が何者であるかが分からない司教たちは、訴えてきたジャンヌの取り調べに三週間を費やした。が、ついにその霊示を神の声と信じて、シャルルの軍隊の指揮を命じた。そして霊示どおりにオルレアンを奪回し、シャルルはシャルル七世として王位についた。
ジャンヌ・ダルクは〝オルレアンの少女〟として大変な称賛をうけた。が、その帰途に悲劇が待っていた。シャルルの軍隊の中にイギリス軍と通じ合っていた連中がいて、ジャンヌを拉致して、イギリスへ王の人質として〝売った〟のである。
無能なシャルル七世は、その後ジャンヌを救うための手段を講じることなく、成り行きまかせだった。英国軍はジャンヌ・ダルクは魔女だったと決めつけ、オルレアンの奪回に成功したのは〝妖術〟のせいであるという訴状のもとに異端審問にかけた。ジャンヌ十九才の娘ざかりだった。 (以上 The book of Knowledge から)
当時の審問の内容がいかに支離滅裂なものであったかを知っていただくために、ジャンヌ・ダルクの場合の質問の幾つかを紹介してみよう。
「大天使ミカエルには頭髪はあったか」
「おまえはミカエルと聖カトリーヌに接吻したのか」
「おふたりを抱擁したとき、暖かく感じたか」
「お体のどの部分を抱いたのか、上の方か下の方か」
こうした愚劣きわまる尋問が、十六回も開かれた審問で、次々と出されたのである。そしてついに〝妖術者〟〝迷信者〟〝悪魔の祈祷師〟等々の罪状によって火刑に処せられた。しかもその処刑の途中で、燃える薪束をかき分けて、衣類の焼け落ちたジャンヌの下半身を立会人の聖職者たちにさらしてみせたという。 (森島恒雄著 『魔女狩り』)
・霊性の封殺
ここまで来ると、もはや評すべき言葉を知らない。しかし、こうした例が示すように、中世ヨーロッパの魔女狩りによって霊的能力をもった者が徹底的に根絶やしにされたのである。心霊治療家の M・H・テスターは Learning to Love (拙訳 『現代人の処方箋』 潮文社の中で次のように述べている)
《私は、今日の地上世界が抱えるさまざまな問題の根本原因の一つに、キリスト教会がほぼ一千年にわたって霊的・思想的・科学的に成長を止められたことにあると確信している。
〝暗黒時代〟と呼ばれているその期間に、キリスト教会はまるでマフィアのように、当時の人間の精神、想像力、霊的ならびに心霊的生活、そして物質文化の発達を徹底的に牛耳った。
心霊能力を持つ者は片っぱしから火あぶりの刑に処せられたり拷問を受けたりした。かくして遺伝的要素の大きい心霊能力が事実上根絶やしにされてしまった。思想上でも、キリスト教の正式の教義以外はすべて禁じられた。
科学は魔術と同類に扱われて、何でもかでも容赦なく否定された。西洋文明は完全にキリスト教会の鉄のごとき掌中に収められ、そして息の根を止められてしまった。
その目的は何だったのか。それはほかでもない、その絶対的な締めつけの体制を脅かすことになりかねない教育、知識、権威、あるいは能力を持たせないようにすることにあったのである。
かくして西洋世界は一千年にもわたって進歩と科学的研究と心霊的発達と霊的進化の機会を失ってしまったのである。他のいかなる原因にもまして、このキリストという宗教が、悲劇と戦争と死者と苦しみと不安と無知を生み出してきたのである。今こそ、それを認識すべき時期がきている。》
・スピリチュアリズムは〝霊性のルネッサンス〟
こうした語調でテスターはキリスト教の罪悪を徹底的に検証している。それは決して単なるアラ探しではない。
そうせずにはいられない心霊治療家としての深刻な理由があるのである。欧米のキリスト教国の患者を数多く治療してきた経験から、器質的なものにせよ心身症的なものにせよ、その病的状態を誘発した根本的原因として、キリスト教的ドグマから生じる罪悪への恐怖心があるというのである。
良心の呵責とは本質的に異なるもので、罪でもないものを罪ではないかと思い込む、その不安と恐怖の積み重ねが精神を歪め、ひいては肉体までも冒してしまったケースが信じられないほど多いとテスターは言う。それほどまでにキリスト教神学は、西欧人の霊性を抑圧してきたということである。
ここで念のために申し添えるが、テスターの診断をキリスト教団に限ったことと考えてはならない。それだけのことであれば私は敢えて課題として持ち出すことはしない。歴史に関心をお持ちの方ならば、こうしてみてきたローマ帝国とキリスト教との関わりの中で非人間的行為───迫害・抑圧・搾取・虐殺等々──は、スケールこそ違え、世界各民族において続けられてきたことをご存知であろう。そして今なお〝虐殺〟を報じるニュースが絶えない。
また、第一次大戦は火薬というものを使用した最初の大量殺戮行為であり、第二次大戦ではそれに原子爆弾が加わって、わずか数年間で数百万の人命を奪った。
しかも今日では各種の核兵器の量産によって、一瞬のうちに敵も味方ももろとに、否、敵でも味方でもない他の民族も巻き添えにして、地上人類という〝種〟を絶滅してしまう危険性すら抱える事態に至っている。
実は、人類がいずれこうした事態に立ち至るであろうことは、地球神庁ではイエスの降誕以前から予測していた。
さらに私の大胆な推察をもう一度述べさせていただけば、イエスの地上への降誕は、地上世界の霊性回復の運動すなわちスピリチュアリズムの推進にそなえて、最高責任者としての霊力の強化という目的があったものと信じている。 『インペレーターの霊訓』 の中に次のような〝霊言〟がある。
《苦難の時代が近づいております。いつの時代にも、真理が顔を出せば必ずそれを目の敵(カタキ)にする反抗勢力が結集するものです。平和が乱されることを嘆く者がいるのも無理からぬことですが、真実を虚偽との戦いの中に、神の真理の火花を打ち出す好機を見いだす才覚のある者には、混乱もまた喜ぶべき理由が無きにしもあらずなのです。
戦争と激動を覚悟しなければなりません。苦難と混乱を覚悟しなければなりません。そしてまた、キリストの再臨を地上への再生と信じる者が引き起こすであろう抵抗も、大いに覚悟しなければなりません。今、〝キリスト的〟と呼ばれる時代が終焉を迎えております。
キリストは霊として、また霊力として地上へ戻り、人類の魂を解放するための新しい啓示をもたらしつつあります。
それを受ける霊媒が背信あるいは不信心ではなかろうかと恐れることは、実は、これより良い種子が蒔かれていく休閑地のようなものです。迷信的教義によってがんじがらめにされた精神の方が、何の先入観もない精神よりはるかに有害です。信仰をもたない者が多いことを恐れることはありません。
新しい真理が注ぎ込まれるためには、先ず無垢な受容性がなければなりません。
キリストの生涯には当時のエルサレム、キリストが涙を流して嘆かれたという都市だけではなく、現代の都会にも当てはまる予言めいた言葉があることに気づかれるでしょう。
ご自身が生きた時代だけでなく、皆さんの時代をも見通しておられたのです。エルサレムへの嘆きは、そのまま皆さんが運命を共にしている人々にも向けられてよいものです。今や金銭が神の座を占めております。まん延する贅沢と怠惰の中に、堕落の要因があります。
どうか、これから始まる最後の闘争にそなえてください。それは善と悪との闘い、信仰心と猜疑心との闘い、〝法と秩序〟対〝無法と放縦〟の闘いです。キリストが予言した嘆かわしい不幸の時代となるでしょう。それが暗黒の勢力、つまり悪魔のしわざとされるでしょう。〝聖霊を汚す〟罪が横行することでしょう。
そうした中にあって確固たる信念を失わずにいる者は幸いです。煩悩に負けて堕落していく者が多いのです。なかんずく、いったん霊的光明を見ながらそれを拒絶した者は、この地上においても、来たるべき霊の世界においても、救いはありません。
今まさに、キリストの再臨の予言が現実となりつつあります。キリストは〝助け主が訪れる〟と述べておりますが、〝助け主〟とはキリストの霊による影響力のことです。それが今、現実に成就されつつあります。地上を去って至福の境涯へたどり着いた霊が、いまふたたび地上圏へと戻ってきて活躍しております。
その余波は最初は不協和音の増幅、邪霊集団による活発な反抗活動、既成権力の狼狽という形で現れます。霊力の流入は反抗勢力を活気づけ、また新しい真理の到来に必ずともなうところの頑迷と偏狭が、なりふりかまわずムキ出しにされます。
われわれは今、二つの敵対勢力の真っ只中におります。片や光明より暗黒を好む邪霊集団であり、片や進歩的なものをすべて毛嫌いする地上の退嬰的人間です。人間界の日常の出来事がどのように霊によって支配されているかについての知識を世間一般に得心させることに、われわれはほぼ絶望的となっております。
その働きかけが五感に反応せず、また霊の動きが目に映じないために、そうした概念を捉えることができないのです。
来るべき時代を担う世代が、外見からは理解出来ない方法でその働きかけを受けつつあります。地上各地に霊的影響力の中枢が形成されつつあります。他方、人間の霊性の衰退と邪霊集団のばっこが、われわれにとって悩みのタネを次々ともたらしております。
人間界において善なるものが進歩することに反抗的態度をつのらせている霊たちです。が、いずれは霊力のほとばしりが地上のすみずみまで浸透して、そうした勢力を内紛状態へと追いやり、受け入れ準備の整っている魂が渇望している真理のメッセージを届けることになるでしょう。
真摯な魂による祈願は、神の霊力の豊かなほとばしりを求め、信仰厚き魂が真理のために結束してくれることを求めるものであらねばなりません。常に未来に目をやり、決して絶望してはなりません。敵対する勢力のすべてが結束しても、味方となってくれる神の勢力の方がはるかに大きいのです。》
付記───本章で私が概説したキリスト教会による陰惨きわまる所業について疑念を抱かれる方、反論されたい方、あるいはもっと詳しく知りたい方は、私が本書を書き上げたあとに発表された 『教皇庁の闇の奥』 (遠藤利国訳──リブロポート) をひとまずお読みいただきたい。一〇〇〇ページになんなんとする大著で、実を言うと、私はまだ最後まで読み終えていない。分厚すぎるからではない───読みかけてはその陰惨さに嫌気がさして閉じてしまうのである。
第三部 霊性の〝夜明け前〟